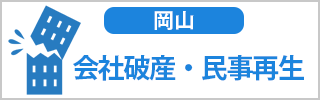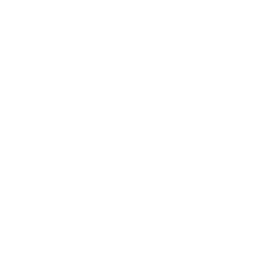知的財産・特許権の法務に強い弁護士
知的財産は企業の大切な資産・権利です
知的財産というと概念的ですが、実は企業経営にとても身近で重要な問題です。知的財産権には、特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権・営業秘密などがあります。具体的には企業が独自に開発した技術、デザイン、ロゴマークなどが該当し、大企業だけでなく、中小企業にとっても、経営上極めて大切な資産・権利なのです。
知的財産に関する典型的な法律問題には、以下のようなものがあります。
・競合他社が、自社が特許を有している技術を無断使用して、商品を開発・販売している
・競合他社から、自社の商品が特許権を侵害している、との警告書が送付されてきた
・競合他社が、自社にそっくりのロゴマークを使用している
・競合他社が、自社にそっくりの商品名を使用している
・他社が特許を持っている技術のライセンスを受けて、製品を開発したい
このような場合は弁護士にご相談ください。特許や商標の申請などは弁理士(特許事務所)の業務領域ですが、知的財産に関する紛争・トラブルは弁護士の業務領域です。もちろん、弁護士が各専門分野の弁理士の先生と協力しながら、事態に対応することが極めて重要です。
特許権の基礎知識
特許権は、20年間、特許を受けている発明を業として(すなわち、事業のために)、独占的に実施することのできる権利であり、特許の設定の登録をすることにより発生します。
本記事では、特許権に関する基礎知識について解説していきます。
「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいいます。すなわち、発明といえるためには、①自然法則を利用したものであること(自然的法則ではない、数学上の公式や人の精神活動などのみを利用したものは除かれます。)、②技術的思想であること(技能や、単なる情報の提示などは除かれます)、③創作、すなわち新しいものを作り出すものであること(単なる新しい事実を発見のようなものは除かれます。)、④高度のものであること(高度性)の4つが必要となります。
もっとも、高度性について、特許庁の特許・実用新案審査基準においては、「『発明』の定義中の『高度のもの』は、主として実用新案法における考案と区別するためのものである。よって、審査官は、発明該当性の判断においては、考慮する必要はない」とされており、特許の登録審査においては考慮されていないようです。
また、特許制度は産業の発達のために存在するので、さらに、発明が産業上利用可能なものであることが要求され、①人間を手術、治療または診断する方法の発明、②業として利用できない発明、③実際上、明らかに実施できない発明は、産業上の利用可能性が認められず、特許を受けることのできる発明にはあたりません。
産業上利用することのできる発明であっても、①特許出願前に公然と知られていた発明や実施されていた発明、②特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が公知の発明に基づいて容易に発明をすることができたときは、特許を受けることができません。
すなわち、既に知られてしまっている発明や、既存の発明から容易に思いつくことのできる発明は、特許を受けることができない、ということです。
なお、出願しようとする発明が公知ではないことを新規性、公知の発明に基づいて容易に発明することができないことを進歩性と呼びます。
「実施」とは、①物(プログラム等を含む。)の発明については、その物の生産、使用、譲渡等、輸出もしくは輸入または譲渡等の申出をする行為、②方法の発明については、その方法の使用をする行為、③物を生産する方法の発明については、その方法を使用する行為、及びその方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入または譲渡等の申出をする行為を差します。
特許権が発生することにより、特許発明の実施を専有(独占)することができます。
特許権の侵害とは
特許権者から実施を許諾されていない第三者が、業として特許発明を実施する場合などには、特許権の侵害となります。
特許権の侵害にあたるかどうかの判断については、問題となっている特許発明が保護される範囲がどこまでかを定める必要があります。
特許発明が保護される範囲は、特許権者が特許出願の際に特許庁に提出した願書に添付した特許請求の範囲(「クレーム」と呼ばれます。)の記載を基準に定められます。
そして、特許権侵害が成立するためには、対象製品または対象方法がクレームに記載された構成要件のすべてを充足することが必要であり、侵害態様が特許発明の構成要件を一部でも欠く場合には、特許権侵害は成立しません。
対象製品または対象方法が特許権侵害にあたるかどうかは、原則としてクレームの文言の解釈によって判断されます。
他方で、クレームの文言を厳格に解釈してしまうと、特許請求の範囲に記載された構成の一部を特許出願後に明らかとなった物質・技術等に置き換えることによって、特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができてしまうなど、特許発明の保護として不十分なものとなってしまいます。
もっとも、最高裁は、以下の要件を満たす場合には、特許請求の範囲に記載された構成中に、相手方が製造等をする製品または用いる方法(以下「対象製品等」といいます。)と異なる部分が存在している場合であっても、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するという判断をしています(最判平成10年2月24日)。
このような、特許発明と異なった製品等に対し、均等と評価できる場合には特許権の効力が及ぶとする考え方を「均等論」といいます。
①:当該異なる部分が特許発明の本質的部分ではないこと
②:当該異なる部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであること
③:②のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであること
④:対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一または当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものであること
⑤:対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情がないこと
特許権の侵害にあたるのは、原則として特許発明の構成要件の全てを実施する場合であって、特許発明の構成要件の一部の実施などは、原則として特許権の侵害にあたりません。
もっとも、特許製品の模倣品の部品の生産のように、構成要件の全てを充足しない場合であっても、特許発明の実施にのみ使用する物の製造、販売行為などによって特許権が直接に侵害される危険が高まり、特許権の保護として十分ではありません。
それゆえ、特許法上、特許権の直接侵害が誘発される可能性のある以下のような行為は、特許権の侵害行為とみなされています。
①:特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入または譲渡等の申出をする行為
②:特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であってその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入または譲渡等の申出をする行為
③:特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等または輸出のために所持する行為
④:特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる 物の生産、譲渡等若しくは輸入または譲渡等の申出をする行為
⑤:特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であってその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入または譲渡等の申出をする行為
⑥:特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての譲渡等または輸出のために所持する行為
※例えば、模倣品の部品を製造する行為は、①にあたり、特許権の侵害とみなされます。
競合他社が、自社が特許を有している技術を無断使用して、商品を開発・販売していると思われる場合は、弁護士にご相談ください。
一見して、競合製品が自社と同じものを作っていると思われる場合でも、実際に特許権を侵害しているかどうかは慎重に検討する必要があります。
弁護士にご相談いただければ、貴社の技術に関する特許だけでなく、周辺の従来技術などを丁寧に調査した上で、最適な対処方法をご提案いたします。
調査の結果、競合製品が貴社の特許権を侵害していると考えられる場合は、警告書を送付し、当該製品の製造・販売の差止請求をしたり、これに伴う損害賠償請求を行います。
逆に、競合他社から、自社の商品が特許権を侵害している、との警告書が送付されてきた場合、早急に弁護士にご相談いただく必要があります。
こういった場合は、回答期限を切って、差止請求や損害賠償請求を行ってくることが通常ですので、一刻の猶予も許されません。
直ちに、相手方が主張する特許権の内容を把握し、本当に自社製品がこれを侵害しているのか、最悪、これを裁判所が特許侵害と認定した場合にどのような損害が発生するのかを判断し、然るべき対応を取らなければなりません。
あくまでも相手と争って勝ち目があるのか、場合によっては勝ち目が無く、損害を最小限に留めるために相手と交渉すべきなのか、という判断が必要になる場合もあります。
技術的な問題で調査に相当の時間を要することもありますので、その意味でも、出来るだけ早く弁護士にご相談されることをお奨めいたします。
知的財産・特許の権利侵害をされた時に弁護士ができること
知的財産は見えないアイデアや信用などを保護するものですが、一度権利が侵害されると、その回復は簡単ではありません。そのため、権利を取り戻すためには、知的財産権の侵害に迅速に対応する必要があります。権利行使としてできること
「もしかして権利が侵害されているかも」と思ったら、どうぞお気軽に西村綜合法律事務所へご連絡ください。
権利行使の例
差し止め請求、損害賠償請求、信用回復措置請求は、知的財産・特許権侵害が発生した際に権利者が取ることができる法的措置です。
差し止め請求
たとえば、競合他社が特許を侵害して特定の製品を製造・販売している場合、特許権者は裁判所に申し立てを行い、その活動の停止を求めることができます。
この請求が成功すると、裁判所は侵害者に対してその製品の製造や販売を直ちに停止するよう命じます。この措置により、さらなる権利侵害の発生を防ぐことができるため、特許権者の権利を有効に保護する手段となります。
損害賠償請求
損害賠償請求は、侵害行為によって生じた経済的損失を回復するために利用されます。
この請求では、侵害行為によって特許権者が失った予想売上、または侵害者が侵害行為から得た利益を基に損害額を算定します。具体的には、会計書類や市場分析を基に、どれだけの販売機会が失われたか、または侵害品が市場でどれだけの利益を生んだかを評価し、その額を損害賠償として請求します。
知的財産・特許におけるトラブルでの損害賠償請求は非常に難易度が高いため、弁護士へ相談することが望ましいでしょう。
信用回復措置請求
信用回復措置請求は、知的財産・特許における権利侵害行為によって企業の評判が損なわれた場合に行われます。
侵害事実の公表や謝罪広告の掲載を通じて、公に企業の名誉を回復し、消費者やその他利害関係者からの信頼を再構築するための措置です。
例えば、侵害者がメディアを通じて謝罪することや、裁判所の判決を公表することが挙げられます。
権利侵害を弁護士に依頼するメリット
弁理士と共同して、権利侵害を精査し、より効果的な対処が可能です
弁護士は、弁理士と共同することで、特許権の範囲や侵害の事実を正確に分析することが可能です。
たとえば、競合他社が特許を侵害しているかどうかを判定する際、弁護士は、弁理士とともに、特許請求の範囲を詳細に調査し、製品や技術が特許の範囲に該当するかを検証します。また、製品の分解や成分分析など、技術的な調査を行うことで、法的な主張を裏付けるための具体的な証拠を収集します。
これにより、単に感情的に「侵害されている」と主張するのではなく、科学的、技術的な根拠に基づいた堅固な法的対策を講じることが可能になります。
相手との交渉を一任でき、本来の仕事に専念できます
弁護士に交渉を一任することで、企業は日々の活動に集中できます。
これには、侵害者との連絡および解決策の提案、そして必要に応じて和解交渉や契約の締結が含まれます
相手からライセンス収入獲得も視野に入れた交渉が可能です
特許侵害問題をただ争うだけでなく、場合によっては侵害行為をライセンス契約に転換させることが戦略的な選択となることがあります。
弁護士は、侵害者との交渉を通じて、適切なライセンス料の設定や契約条件の交渉を行います。そのため、場合によっては敵対関係をビジネスチャンスに変え、継続的な収入源としてのライセンス契約を確立することが可能です。
これは、特に中小企業やスタートアップにとって、迅速な市場展開と収益化の機会を得ることにも繋がります。
権利侵害してしまった(警告を受けた)時に弁護士ができること
相手から権利行使をされた際の対処
侵害ではない旨を適切に反論する
特許権侵害の申し立てを受けた場合、まずは侵害が実際にあったかどうかを精査します。
例えば、申し立てられた特許内容と自社の製品や技術が実際に一致するか、特許請求の範囲に本当に該当するのかを詳細に検証する必要があります。
専門的な分析や法的な解釈が必要ですので、弁護士や弁理士などの法律の専門家へ相談しながら進めることが一般的です。
正当事由があった旨を主張する
特許侵害が指摘された場合には、その使用が何らかの法的な例外に該当する可能性があるかどうかを検討します。
例として、研究目的での使用や、すでに市場に出回っている製品の改良など、特定の条件下で許可される活動があります。
また、同じ技術が公知である場合や、先行技術により既に公開されていた場合は、その事実を根拠に正当な使用であると主張することができます。
その権利が無効であると主張する(審判・裁判を起こす)
特許権の侵害申し立てに対して、その特許自体が無効であるという反論を行うことも一つの手段です。
特許が新規性や進歩性を欠いている、あるいは特許登録の過程での手続き上の瑕疵がある場合には、審判や裁判を通じてその無効を主張します。
ここでは、関連する先行技術の調査や、特許登録時の文書の再検証が行われ、特許庁や裁判所に特許の無効を訴えることになります。
権利行使された時に弁護士に依頼するメリット
権利者の主張や証拠を精査し、適切な反論が可能です
弁護士は、弁理士とともに、特許法や知的財産法の専門家として、権利侵害の申し立てに対して緻密な検証を行います。
具体的には、相手方が提出する証拠(特許文書、技術データ、市場の販売情報など)を徹底的に分析し、その主張の正当性を問います。
例えば、相手が特許権を侵害されたと主張する場合、その特許の請求範囲とあなたの製品や技術が実際に一致するかどうかを詳細に検討します。
もし不一致があれば、その点を明確にして効果的に反論し、訴訟での主張やその根拠とします。
権利侵害をしてしまっていても、負担を最小限に留めた解決を図ります
万が一権利侵害があったとしても、弁護士は事態の悪化を防ぎつつ、和解交渉に向けて行動します。
和解により、裁判による高額な費用や時間、企業の評判への影響を避けることができます。和解交渉では、侵害された権利者との間で合意に達するための損害賠償額の調整や、将来にわたる利用条件を設定することが一般的です。
状況に応じてライセンス契約を結び、事業の継続を図ります
権利侵害の問題が発生した場合、訴訟による解決だけが選択肢ではありません。
特に権利侵害が認められた場合や、両者にとって有益な条件で合意が見込める場合は、ライセンス契約を結ぶことが望ましい解決策となることがあります。ライセンス契約によって、侵害行為を合法的な利用に変え、定期的なライセンス料の支払いを通じて、事業を円満に継続することが可能です。
知的財産・特許に関する法律トラブルは西村綜合法律事務所へご相談ください
私たちの法律事務所では、知的財産や特許に関する広範な法律支援を提供しています。
オンライン面談も可能なので場所・時間を問わずご相談いただけます。知的財産・特許にお困りの企業様におかれましては、西村綜合法律事務所にお気軽にご相談ください。

 メール・Web
メール・Web