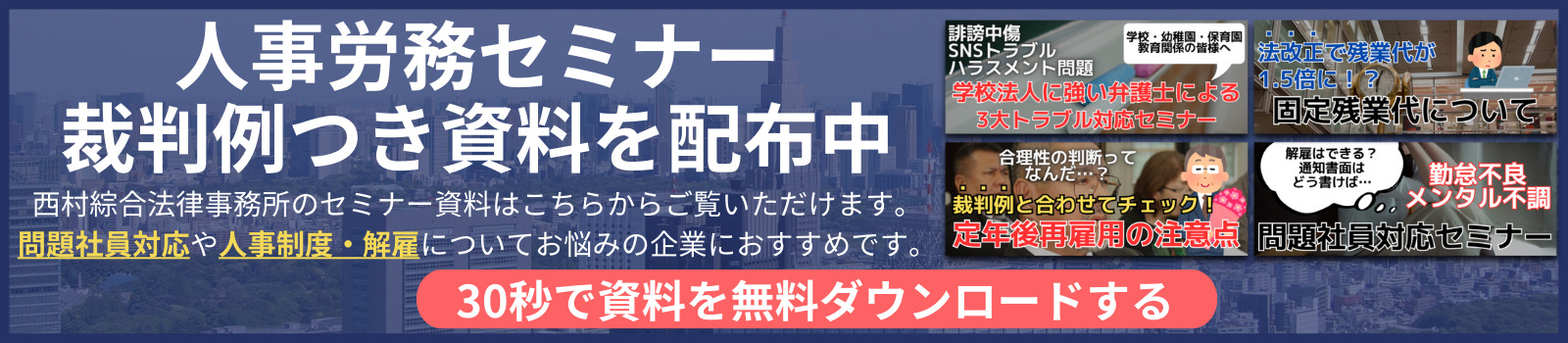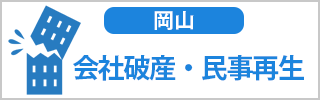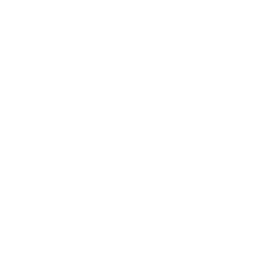労働審判

不当解雇や未払い残業代請求などの労働トラブルが生じた際、会社は労働審判の申し立てを受けることがあります。
もし会社が労働審判の申立てを受けた場合、会社としてはどのような対応をとることになるのでしょうか?
労働審判に潜むリスク
労働審判は、労働問題を迅速に解決するための手段ですが、その一方で以下のようなリスクもあります。
裁判所の判断がざっくりしたものになる
労働審判は通常の裁判に比べて迅速な解決を求められるため、裁判所の判断が粗くなりがちです。
全ての事情を詳細に検討する時間が限られているため、裁判所が全ての証拠を十分に評価し、詳細な法的分析を行うことが難しい場合があります。その結果、裁判所の判断が予測しづらく、企業にとって不利な結果になる可能性もあります。
解決金が高額になりやすい
労働審判は、裁判所が迅速に決定を下すため、訴訟費用が高額になりやすいです。特に、企業が労働者の主張を全面的に否定する場合、裁判所が高額な解決金を命じる可能性があります。また、企業が自身の立場を明確に示すためには、専門的な法的助言を得る必要があり、それによってさらにコストが増える可能性があります。
訴訟に移行し企業イメージが悪化する
労働審判の結果が双方にとって納得のいくものでない場合、訴訟に移行する可能性があります。訴訟になると、企業の名前が公になり、企業のイメージが悪化する恐れがあります。また、訴訟は時間と費用がかかり、企業の業績に影響を与える可能性もあります。これらの理由から、労働審判は慎重に取り組むべき課題であり、可能な限り適切な法的アドバイスを受けることが重要です。
労働審判対応を弁護士に依頼するメリット
上記のように労働審判は時間との勝負です。
会社が労働審判を申し立てられた場合には、約1か月という非常に短い期間で答弁書を提出し、労働審判期日に臨む必要があります。
既にご説明したとおり、労働審判は第一回期日が決定的に重要であるためここでの対応が労働審判の勝負を分けるものになってきます。
労働審判を申し立てられた際には早急に弁護士へご相談されることをお勧めします。
弁護士にご相談いただくことで、答弁書の記載の仕方や労働審判における質疑応答の回答の仕方などを徹底的にサポートさせていただき、短時間での迅速な準備に対応することが可能になります。
労働審判を会社に有利に進めるためにも、ぜひ労務問題に強い弁護士へのご相談をご検討くださいませ。
そもそも労働審判とは

労働審判制度とは、近年増加傾向にある労働トラブルに対応するため2006年に新設された制度です。
労働審判制度は、労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について、個々の従業員と会社との間に生じた民事に関する紛争について裁判所での解決を図ることを目的としています。
この制度が施行されるまでは、労使間の労働紛争を解決する手段として裁判所による解決を求めた場合には、民事通常訴訟手続や保全訴訟手続が利用されていました。
しかしながら、裁判所で訴訟手続きを利用した場合、訴訟手続きが終了するまでには相当長い時間がかかってしまうという問題もありました。
皆様の中にも訴訟制度のイメージとして、いったん訴訟手続きが開始されるとこれが終了するまでにはかなりの時間が掛かり、訴訟は長時間拘束されるものであるという印象をお持ちの方が多いかと思います。
実際、一般的な民事訴訟であっても、解決までに1年以上の時間を要することは珍しくありません。
そのため、労使間で労働トラブルが生じても解決までに多大な時間・費用・労力が必要であり、利用者にとっても非常に負担の大きいものでした。
労働審判制度は、そのような訴訟制度における利用者の負担を軽減し、労働トラブルが生じた際の利用しやすい紛争解決方法として制定されました。
それでは、労働審判制度と訴訟制度にはどのような違いがあるのでしょうか?
まず、労働審判手続は通常の訴訟手続きとは全く異なる制度です。
労働審判手続きは、裁判官である労働審判官1名と、日本労働組合総連合会や日本経済団体連合会といった労使団体から推薦された労働審判員2名で構成される労働審判委員会によって組織され、3回以内の期日において問題の解決が図られます。
労働審判ではまずは調停での話し合いによる解決が試みられますが、調停が不成立であれは審判がなされます。
そして、審判の結果に不服がある場合は通常訴訟手続きへ移行することとなります。
(1)労働審判の特徴について
次に、労働審判の特徴についてご説明いたします。
まず一つ目の特徴としては、労働審判は労働トラブルの簡易・迅速な解決を可能とするために制定された制度でありますので、通常の訴訟制度と比べ比較的短期間での労力やコストを抑えた問題の解決が見込まれるという点が挙げられます。。
実際、申し立てられた労働審判のほとんどにおいて金銭解決を中心とした和解的な解決がなされており、労働審判制度は、両当事者にとっても通常訴訟と比較したときに負担の少ないものである場合が多いです。
また二つ目の特徴として、労働審判委員会には労働関係に関する専門的な知識・経験を有する者が労働審判員として参加することが挙げられ、こちらも労働審判制度の大きな特徴の一つとなります。
労働審判員は経営側の有識者と労働者側の有識者からそれぞれ1名ずつ選任され、これらの雇用関係に関する現場の方が直接審理を行うため、実態に即した柔軟な判断がなされることになります。
さらに三つ目の特徴として、労働審判において通常訴訟ほど厳密な手続きは採用されていないという点が挙げられます。
労働審判制度は裁判所へ提出する書類が少なく、証人尋問などの正式な手続きが省略されていますので、簡易な手続きで事件の解決が図られることになります。
(2)労働審判の対象
労働審判手続は労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の従業員と会社との間に生じた民事に関する紛争を対象とします(労審1条)。
具体的な労働審判制度の対象としては、個々の従業員と会社との間の紛争である個別労働関係民事紛争のみが対象であり、使用者と労働組合との間の紛争(集団的労使紛争)や、公務員と国・地方公共団体との紛争(公務員労働関係紛争)は対象外となっています。
労働審判の対象となる個別労働関係民事紛争の例としましては、従業員から会社に対する未払い残業代請求や解雇無効請求などがこれに該当します。
(3)労働審判の現状
労働審判制度の開始当初の2006年(4月~12月)の地方裁判所における労働審判事件の新規受理件数は877件であったのに対し、2020年(1月~12月)は3907件でした。
労働審判事件の新規受理件数は、制度が施行された2006年から2009年までは急激に増加し2010年以降はほぼ横ばいとなっていますが、依然として高い水準を維持しています。近年では日本全国で年間3300件を超える労働審判が申し立てられています。
また2020年の終局既済事件数3754件においてこれらの終局事由別の割合をみると、調停が成立した事件は2559件(全体の68.2パーセント)で、労働審判がなされた事件は608件(全体の16.2パーセント)でありそのうち異議申し立てがなされなかった事件は261件(全体の約7パーセント)であることから、全体のおよそ8割の事件が労働審判手続きにおいて終了していることが分かります。
もっとも、労働審判制度の特徴の一つである問題解決までの迅速性については、ほぼ全ての労働審判が3回以内の期日において終了しており、平均審理期間は2020年においては3.6か月であることから、通常の訴訟手続と比較してもかなり短い時間での紛争の解決が図られていることが分かります。(ただし、2020年の平均審理期間は例年に比べて長期化しています。この背景として、新型コロナウイルスの感染拡大により、緊急事態宣言のため訴訟期日の延期等の措置がとられた結果が影響していると考えられます。ちなみに、2015年から2018年までは2.6か月から2.7か月、2019年は2.9か月でした。)
以上から、労働審判の8割以上が調停・審判の形で終了しておりそのほとんどが訴訟へと移行することなく終了しているため、労働審判における事件解決率は非常に高く制度としても有益なものと言えるでしょう。
労働審判の流れと留意点

労働審判制度の特徴の一つとして迅速性が挙げられますが、労働審判手続はこの迅速性を常に意識した流れで進んでいきます。
以下では、労働審判の流れとその留意点についてご説明いたします。
(1)従業員からの労働審判の申立て
労働審判制度の手続きは、通常は従業員が裁判所に「労働審判手続申立書」を提出することにより開始されます。
この労働審判手続申立書には、申立ての趣旨および理由のほか法定されている事項が記載されています。
もちろん会社側が従業員に対して労働審判を申し立てることも可能ですが、現状としてあまり多くはありません。
(2)答弁書の作成・提出
従業員側から裁判所に労働審判を申し立てると、裁判所から会社に労働審判手続申立書の写しと労働者側から提出された証拠の写しとともに、期日呼出状および答弁書催告状が郵送されてきます。
この期日呼出状には労働審判の第一回期日と答弁書の提出期限が記載されており、労働審判においてはこの第一回目の労働審判期日は非常に重要なものとなります。
労働審判制度では、第一回期日は基本的に裁判所の予定を優先し相手側へ予定を伺うことなく期日指定がされますので、もし第一回期日への出席が難しい場合は裁判所に対して速やかに連絡してください。
ただし、使用者側からの第一回期日の変更や延期は認められないケースも多く、非常に困難であると言えるでしょう。
仮に第一回期日に欠席してしまった場合は、通常の裁判制度にある擬制陳述(第一回口頭弁論期日に欠席した場合、あらかじめ答弁書を提出していた場合には答弁書に記載されている内容を法廷で陳述したこととみなす民事訴訟法上の扱い)は採用されていないため、非常に不利な立場となる可能性が高いです。
労働審判制度においては直接口頭審理が採用されており、労働審判委員会が当事者に直接質問を行い、これに対してその場で直接回答をします。
そして、この回答をもとに裁判官の心証が形成されます。
つまり労働審判では、第一回期日にすべての証拠・主張を提出しこれに基づいて裁判所の心証形成がなされるので、第一回期日でいかに有効な証拠を提示し、有益な主張を行えるかが労働審判の勝負を決めるポイントとなってきます。
(3)第一回労働審判期日
第一回期日は、原則として労働審判の申立てから40日以内に設定され基本的には日程の変更は困難です。
第一回期日は、通常2~4時間程度行われ、審判官および審判員2名のもとで争点整理、証拠書類の取り調べを行った後、両当事者に対してその場で審問が行われます。
以上の結果を踏まえ調停が試みられますが、話し合いがまとまらず調停が不成立となれば次回期日の調整が行われます。
ただし、第一回期日において調停が成立するケースは多く、企業としては調停の決定権限を有する役員等を第一回期日に出席させるか、あるいはすぐに連絡がとれるようにしておくことが望ましいと言えるでしょう。
また、事実関係の確認については原則として第一回期日でのみなされ第二回・第三回期日においては行われないため、第一回期日での主張は非常に重要となります。
仮に第一回期日で調停が成立しなかった場合には、第二回・第三回期日が設定され、再度の話し合いの機会が設けられます。
(4)第二回・三回労働審判期日
第一回期日で話し合いが成立しない場合には、第二回・第三回期日が設定されます。
この第二回・第三回期日においては、まずは両当事者間で話し合いによる解決(調停)が試みられます。
両当事者間で話し合いがまとまらず調停が不成立となった場合には、労働審判委員会が合議によって解決案を決定し、審判を下します。
下された審判に対して両当事者に異議がない場合には、審判は裁判上の和解と同一の効力を有するものとされます。
(5)異議申し立てがあった場合は訴訟へ移行
労働審判の内容に不服がある場合は、裁判所に対して異議を申し立てることができます。
異議申し立てができる期間には制約があり、審判書を受け取った日または期日において労働審判の告知を受けた日の翌日から起算して2週間以内とされていますので注意が必要です。
異議申し立てがなされると、労働審判の効力は失われ通常訴訟に自動的に移行されることになります。
労働審判に関するご相談は西村綜合法律事務所まで
当事務所では、最新の法的情報に基づいた具体的なアドバイスを提供し、企業の皆様が安心してビジネスに専念できるようにサポートします。さらに、審判が訴訟に移行するリスクを最小限に抑えるための戦略的なアプローチも提案します。
また、顧問契約による継続的な支援も可能です。法律情勢は日々変化し、それに対応するためには専門的な知識と情報が求められます。
西村綜合法律事務所ではオンライン形式も可能な初回無料相談を実施中です。まだ手探りの状況であっても、少しでもお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。
初回無料相談はこちら

 メール・Web
メール・Web