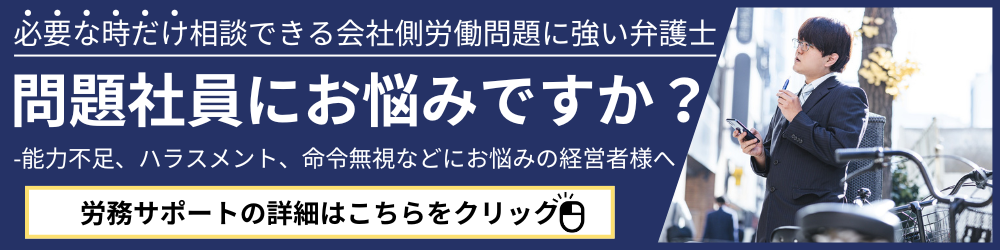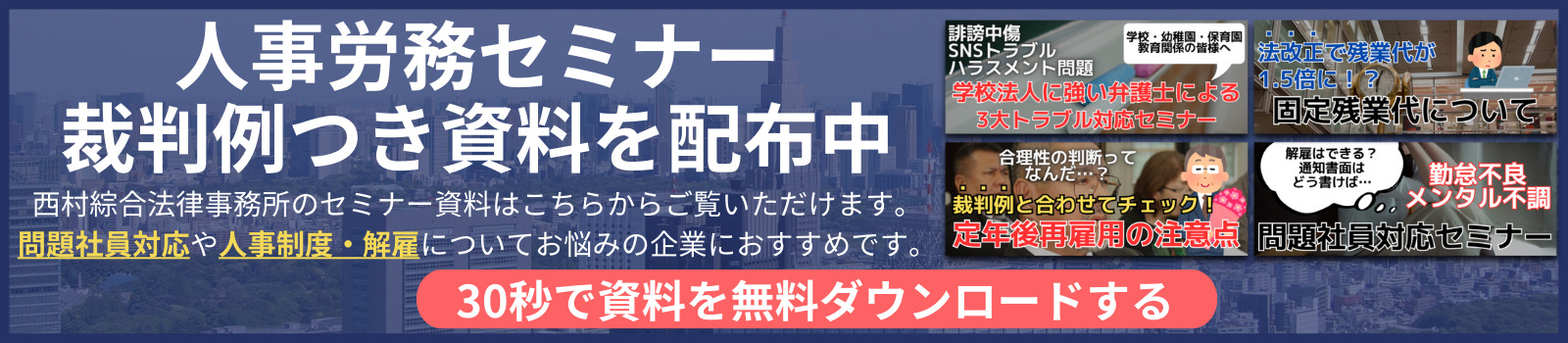問題社員対応について弁護士が解説!解雇を見据えた指導・手続きについて

「ちょっと社内で問題になっている社員がいるが、弁護士に頼むほどではないか…」
この記事をご覧になっている中には、そうお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、問題社員対応は、時間の経過とともにどんどん対応が困難になっていく性質があります。ぜひ、早めのご相談を検討ください!
問題社員対応を西村綜合法律事務所に相談するメリット
企業法務・人事労務の豊富な経験を活かした最適な対処
西村綜合法律事務所では東京、岡山、名古屋、大阪、神戸等において約90社(2025年8月現在)の顧問先企業様のサポートをしております。企業法務に関して豊富な経験を持っているため、問題社員対応の戦略立案や、具体的な手順のご提案等、業界特有の考え方やトラブル傾向を考慮したサポートが可能です。
法的に正しい手続きでの解雇や懲戒が可能
問題社員に対する解雇や懲戒は、非常に難易度の高い手続きです。間違った手順を踏むと、逆に企業が法的リスクを負う可能性もあります。そのため、弁護士のサポートを受けながら法的に正しい手続きで対処することが望ましいです。
問題社員側からの指摘によるトラブルを予防
問題社員に対する指導や指摘が適切なものであったとしても、向こうが腹を立てて「パワハラ被害を受けた」「退職強要だ」として反論される場合があります。このようなトラブルに発展してしまうと、企業側が不利になる可能性が出てきます。
弁護士が初期対応から入ることで、上記のような事態を想定した対応が可能です。
問題社員・モンスター社員を放置した場合のリスク
問題行動のエスカレート
問題社員を放置していて、問題が自然に収まることはありません。多くの場合、むしろ、当該社員は
「これくらいならやっても大丈夫なんだ」
と認識しますので、行為はどんどんエスカレートしてしまいます。
この場合、行為自体もさることながら、法律上、それまで(いわば)野放しにしていた問題社員を一発解雇することがなかなか認められない点も問題となります。つまり、周囲からすれば、問題社員を会社として解雇してくれることを望んでいるのに、それに応えられるような毅然とした対応がとれず、対応が後手後手となり、求心力が低下してしまうのです。
周囲の優秀な社員への悪影響
上記と関連しますが、一人の社員の行動は独立した問題ではなく、周囲の社員に影響を及ぼします。
・「アイツがアレで済んでるなら、僕もこれくらいはいっか…」というモラルハザード
・「あの人がいると雰囲気悪いし、やる気が出ないのよね…」というモチベーション低下
が起こって生産性が低下しますし、誘発された環境悪化は別の問題の原因にもなり得ます。
問題の芽は、時間とともに、どんどん拡大してしまうのです。
指導や指摘がパワハラ扱いされて逆にトラブルになる
さらに、問題社員を放置する弊害として重要なのが、「指導や指摘がパワハラ扱いされて逆にトラブルになる」というリスクです。
問題社員の行為を見過ごし続けた結果、その人物が自分の行動に対する意識が希薄になり、「ここまでやっても許される」という誤った認識を持つことになるかもしれません。その結果、当然のことながら問題行動がさらにエスカレートし、組織全体が影響を受けるリスクが高まるのです。
そして、ここで初めて指導や指摘を行ったとき、それがパワハラとして捉えられ、新たなトラブルの火種になる可能性があります。問題社員がこれまでの放任状態を「黙認」と捉え、突如とした指導をパワハラと受け取ってしまうのです。
これは、組織の管理職にとって非常に困難な状況です。本来であれば指導や指摘を通じて問題解決を図るべきですが、逆に新たな問題を生むことになってしまうのです。組織としては、最初から適切な対応を怠ってしまったことが、後々まで引きずる大きな問題となり、適切な対応をとるのが難しくなります。
問題社員・モンスター社員の種類と対応方法
ローパフォーマー社員とは、「会社が求めている労働能力を備えていない社員」です。
法的対応を見据えた場合、「会社が求めている労働能力」、というところがポイントです。つまり、いざ裁判となった場合、漠然と「パフォーマンスが低い」ことだけを主張しても無意味で、
・即戦力採用なのだとしたら、どういう「戦力」を備えたものとして雇ったのか
・そうでないなら、「労働者としての基礎的能力すらない」と言えるか
明確に主張しなければならないことに留意しましょう。
ローパフォーマー社員は教育指導などの解雇回避措置を
結論として、ローパフォーマー社員への対応は、必ず、教育指導から入り、かつ、その指導内容と結果を文字化しましょう。これには2つの理由(意味)があります。
・第一に、「ローパフォーマンス」の証拠というのは、自覚的に作らないと残らないからです(例えば無断欠勤ならタイムカードがあります。)。ですので、どういう指導に対してどういうパフォーマンスだったのか、どの点が不足していたのか、きちんと記録化しておきましょう。
・第二に、そもそも、「会社がその社員にどういう労働能力を求めているか」自体、自覚的に記録の機会を設けない限り、実は明確でないことがほとんどだからです。
協調性を欠く社員とは、他の社員と協力して仕事を進めるのが難しく、対人関係にトラブルを抱えてしまう社員です。職場では、大なり小なり人間関係のトラブルは避けられないものですが、特定の社員がトラブルを引き起こしがちな場合、厄介なのは、その社員は「自分が正しい、間違っているのは相手の方だ」と思っていることが多いことです。また、それゆえ、会社が事を収めようとしても逐一反発してくることもあり得ます。
したがって、この種の問題社員への対応に当たっては、後から文句の種にならないよう、形式面から注意を払って臨むことが大切です。
協調性を欠く社員への注意指導の注意点
協調性を欠く社員に注意する場合、まずは基本的・形式的な面を押さえておきましょう。
・ 場所は、プライバシーへの配慮として、他の社員のいない会議室を利用しましょう。
・ 時間帯は、退職時刻の1時間前後前から開始するのが望ましいです。これは、対応が業務時間内に収まり、かつ、問題社員がそのまま帰宅できるようにするためです。
・ 出席者は、現場レベルの上司も同席しつつ、対応は、相応の人事担当者が行うべきです。
・ 後日の証拠とするため、注意は、「注意書」の形で書面で交付しましょう。可能そうなら、誓約書の差入れを求めることも検討すると尚よいです。
会社の指示に従わない社員は、上記「協調性を欠く社員」のいわば発展形と捉えることができるでしょう。彼/彼女にとっては間違っているのは会社ですから、その会社が何らかのアクションを起こした場合、必然的に、反発が想定されます。
この場合、会社側としては、全てを記録に残すよう心掛けることが必要です。例えば、話合いのための面談への呼び出しも業務命令ですから、拒否された場合はきちんと記録に残し、できれば注意書を交付しましょう。また、社員の反発・反論についても、水掛け論を避けるため、文書として提出するよう求めましょう。これは、会社側がいたずらに疲弊しないようにするためにも有効です。
会社の指示に従わない社員の処分について
会社の指示に従わない社員に対する懲戒処分は、事案の軽重により様々と言わざるを得ません。会社としては、不服従社員に対しては解雇で臨みたいところですが、『一発』『懲戒』解雇は相当なリスクが伴います。
最大公約数的にまとめるとすれば、次のようになるでしょう。
・ 戒告・譴責は必ず挟みましょう。業務命令無視のたび、きちんと書面化して処分しましょう。
・ 一般的には、徐々に処分を重くしていく(戒告→減給→出勤停止…)ことが望ましいと言えます。ただ、例えば重大な人事命令(配転や出向等)に従わない場合等は、性質上、複数回の戒告/譴責に従わない場合、解雇も検討せざるを得ないでしょう。
・ 懲戒解雇は、厳格な手続が要求されますし、争われるリスクも高いです。どうしても解雇が必要である場合、退職勧奨からの合意退職や、普通解雇も検討してください。
非違行為とは、非行・違法な行為のことです。非違行為を行う社員とは、まるっと言えば、故意に規律を無視するタイプの社員のことです。非違行為としては様々な行為が幅広く想定されますが、本稿では差し当たり、外回り中に仕事をサボる等の業務関連行為を念頭に置いてみます。
いけないと知りつつ、敢えて自分の満足等のために行為に及んでいるわけですから、一番シンプルな問題類型であると言えます。問題の軽重に応じて、相応な処分を検討しましょう。
非違行為を行う社員は証拠集めが重要です
前述のとおり、非違行為はダメと分かって敢えてなされるものですから、良くも悪くも証拠が重要です。客観的な証拠がなければ、本人は確信犯である以上、白を切る可能性が高いといえるでしょう。客観的な証拠やデータを集めた上で、本人に確認しましょう。あとは、注意をした場合は注意書を交付するか誓約書を徴し、問題が繰り返されるようなら、重い処分を検討します。
ただし、非違行為が特定の社員に限らず高い頻度で起こる場合には、より抜本的な解決策が望まれることもあり得ます。そのあたりを見極めるためにも、まずは、客観的なデータを集めることが大切です。
非違行為に比べると、セクハラ・パワハラは少し厄介です。社員の主観としては「これくらい問題ない」と思ってやっていることが多いですし、特にパワハラについては、むしろ被害者のための教育だ、という意識で行われることも少なくないからです。
したがって、事後的対応だけではうまく解決できないことも多く、日頃からの予防が重要な類型となります。会社として「ハラスメントは許さない」というメッセージを明確に打ち出し、さらに、どのような行為がハラスメントに当たるか、具体例を示して周知徹底を図りましょう。研修・文書掲示・メール送信等、それぞれの会社に合った方法を検討してみてください。
セクハラ・パワハラの防止策(事業主が雇用管理上講ずべき10つの措置)
他方、ハラスメント問題は、事前の予防策が重要です。これについては、厚生労働省が指針(10の措置)を公表しています。直接的にはセクハラに関するものですが、ほぼ同様のことがパワハラにも当てはまります。
- 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
①職場におけるセクシュアルハラスメントの内容・セクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
②セクシュアルハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
- 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③相談窓口をあらかじめ定めること。
④相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また、広く相談に対応すること。
- 職場におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
⑤事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
⑥事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
⑦事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
⑧再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様)
- 以上と併せて講ずべき措置
⑨相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること。
⑩相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。
これを参考に、自社の備えを検討するのが望ましいでしょう。
無断欠勤(遅刻等も含みます。)を(頻繁に)行う社員の問題については、
「周囲のモチベーションを大きく下げる割に、本人が重大性を自覚していない」
点が特徴として挙げられます。
したがって、問題が拡大する前に、放置せず厳正な対処をすることが望まれる一方、本人ときちんと対話をすれば、事の重大性を本人が自覚し、改善することもあり得る類型です。ですので、本人と面談して注意をすることにも、予防線以上の積極的な意味合いがあります。感銘力を上げるために、書面も積極的に活用しましょう。
もちろん、そのような手順を踏むことは、改善に繋がった場合はもちろん、残念ながらそうでなかった場合も、然るべき手続を経たという意味を持ちます。
無断欠勤を行う社員に対応した就業規則の整備
無断欠勤や遅刻については、2つ、注意点があります。
・ 第一に、遅刻の場合、ありがちですが、問題社員は、「ちょっとくらい…」程度の短時間の遅刻を頻繁に繰り返す、ということがあります。しかしながら、仕事の多くはチームを組んでするわけですから、短時間だから支障が軽微、というわけでもありません。
こういう場合に、「戒告」程度のものであれ、きちんと懲戒処分を下せるよう、就業規則の懲戒事由に入れておきましょう。
・ 第二に、無断欠勤の場合、時々、「そもそも本人と連絡が取れない」という事態が起こります。これは話合い以前の問題ですから、このままでは会社は身動きが取れず、手続がフリーズしてしまいます。
したがって、無断欠勤が一定期間続いた場合の取扱いにつき、就業規則に定めておきましょう。
いずれにしても、就業規則の事前の定めが重要であるといえます。
問題社員に対して当事務所ができること
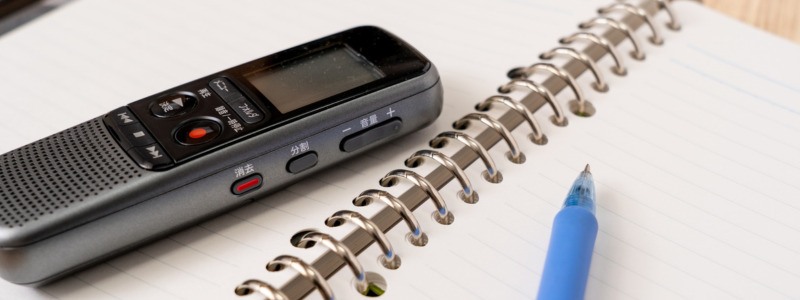
懲戒処分サポート
以上のように、いずれの類型の問題社員の場合にも、まずは、事実を確認し、軽い注意から始めることが穏当・妥当です。これを懲戒処分として行う場合、「戒告」という手続になります。
しかし、正式な処分となると、適正な手続の下、適切な内容・適切な表現で処分を下さなければなりません。その場合、事案の具体的事実はもちろん、場合に応じて、御社の就業規則や前例等を斟酌する必要があります。
当事務所は、豊富な経験をもとに、御社の意思決定を力強くサポートします。
配置転換サポート
他方、戒告等の注意で済む話ではないが、かといって解雇もハードルが高い、という事案はかなり数があります。この場合、出勤停止等の中間的な重さの懲戒処分をする他に、御社の規模や事情の委細によっては、配置転換を行い人間関係をいわばリセットする方が、解決策として適切な場合もあります。
ただし、懲戒処分ではなくとも、配置転換も、企業側が一方的に自由に行えるというものではありません。
当事務所では、そのような方法も念頭に置きつつ、柔軟な解決をご提案します。
退職勧奨サポート
とはいえ、問題社員対応としては、多くの企業様にとって、解雇が理想であることが多いです。もっとも、解雇=一方的労働契約終了となると、後から法的に無効とされ、多額のバックペイを支払わざるを得なくなるリスクを無視できません。
そこで、社員の経済的・精神的な不安を軽減しつつ、話合いで退職の合意に至ることが、有力・有効な選択肢になります。その場合に、社員に対して合意による退職を勧めることを退職勧奨と言いますが、これを実施するに際しては、後から「退職を無理強いされた」と主張されないよう、様々な注意が必要です。
当事務所では、問題社員の類型・パターンに応じ、退職勧奨の具体的なアドバイスをさせていただくことが可能です。
問題社員・モンスター社員にお困りの方へ
問題社員の対応が遅れるほど、社員からの印象は悪化し、働きやすい環境は損なわれます。その損失は金銭的なものだけではありません。
我々はそのような状況を避けるために、迅速かつ適切なサポートをいたします。
問題社員にお困りの企業様におかれましては、西村綜合法律事務所にお気軽にご相談ください。オンライン面談も可能なので、場所を問わずご相談いただけます。
初回相談はこちら
「問題社員対応について弁護士が解説!解雇を見据えた指導・手続きについて」の関連記事はこちら
- 諭旨解雇をするには?懲戒解雇との違いや法的な注意点を弁護士が解説
- 解雇や退職勧奨に踏み切る際の注意点!!問題社員(モンスター社員)への対応に強い弁護士が解説
- 異動や配置転換を拒否する社員への会社としての対応を解説
- 協調性のない社員やお局さん型の従業員を解雇するには?問題社員対応に強い弁護士が解説
- 解雇を見据えた問題社員との付き合い方・指導方法を徹底解説
- 能力の低い社員を配置転換したい!有効なケース、無効になるケースを徹底解説
- ローパフォーマー社員って?能力不足の部下・職員に会社として対処するには
- これって問題社員?辞めさせることはできる?パターン別の対処法を徹底解説
- 懲戒処分の要件・種類を弁護士が解説!法的に有効な処分を科すポイントって?
- 問題社員を辞めさせることって可能?モンスター人材への対処方法を企業側弁護士が解説
- モンスター社員を辞めさせる方法って?退職勧奨の流れと注意点を労働弁護士が徹底解説
- 自主退職させるための退職勧奨のポイント!解雇との違い、違法になるやり方を弁護士が解説

 メール・Web
メール・Web