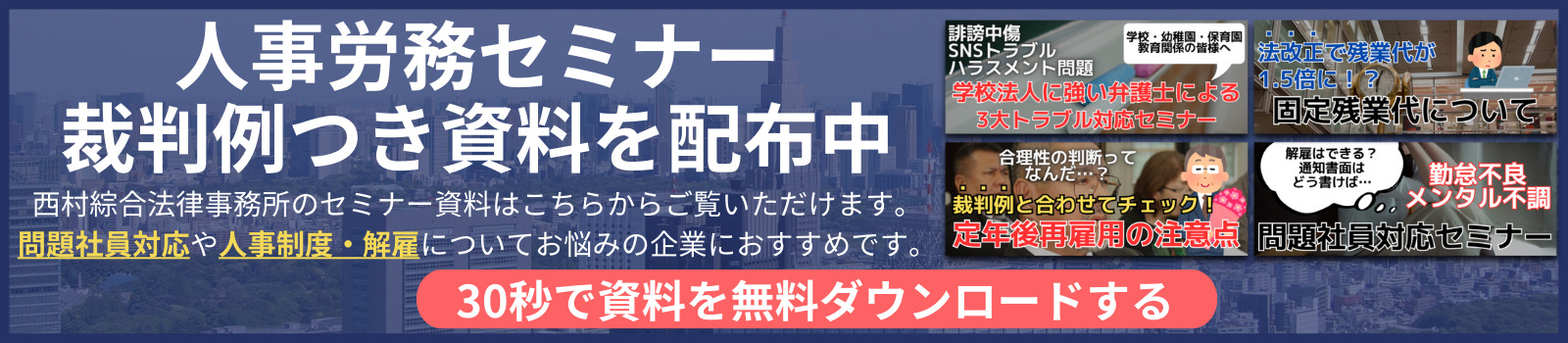景品表示法の相談に強い弁護士なら – 違反するとどうなる?

商売をする上で、自社の商品やサービスを売り込むためには様々な方法がありますが、ルールを破ると法律により罰せられることがあります。その一つが、景品表示法(景表法)という法律です。
景品表示法(景表法)における規制とは
景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止し、一般消費者の利益を保護することを目的とする法律です。
上記のように、景品表示法は、一般消費者の利益を目的とする法律ですが、企業が景品表示法を遵守しない場合、景品表示法違反行為があったことを公表されたり、再発防止策を講じなければならなくなったりと、イメージダウンや、余計な出費につながってしまうため、企業側も景品表示法を十分に理解しておく必要があります。
景品類の制限・禁止について
景品表示法では、消費者に対して虚偽の表示を行ったり、不当な景品や割引を提供することを禁じています。特に、高額な商品を無料や割引で提供するといった、消費者を誤認させるような表示は厳しく制限されています。
不当表示の禁止について
不当表示と呼ばれている表示には、(1)優良誤認表示、(2)有利誤認表示、(3)その他誤認されるおそれのある表示の3種があります。
なお、景品表示法にいう「表示」は、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、内閣総理大臣が指定するものをいい、チラシやパッケージ、商品のラベルといったものだけでなく、ポスターや看板、セールストーク(訪問・電話は問いません)、インターネット上の広告や広告メールなども含まれます。
優良誤認表示
商品・サービスの品質・規格等の内容について、実際のものや事実に相違して競争事業者のものより著しく優良であると一般消費者に誤認される表示が該当します。例えば、「カシミア100%」と表示しているにもかかわらず、実際にはカシミア混用率が80%程度であった、「栄養成分が他社の2倍」と表示しているにもかかわらず、実際には同量であったなどの表示は不当表示となります。「合格実績No.1」や「医学的に証明済み」といった根拠のない表現を用いることは、消費者を誤認させるため禁止されています。
有利誤認表示
商品・サービスの価格等の取引条件について、実際のものや事実に相違して競争事業者のものより著しく有利であると一般表示者に誤認させる表示がこれに当たります。例えば、3人前の分量しかないのに5人前と表示している、「特別価格5,000円!」と表示しているにもかかわらず、実際には通常価格10,000円で販売している場合、「他社商品の1.5倍の量」と表示しているにもかかわらず、実際には他社商品と同程度の量である場合などがあります。
その他誤認されるおそれのある表示
商品・サービスの取引に関する事項について、一般消費者に誤認されるおそれがあると認められ、内閣総理大臣が指定する表示がこれに該当します。例えば、商品の原産国に関する不当な表示やおとり広告(例えば、「超特価商品10点限り!」と表示しているにもかかわらず、実際には当該商品を全く用意していない場合又は表示した量より少ない量しか用意していない場合など)に関する表示などが挙げられます。
企業が事前に講じなければならない管理措置の指針
国によって定められた措置の指針があります
景品表示法の第22条第1項では、企業が法律を遵守するための適切な措置を講じる義務が定められています。また、第2項では、内閣総理大臣が企業が実施すべき管理措置についての基準を示すものとされています。この基準に基づき、「事業者が講ずべき景品類の提供及び管理上の措置についての指針」(以下「管理措置指針」)が策定されています。
企業が講じるべき7つの指針
① 景品表示法の考え方の周知・啓発
従業員や関係者に対し、景品表示法の基本的なルールや遵守の重要性を定期的に教育し、周知徹底する。
② 法令遵守の方針等の明確化
社内ルールとして、景品表示法を遵守することを明文化し、従業員が遵守すべき具体的な方針を策定する。
③ 表示等に関する情報の確認
広告や商品表示を行う際、事実に基づいているか、消費者に誤解を与えないかを十分に確認する。
④ 表示等に関する情報の共有
③で確認した情報を、当該表示等に関係する企業内の関連部門が連携し、適切な情報共有を行う。
⑤ 表示等を管理するための担当者等(表示等管理担当者)を定めること
景品表示法に関する社内の担当者や担当部門をあらかじめ定める。
⑥ 表示等の根拠となる情報を事後的に確認するために必要な措置を採ること
③で確認した情報を、表示等の対象となる商品又はサービスが一般消費者に供給され得ると合理的に考えられる期間、事後的に確認するため、表示の正確性を担保するために、広告掲載後もデータやエビデンスを保管等必要な措置をとる。
⑦ 不当な表示等が明らかになった場合における迅速かつ適切な対応
問題が発生した場合は、迅速かつ正確な確認、迅速かつ適正な是正措置を取り、再発防止策を講じる。
違反するとどうなる?罰則について解説
景品表示法違反行為の疑いがある場合、消費者庁が調査を開始し、資料の収集、事業者への事情聴取等がなされます。
そして、消費者庁が、違反行為があると認定した場合には、措置命令が出され、また、優良誤認表示・有利誤認表示があった場合、課徴金納付命令が出されます。また、違反事実及び処分内容は消費者庁ウェブサイトの景品表示法関連報道発表資料のページに記載されます。
措置命令
消費者庁が景品表示法違反を認定した場合、事業者に対して「措置命令」が発せられます。措置命令の例としては下記のようなものがあります。
違反事実の公表:
企業は消費者に対し、自社が違反を行ったことを明確に知らせなければなりません。
再発防止策の実施:
企業は、今後同様の違反を繰り返さないよう、社内体制の見直しや従業員教育の強化を求められます。
対象商品の販売中止や修正:
虚偽の表示が行われた商品・広告について、販売の停止や修正が指示されることもあります。
課徴金納付命令
企業が「優良誤認表示」または「有利誤認表示」の違反を行っていた場合、消費者庁から「課徴金納付命令」が出されることがあります。課徴金の額は、「違反行為が行われた期間の売上の3%」と定められています。
この金額は違反行為の規模によっては数千万円、場合によっては数億円にのぼることもあるため、会社経営に与えるダメージは計り知れません。
消費者庁HPへの掲載
景品表示法違反が認定されると、消費者庁の公式ウェブサイトに企業名や違反内容が公表されます。これにより、企業の信頼は大きく損なわれ、消費者や取引先からの信用を回復するのが困難になります。
このように、景品表示法違反に基づく処分がされた場合、企業にとって大きな不利益となりますから、広告に関しては、景品表示法の規制を十分に理解しておく必要があります。
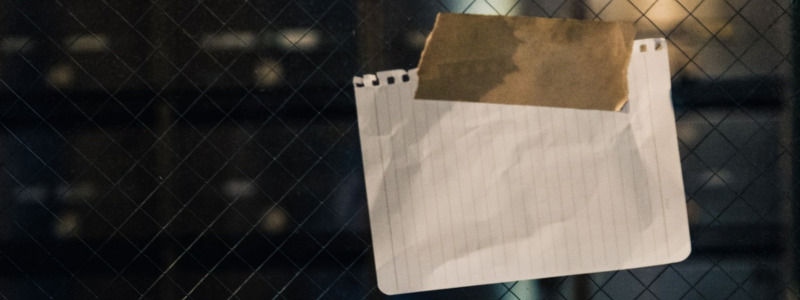
ステマ表示(ステルスマーケティング)への規制
そもそもステルスマーケティングとは
ステルスマーケティング(ステマ)とは、事業者が自社の商品・サービスを宣伝する際に、広告であることを隠し、あたかも消費者の自然な口コミやレビューであるかのように装う手法を指します。たとえば、SNSやブログで著名人が「この商品を使ってすごく良かった!」と投稿しながら、実際には企業から金銭を受け取って宣伝していた場合、これがステマに該当します。
特に近年、インフルエンサーを活用したマーケティングが普及する中で、消費者が「本当に信頼できる情報なのか?」と疑念を抱くケースが増えています。そのため、公正な取引と消費者の権利を守る観点から、ステルスマーケティングに対する規制が強化されました。
具体的な規制内容
2023年の法改正により、ステルスマーケティングが景品表示法上の「不当表示」に明確に位置付けられました。これにより、広告であることを明示せずに消費者を誤認させる行為は規制の対象となります。
(1) 広告であることを明示しない投稿の禁止
事業者がインフルエンサーや一般消費者に金銭や商品を提供し、対価として投稿を依頼する場合は、その投稿が「広告」であることを明確に表示する必要があります。たとえば、「#PR」「#広告」「提供:○○会社」といった明確な表記をしなかった場合、規制違反となる可能性があります。
(2) 事業者が間接的に関与した投稿も規制対象に
事業者が直接投稿を依頼していなくても、間接的に投稿内容をコントロールした場合(例:企業がインフルエンサーに対して特定の文言や表現を求める、事前に承認を求める等)、これもステマ規制の対象となります。
(3) 消費者に誤認を与える口コミや評価の操作の禁止
企業が自ら、あるいは外部業者を通じて、商品やサービスの評価を意図的に操作する行為も禁止されます。たとえば、実際には利用していない人に高評価のレビューを投稿させる、ネガティブな口コミを削除する、架空のアカウントを作って自社の製品を絶賛する、などの行為が該当します。
(4) 違反した場合
ステマ規制に違反した場合、景品表示法の「不当表示」として措置命令の対象となり、企業名や違反内容が公表される可能性があります。さらに、悪質な場合は課徴金の支払い命令が下されることもあり、企業にとって大きな経済的・信用的ダメージを被ることになります。
企業が講じるべき対応策
ステルスマーケティング規制を遵守するためには、以下のような対応が求められます。
- インフルエンサーや広告代理店と契約を結ぶ際に、広告であることを明記するルールを設定する
- 口コミやレビューの管理を適切に行い、不正操作を行わないようにする
- 社内研修を実施し、マーケティング担当者にステマ規制の重要性を周知する
消費者の信頼を損なうことなく、適法なマーケティング活動を行うためにも、企業はステルスマーケティングのリスクを正しく理解し、適切な対応を取ることが重要です。
景品表示法(景表法)について弁護士ができること
ビジネスを展開するにあたり、景品表示法に関する規定を理解し、遵守することは不可欠です。しかし、法律の解釈は専門的な知識を必要とします。そこで弁護士の力が必要となるのです。私たち弁護士が貴社のビジネスに対して果たせる役割について、具体的に説明させていただきます。
(1)広告審査・景表法の制限への対応
広告の制作はビジネスにおける重要な要素の一つですが、その表示内容が法律に抵触しないか確認することは非常に重要です。私たち弁護士は、貴社の広告や表示内容が景品表示法に適合しているか確認し、必要に応じて具体的なアドバイスを提供します。
広告審査(不当表示該当性)についてのアドバイス
広告内容が不当な表示に該当する可能性がある場合、具体的にどの部分が問題となるのか、どのような対策が必要となるのかを詳細に調査します。さらに、適切な修正案を提供し、貴社が法律違反を未然に防ぐためのサポートを行います。
広告審査(不実証広告規制対応)についてのアドバイス
広告内容が実際の事実に基づいていない場合や、その表示が消費者を誤解に導く可能性がある場合も同様です。具体的な検証を行い、法令違反を回避するためのアドバイスを行います。具体的な事例や根拠をもとに、貴社の広告が適法であることを確保します。
景品類の制限に関する調査・アドバイス
貴社が提供しようとしている景品や割引が景品表示法に反しないか、また、法的な制限に適合しているかどうかを専門的に調査します。必要であれば、提供内容の改善案を提案し、法律問題を未然に防ぐお手伝いをします。
(2)顧問弁護士としての継続的なサポート
不確定要素が多い法律問題。一度の対応だけでなく、継続的なサポートが必要となることは少なくありません。私たちは、顧問弁護士として、貴社が安心してビジネスを行えるよう、法律に関する様々な問題についての継続的なサポートを提供します。
法律問題は一見すると難しそうなイメージがありますが、適切な対応を行えば事業の安定につながります。もしも法律に関する疑問や悩みがありましたら、私たちにご相談ください。
景品表示法(景表法)に関するご相談は西村綜合法律事務所まで
景品表示法は罰則だけでなく、正しい商品情報伝達、公正な取引のための法律です。遵守は法的問題を避けるだけでなく、信頼性の高いビジネス展開、長期的な成功へのステップとなります。
また、顧問契約による継続的な支援も可能です。法律情勢は日々変化し、それに対応するためには専門的な知識と情報が求められます。
西村綜合法律事務所ではオンライン形式も可能な初回無料相談を実施中です。まだ手探りの状況であっても、少しでもお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

 メール・Web
メール・Web