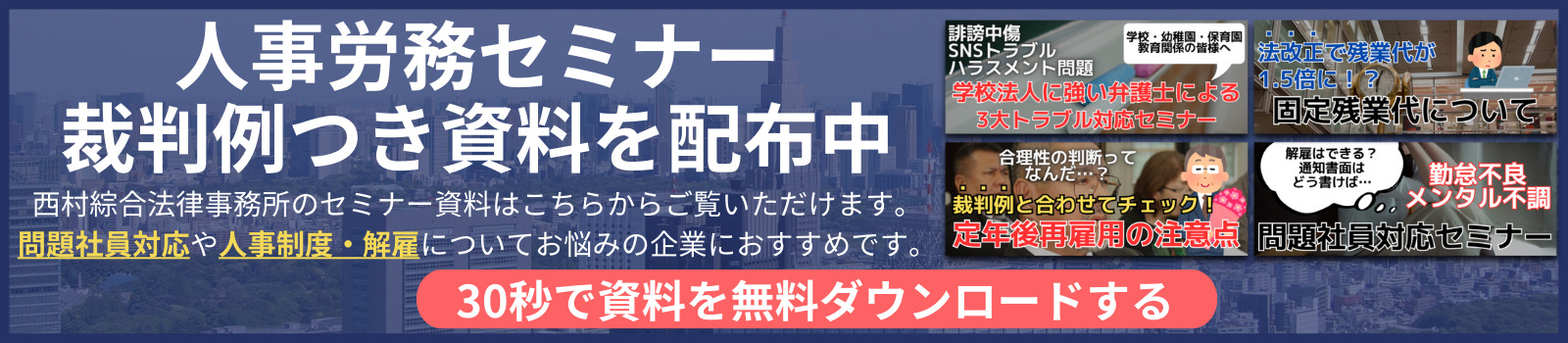同一労働同一賃金について!勤続年数との関わりも弁護士が解説

同一労働同一賃金の目的と法的リスク
同一労働同一賃金とは
同一労働同一賃金とは、正社員と非正規社員が同じ仕事をしているにもかかわらず、その待遇に大きな違いがあるという状況を是正しようとする考え方のことを言います。これは、労働者の賃金や待遇が、その労働内容や能力に応じて適切に評価・反映されるべきであるという原則に基づいています。
罰則はないが損害賠償請求リスクがある
同一労働同一賃金の原則に違反した企業に対して法律上の罰則は設けられていませんが、違反が発覚した場合、不当な待遇を受けていた労働者からの損害賠償請求のリスクが高まるでしょう。
また、社会的な評価も低下し、採用活動に悪影響を及ぼす可能性もあります。このようなリスクを回避するためにも、企業は同一労働同一賃金の考え方を理解し、実践することが求められています。
企業側に求められること
企業側に求められる対応は決まっている訳ではありませんが、以下のような例が挙げられます。
賃金規定などの見直し
まず、企業は自社の賃金規定や労働規則を見直し、必要な場合には改定する必要があります。正社員と非正規社員の間で、同じ仕事をしていても賃金に差がある場合、それが「合理的な理由」に基づくものでなければ、賃金規定の見直しが求められるでしょう。
正社員以外にも福利厚生施設の利用機会を与える
また、福利厚生施設の利用についても同様です。例えば、企業が保有する保養施設やクラブ活動などへの参加機会は、全ての労働者に平等に提供されるべきだとされています。
待遇差の合理性について説明できるようにする
同一労働同一賃金の原則に違反していないかどうかを判断する上で重要となるのが、「待遇の差に合理的な理由があるか」です。この点については、具体的な事例をもとに判断が分かれることもあるため、ガイドラインおよび判例を照らし合わせることが必要となります。
ここは情報収集や判断が難しくなるため、弁護士への相談が望ましいでしょう。
同一労働同一賃金のガイドライン・判例に関して
ガイドラインについて
そもそも、ガイドラインは、正規社員と非正規社員との間において、基本給の決定基準・ルールが同一であること、職務内容、配置の変更の範囲の同一が前提としたものですが、実際は同一はまれといえますのでガイドラインをそのまま適用する場面は少ないのではないかと思います。すなわち、ガイドラインを分析しますと、ガイドラインは、
①能力又は経験
②業績または成果
③勤続年数
について、賃金決定の要因が同一であることを想定した記述となっています(職能給vs職能給、成果給vs成果給)。しかしながら、実務上は、正社員と非正規とで、賃金決定の要因が同一であるケースは極めて稀ではないかと思うのです。実務上は、賃金決定の要因について多様な趣旨を含みうるものであり、ガイドラインの示すような単純な基準に基づくケースは稀であるといえます。特に、基本給は複合的な基準によって規定している会社がほとんどであると思います。①能力又は経験②業績または成果③勤続年数という複数の基準によって規定している会社が多数であると思います。そうなりますと、正規と非正規との間において、基本給の定め方を同一にしているケースは少ないでしょう。
他方、正規と非正規の間において基本給の定め方を同一にしている場合は要注意といえます。また、実務上は正社員と非正規とで職務の内容及び配置の変更の範囲に大きな違いが認められるケースが多いことからも、ガイドラインがそのまま適用される場面は少ないといえるでしょう。加えて、正規と非正規の間において職務の内容及び配置の変更の範囲を同一にしている場合は要注意といえます。
なお、ガイドライン(注)1には気を付ける必要があります。
具体的には、「通常の労働者と短時間・有期雇用労働者との間に賃金の決定基準・ルールの相違がある場合の取扱いとしては、通常の労働者と短時間・有期雇用労働者との間に基本給、賞与、各種手当等の賃金に相違がある場合において、その要因として通常の労働者と短 時間・有期雇用労働者の賃金の決定基準・ルールの相違があるときは、「通 常の労働者と短時間・有期雇用労働者との間で将来の役割期待が異なるため、賃金の決定基準・ルールが異なる」等の主観的又は抽象的な説明では 足りず、賃金の決定基準・ルールの相違は、通常の労働者と短時間・有期 雇用労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の 事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものの客観的及び具体的な実態に照らして、不合理と認められるものであってはならない」というものです。同一性がないとしても、会社としてはその区別については具体的な説明ができるようにしておく必要があります。
現在の裁判例の分析
実際の裁判例においても、上記①②③の基準のうち、いずれの基準にも分類できないケースが争われています。
裁判例においては、(1)基本給全体の金額比較を行った上で、(2)その相違が不合理か否かの判断が行われており、その際に職務内容の相違や異動範囲の相違を主たる理由に掲げて不合理性を判断する傾向にあります。まずは(1)同一の職務についている正社員と非正規の基本給全体の金額比較を行い、(2)相違がある場合には、職務内容や異動範囲などの点を理由に不合理ではないと説明が可能かどうかの検証をすることがポイントとなっています。検証の結果、そのような説明が困難な場合は、基本給制度の見直しを行うなどの対応を検討することとなるでしょう。
なお、職務範囲や異動範囲等の違いについては、社内規程等の整備によって明確化しておくことが有用であると思います。
正社員=月給制、非正規=時給制を採用しているケースについて
この点、採用している賃金制度が異なるケースでは、非正規に異なる賃金制度を採用することに合理的な理由があるか、また、待遇の相違が賃金制度の相違から必然的に生じるものかを確認することが実務上のポイントとなります。
たとえば、大阪医科薬科大学事件の原審では、非正規に時給制を採用することについて、勤務体制が正社員と異なることや個別の賃金計算がより容易であることなどを理由に不合理であるとはいえない旨判示しています。
また、非正規において短時間の労働をしている人間の割合が、会社においてどの程度なのかという視点も重要となるでしょう。割合が多ければ非正規全体を時給制とすることに合理性が認められやすくなると思います。
年功型賃金制度について
いわゆる年功型賃金制度においては、勤続給(③)や能力給(①)が賃金決定の基準となります。そうすると、正社員に勤続給を取り入れている場合、正社員と同一職務内容等で同一の勤続年数の非正規には同一の支給をしなければ不合理な待遇差となる可能性がありますが、実際にそのような支給をしているケースは稀といえます。今後も正社員に勤続給を維持するならば、非正規についても均等・均衡のとれた勤続給を支給する必要がありますが、実務上は必要な賃金原資の確保等の点から難しいケースが多いと考えられます。そのような会社においては、年功型賃金制度自体の見直し等を検討するケースが多いと考えられます。
成果型賃金制度への移行
同一労働同一賃金施行後は、基本給を年功型賃金から成果主義型に移行した方が、正規と非正規の間の待遇差について合理的な説明がしやすくなると言われています。
それでは、移行手続については、どのように対応すべきなのでしょうか。この点、年功型賃金から成果主義型賃金への不利益変更が争われた東京商工会議所事件(東京地裁平成29年5月8日判決)が参考になります。
東京商工会議所では、職員に対し、基本給として、年齢給、職能給、資格手当が支給していましたが、成果主義型賃金に変更後は、従前の年齢給、職能給、資格手当は廃止し、役割給に一本化しました。そして、本件変更により、従前受給していた給与よりも低い給与となる者に対しては、影響緩和のために平成27年から平成29年にかけて3年間調整給が支給されていました(ただし、調整給は毎年3分の1ずつ減額される。)。調整給が1年ごとに3分の1ずつ減額されることになっていたこと及び原告が平成27年度の人事評価において昇級しなかったことに伴い、原告の給与は、平成28年4月1日から、役割給37万9300円、調整給3万2000円の合計41万1300円となりました。今後、調整給が3分の1ずつ減額されるので昇給しない限り、以前の賃金総額からは減額されることになったのです。このような状況に対して、原告は訴訟を提起しました。
裁判所は、以下の理由により原告の訴えを認めませんでした。
① 会社の総人件費の総額の変更なし
「本件変更が賃金配分の見直し目的の賃金体系の変更であるとして、賃金体系をどのようなものにするかは、人材育成等の雇用施策と深く関わるもので、使用者側の経営判断に委ねられている部分が大きいといえるところ、被告が上記アのような検討を行い、年功序列型から成果主義型の賃金体系に変更することとした経営判断自体に合理性がないとはいえない。」
② 人事評価制度の内容について
「被考課者が考課者と面談して策定した成果目標等を目安としつつ、その達成度を考課者が被考課者の自己評価も踏まえて評価し、その結果、現等級以上の役割を果たしているかが数値化して検討できるようになっており、さらにその結果が被考課者に開示され、異議申立てもできるというものである。かかる仕組みは、できる限り客観性と透明性を保って人事評価をしようとするものといえ、本件変更の合理性を判断するに当たり、人事評価制度として必要とされる程度の合理性を備えたものになっているといえる。」。
③経過措置・緩和措置を設けた
「被告が経済的に逼迫していたとは認められず、柔軟な経過措置を設けても経営上の支障はなかったとうかがわれること等に照らすと、経過措置が十分に手厚いものであったかは疑問が残るところではある。もっとも、本件の調整給にも一応の緩和措置としての意義はあり、その支給期間中に2回の昇級・昇給の機会があることにも照らすと、合理性を基礎づける要素として考慮するに値する。」
④ 労使交渉
労働組合とも何度も意見交換をして、労働組合の意見を制度に反映。労働組合と合意には至っていないのですが、特段異議は示されなかった。
同一労働同一賃金について弁護士に相談するメリット
最新の判例に基づいた助言が可能
同一労働同一賃金の法的判断は、新しいガイドラインや判例に大きく影響されます。経験豊富な弁護士に相談することで、最新の判例に基づいた適切な助言を得ることが可能です。
それにより、法的リスクを最小限に抑えつつ、適切な対応を行うことができます。
賃金規定や就業規則の最適化が可能
弁護士に相談することで、賃金規定や就業規則を見直し、最適化することも可能です。
特に、正社員と非正規社員の待遇差を適切に説明するための規定作りは、弁護士の専門的な知識が有効です。
同一労働同一賃金に関するご相談は西村綜合法律事務所まで
同一労働同一賃金の問題は、一見すると複雑で理解しにくいかもしれません。しかし、それは弁護士等の専門家の助けを借りれば、解決の糸口を見つけられる問題でもあります。
西村綜合法律事務所ではオンライン形式も可能な初回無料相談を実施中です。まだ手探りの状況であっても、少しでもお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

 メール・Web
メール・Web