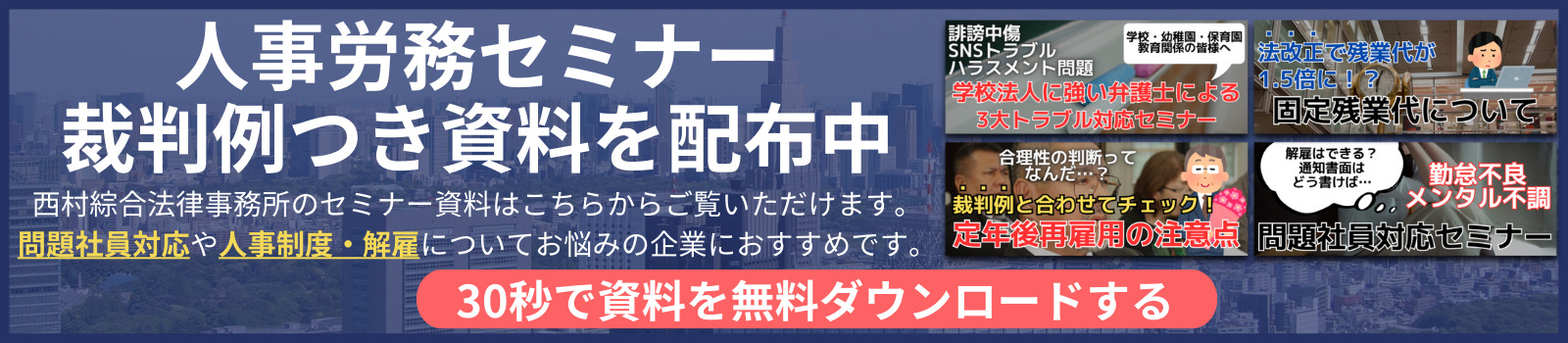不利益変更は顧問弁護士と進めましょう!給料減額や内定取消しの注意点
景気が冷え込む中、急速な業績悪化によってやむを得ずに事業規模を縮小する場合、併せて人事上の措置も視野に入れた対応を検討する必要があります。
今回は、給料減額(雇用は継続する)、内定取消し(雇用の入口段階での対応)についてご説明します。
不利益変更って?無効になるケース
不利益変更とは
不利益変更とは、労働者の賃金、労働時間、勤務地などの労働条件を劣悪なものに変更することを指します。
例えば、給料減額や労働時間の増加、転勤などが該当します。
同意が無効になるケースがあります
しかし、上記の変更は労働者の同意がなければならず、その同意も無理強いされたものや、事実を隠蔽した上でのものであれば無効になる可能性があります。
罰則はありませんが損害賠償請求のリスクがあります
また、不利益変更には罰則が設けられていないため、一見リスクが少ないように思えるかもしれません。
しかし、労働者からの損害賠償請求のリスクをはらんでいます。不利益変更が無効と判断されれば、元の労働条件を回復するための損害賠償が求められることになります。
先に余剰人員の整理を行うべき局面かもしれません
不利益変更を考えている企業が最初に行うべきことは、余剰人員の整理であるかもしれません。
経営状態を短期的に改善するために人件費を抑えるとして、その方法が不利益変更では全従業員からの心象が悪化し、異なる問題が引き起こされる可能性があるからです。
そのため、まずは早期退職募集や出向など、労働者の自発的な行動を促す方法を考えるべきです。
顧問弁護士との契約を検討してください
労働法規は頻繁に変更され、その都度理解して適切に対応するのは困難です。
顧問弁護士がついていれば、常に最新の法律情報を把握してアドバイスを提供してくれるので、事前に問題を予防し、適切に対応することができます。
また、万が一紛争に発展してしまった場合でも迅速かつ適切な対応が期待できます。
不利益変更を行う際に弁護士に相談すべき理由
不利益変更への助言・方針のご提案ができる
不利益変更はその手続きと内容により、労働者からの不服申し立てや紛争を招く可能性があります。
弁護士に相談することで、そのリスクを適切に評価し、不利益変更の方法や内容を検討する際の助言や方針を得ることができます。また、同意を得るための対話の方法や表現もアドバイスしてもらえます。
就業規則改定、同意書の作成をしてもらえる
不利益変更を行う際には、就業規則の改定や、労働者からの同意書の取得が必要になることがあります。
これらの文書は、法的に有効であり、かつ紛争を回避するためには、適切な表現と内容が求められます。弁護士に依頼すれば、これらの文書を法的に適切な形で作成してもらうことが可能です。
不利益変更の進め方
給料減額
従業員の給料を減額するには、大きく分けて以下の2つの方法があります。
① 従業員の同意を得る。
② 就業規則の不利益変更による。
なお、労働組合がある場合は、労働組合と労働協約を締結する方法もあります(労働組合法第16条)。
給料減額の進め方
次のⅰからⅲの順に進めることを検討します。
ⅰ 従業員の合意を得られるよう、まずは協議・交渉する。
ⅱ 合意が得られれば、その内容を就業規則に反映させる。
ⅲ 合意が得られなかった場合、法的リスクを改めて検討した上で、就業規則変更による給料減額に踏み切るかどうかを判断する。
就業規則の最低基準効について
引き下げの対象となる給料の支給基準や金額が就業規則で定められている場合においては、たとえ給料減額について従業員との個別合意が成立した場合であっても、就業規則で定める基準を下回る部分については無効となり、従業員は就業規則の支給基準や金額を請求できます(就業規則の最低基準効、労働契約法第12条)。
そのため、給料減額を検討する場合は、給料減額の対象となる賃金の支給基準や金額が就業規則を根拠とするものかどうかを注意が必要です。
もし、就業規則に基づくものである場合は、従業員の同意を得た場合であっても、別途就業規則を変更する必要があります。
個別合意を得るには
従業員からの個別合意を得る際には、以下の点を踏まえた対応が望ましいといえます。
・十分な説明を行い、検討期間も与える。
まずは、従業員に対して、コロナの影響で会社の業績が急速に悪化していること、給料減額を実施する必要があること、対象となる従業員の範囲、引き下げの具体的な内容、引き下げの実施期間、給料減額以外の手段の実施状況等について、会社の実情に即してできるだけ具体的に説明し、従業員に理解してもらうような丁寧な対応が必要となります。
のちに従業員から「会社から十分な説明がなかった」「内容を理解せずに合意をした」といった指摘がなされた場合、従業員が真に合意したかが問題となります。
また、従業員に十分な検討期間も与えることも必要となります。従業員にとって、賃金は重要な労働条件ですので、従業員が十分に納得しないまま給料減額の決断を迫るような対応は、従業員の自由な意思に基づき合意したかどうかという点で問題となります。
・合意内容を書面にしておく。
従業員との話し合いの結果、従業員が給料減額に応じた場合は、合意内容を文書として残す対応が必要になります。
後に従業員との間で給料減額に応じたかどうかのトラブルを避ける意味でも、合意内容を書面化することが望ましいといえます。
他方、従業員に対して、「同意しないなら辞めてもらう」「同意しないなら人事評価を下げる」の発言をすることは避けるべき対応といえます。
これらの発言があり、録音されていた場合、後になって、会社からの不当な圧力によって同意することを強制された等の主張を受け、給料減額合意の効力が否定される可能性が高まるおそれがあります。
参考裁判例
○参考裁判例1:大阪高判平成10年7月22日(駸々堂事件判決)
給料減額を含む新社員契約書に署名していたことについて、裁判所は、「新社員契約に応じなければ、被控訴人との雇用関係を維持できず、退職せざるを得ないものと考えて、新社員契約を締結したものと認めら」れると認定し、結論として、「新社員契約締結の意思表示は錯誤により無効」との判断がなされました。
○参考裁判例2:東京地判平成20年1月25日(日本構造技術事件判決)
会社側は、従業員と給料減額の合意があったと主張しましたが、合意書はありませんでした。
裁判所は、「重要な労働条件の変更には,上記のような多数組合なり労働者の過半数代表者との書面による合意,あるいは労働者各人からの同意書なりを徴求することによって意思表示の確実を期さなければ確定的な合意があったとは経験則上認めることは難しい」と述べ、合意の存在を否定しました。
まとめ
給料減額の有効・無効について、裁判所は従業員の同意が真意に基づくものであるか否かについて慎重に判断する傾向にあるため、こうした判断の傾向を念頭に置いた対応が必要となります。
就業規則変更について
従業員の同意が得られなかったにもかかわらず就業規則を不利益変更する場合、有効性判断の考慮要素として労働契約法が掲げるのは以下の4つです(労働契約法第10条)。
ⅰ 労働条件変更の必要性
ⅱ 労働者の受ける不利益の程度(経過措置・代償措置の有無や内容も含む)
ⅲ 変更後就業規則の内容の相当性(相場との比較等)
ⅳ 労働組合等との交渉の状況
(ⅴ その他の就業規則の変更にかかる事情)
労働条件変更の必要性
判例は、「賃金、退職金など労働者にとって重要な権利、労働条件」に関する「変更については…そのような不利益を労働者に法的に受忍させることを許容することができるだけの高度の必要性」が求められる、としていることに留意が必要です(最判平成9年2月28日(第四銀行事件判決))。
もっとも、コロナ禍による急速・大幅な業績悪化が存在する場合は、高度の必要性が認められる場合も少なくないと考えられます。
また、ⅰ労働条件変更の必要性は、それ単体で判断されるものではなく、ⅱ労働者の受ける不利益の程度とのバランスの問題でもあると解されております。
すわなち、ⅰ労働条件変更の必要性が高ければ、ⅱ労働者の受ける不利益性の高い変更も認められる傾向にありますし、他方、ⅰ労働条件変更の必要性が低いとしても、ⅱ労働者の受ける不利益性を低く抑えれば、それも是認される余地はあります。
経過措置・代償措置について
コロナ禍の場合、早急な対策が必要であるため、経過措置を設けるのは現実的でない場合もあります。
このような場合の代償措置としては、例えば、他社との雇用契約締結を締結し、勤務時間外に副業をすることを認めること等が考えられるところです。
まとめ
コロナ禍を理由とした就業規則の不利益変更にあたっては、外出に伴う消費の冷え込みや急速な業績悪化について具体的な裏付けをもとに労働条件変更の必要性を説明することが重要となります。
また、一時的とはいえ賃金という従業員とって重要な労働条件に関わるものであることからすれば、会社としては、過去の裁判例の傾向も踏まえ、丁寧な対応が求められます。
もっとも、コロナ禍における急速な業績悪化の中で、どの程度の時間的余裕があるかを念頭に現実的な対応をせざるを得ない側面もあると考えます。
内定取消し
経営環境の悪化を理由とする内定取消し
採用内定時には予測できなかったコロナ禍による経営状況の悪化を理由とする場合、採用内定者本人の適格性等を理由とした取消しではなく、会社側の事情による取消しであると整理されます。
この点、中途採用者に対する内定取消しの事案ではありますが、東京地決平成9年10月31日(インフォミックス事件判決)は、「企業が経営の悪化等を理由に留保解約権の行使(採用内定取消)をする場合には、いわゆる整理解雇の有効性の判断に関する…四要素を総合考慮のうえ、解約留保権の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ、社会通念上相当と是認することができるかどうかを判断すべき」と判示し、いわゆる整理解雇の4要素を考慮の上、その効力を判断するとしております。
そのため、内定取消しにおいて整理解雇4要素が考慮される場合、既に勤務を行っている従業員よりもいまだ勤務を行っていない内定者を優先して削減する点で人選の合理性はあるとしても、内定取消しの回避努力義務や取消し手続は適正に行われる必要があります。
何らかの回避努力義務の履行としては、例えば、各種助成金の申請、契約内容変更(賃金額、入社日、入社先)の条件交渉等が挙げられます。採用内定者に対して十分な説明を行い、不利益を緩和する措置をとることが重要になります。
なお、違法な内定取消しは労働契約上の地位確認請求のほか、損害賠償請求の対象となります。
新卒採用者の内定取消しにあたっての留意点
上記のほか、内定取消しの対象が新卒採用者の場合、以下のとおり、ハローワークへの届出義務が課されております。
〇職業安定法施行規則第35条2項
「学校…、専修学校、…を新たに卒業しようとする者(以下この項において「新規学卒者」という。)を雇い入れようとする者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ、公共職業安定所…に…その旨を通知するものとする。
②新規学卒者の卒業後当該新規学卒者を労働させ、賃金を支払う旨を約し、又は通知した後、当該新規学卒者が就業を開始することを予定する日までの間(次号において「内定期間」という。)に、これを取り消し、又は撤回するとき。」
また、厚生労働省は、新卒採用者の内定取消しに関し、厚生労働大臣が定める場合(下記参照)に該当するときは、その報告内容を公表するものとしております。
○厚生労働省「新規学校卒業者の採用内定取消しの防止について」「2 概要」「(3)採用内定取消しを行った企業名の公表」
①2年度以上連続して行われたもの
②同一年度内において10名以上の者に対して行われたもの(内定取消しの対象となった新規学卒者の安定した雇用を確保するための措置を講じ、これらの者の安定した雇用を速やかに確保した場合を除く。)
③生産量その他事業活動を示す最近の指標、雇用者数その他雇用量を示す最近の指標等にかんがみ、事業活動の縮小を余儀なくされているものとは明らかに認められないときに、行われたもの
④次のいずれかに該当する事実が確認されたもの
・内定取消しの対象となった新規学卒者に対して、内定取消しを行わざるを得ない理由について十分な説明を行わなかったとき
・内定取消しの対象となった新規学卒者の就職先の確保に向けた支援を行わなかったとき
まとめ
採用内定者にとって、内定取消しはその不利益が甚大です。
内定取消しによって、本人は、再度就職活動を再開する必要があります。
特に、内定を取り消されたのが新規学卒者の場合は、内定取消しの通知時期によっては、別の企業の採用試験がすでに終了し、満足な就職活動を行うことができない可能性もあります。そのため、内定取消し後に法的紛争に発展するリスクが少なくありません。
また、企業にとって、SNSや口コミによる拡散、メディアで報じられるリスクもありますし、翌年以降の採用活動にも影響を及ぼすおそれもあります。
そのため、コロナ禍による経営状況の急速な悪化による内定取消しは、限定的な場面での実施が想定されます。また、内定取消しに正当な理由がある場合であっても、会社側としては、内定者の理解を得るための説明を尽くすなどの誠実な対応が求められますし、一定の金銭補償を提案して話し合いにより解決する方法も現実的といえます。
不利益変更に関するご相談は西村綜合法律事務所まで
不適切な手続きや説明不足は訴訟リスクをもたらします。当事務所では事前の助言や方針の立案、さらには必要な場合には同意書の作成など、企業側を全面的にサポートします。
また、顧問契約による継続的な支援も可能です。法律情勢は日々変化し、それに対応するためには専門的な知識と情報が求められます。
西村綜合法律事務所ではオンライン形式も可能な初回無料相談を実施中です。まだ手探りの状況であっても、少しでもお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

 メール・Web
メール・Web