会社破産・法人破産について弁護士が解説
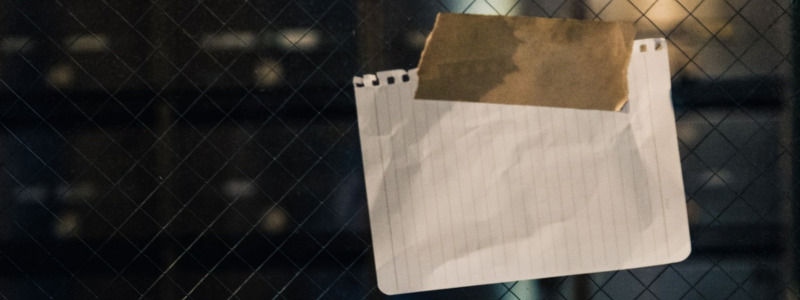
法人の「破産」とは、様々な理由から、これ以上会社を継続的に経営していくことが難しいという倒産状態にある企業を法律に従って処理する(会社をたたむ)手続きのことをいいます。
破産手続は、破産する旨を裁判所に申し立て、裁判所から破産管財人が選任され、最終的に会社の財産を債権者に公平に配当するという流れで行われます。
会社破産を弁護士に依頼するべき理由
債権者からの取り立てが止まります
弁護士が破産手続きを受けると、まず破産会社や債権者の状況を適切に判断したうえで、債権者全員に対して「受任通知」を送付することが一般的でず。
この通知を受け取った債権者は、弁護士と直接交渉することになります。
その結果、会社自体への直接の取り立て行為は停止します。この受任通知が、実質的に債権者の取り立てを防ぐ役割を果たします。
予納金を低く済ませ、全体的な費用を節約することが可能です
破産の申立をする場合には、裁判所に、予納金や官報公告費を納める必要があります。
予納金とは、破産管財人が破産手続を行うための実費や破産管財人の報酬に充てるために、裁判所に納める費用となります。
予納金の額は裁判所によって異なりますが、弁護士を代理人とせず個人で申立てする場合には、破産管財人の業務負担が大きくなり、弁護士申立ての場合以上の高額な予納金を求められることになり、かえってコストがかかってしまう場合があります。
専門知識による最適な判断、経営者様の権利を最大限に保護します
また、破産法では、破産手続開始前に行う特定の債権者への弁済行為や財産処分行為等が問題となる場合があり、その判断には専門的知識が必要不可欠です。
さらに、法人破産をする場合には、個人破産と比較して、多数の債権者や金融機関等、利害関係人が多いことから、慎重な準備と適切な判断が求められます。
このような点を踏まえると、弁護士費用がかかることを差し引いたとしても、破産後の再出発をより円滑にするという観点からも、専門家である弁護士に依頼されることをお奨めします。
私たち弁護士は、会社が清算する場合にも、経営者に寄り添って、経営者やご家族、従業員の方の権利を最大限保護し、人生の再スタートが切れるようにお手伝いします。
会社破産そのものを決断するメリット・デメリット
メリット
・債務が免除され、返済や取立てにあわない
⇒弁護士に依頼をした時から、即日債権者に対して支払停止の通知を発送します。その後のやりとりや交渉は全て弁護士が対応しますので、直接依頼者に対する取立てはなくなります。
・債権者の理解・協力を得られやすい
⇒私的整理とは異なり、破産手続きは必ず裁判所を通して手続きが行われます(法的整理)。法律の規定に則って処理されるため透明性があり、公平性を欠くこともないため、債権者の理解を得られやすいといえます。
・負債が消滅するため、資金繰りに悩む必要がなくなります
⇒破産手続きが完了したら、会社は清算され、法人格そのものが消滅します。そのため負債がなくなりますので、資金繰りで悩む必要がなく、再スタートの準備に時間をかけることができます。
デメリット
・会社を再建することはできません
⇒中小企業は、経営者が会社の債務保証をしているケースが多く、その場合は会社の破産手続きと同時に、経営者の個人破産をすることになります。経営者自身が破産をすると、金融機関からの借入が不可能になりますので会社を築くことは難しくなります。
社会的信用の損失もありますので、どうしても、会社を再建させたい場合は民事再生という手法を選びましょう。
・従業員の解雇
⇒破産の場合、会社そのものが消滅しますので、勤めている従業員を全員解雇する必要があります。伴い、会社がこれまで培ってきたノウハウも失います。従業員の今後を考えた解雇の手続きを取ることで、次の就職時に保険や年金等で困らせないようにしましょう。
・裁判所を通じた法的手続きのため、破産決定が官報に掲載され、公となる。
破産手続きは裁判所を通じた法的手続きであるため、破産手続開始決定は官報に掲載されます。これは企業の信用に大きな打撃を与え、取引関係者や顧客、投資家などへの信頼を失う結果となります。また、これは企業の社会的評価を低下させる可能性もあります。
会社破産の流れ
弁護士が債権者に受任通知を送ることで、これまでの取立ては依頼者に来ることはなく、直接弁護士が交渉することになります。
債務者と債権者が破産の申立て手続をすることにより、破産手続は開始します。申立ては会社の所在地を管轄する地方裁判所となります。(主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所が原則ですが、東京地方裁判所の場合は全国の法人破産申し立てをすることが可能です)
裁判所により破産手続きの開始が決定されると、株式会社は解散し、同時に破産管財人が選任されます。破産管財人も弁護士ですが、申立側弁護士とは違い、中立の立場から破産事務を取り扱います。
債権者は、破産管財人により定められた期間のうちに、破産債権の届出をする必要があります。届出られた破産債権は、破産管財人の債権調査を経た後確定されます。
破産債権の確定手続と平行し、破産財団(破産会社の財産:管財人が管理する)の調査・管理を行う必要があります。破産管財人は破産者の財産を正確に把握しなくてはなりません。また、役員等に対する責任追及が行われ、場合によっては損害賠償請求などが行われることもあります。
そうすると役員から破産財団もお金が入り、会社の財産(財団)が増えるからです。最終的には財産を可能な限り現金化し、配当の準備を進めます。
破産管財人の裁量により、換価が進んだ破産財団を随時債権者に配当していくことが可能です。(債権者として、配当が1年もないよりは、少しでも早く配当を受けたい場合も多いからです。)
破産財団の換価がすべて終了した後、届出をした破産債権者に対して配当が行われます。最後配当は厳格な手続の下で行われますが、配当金額が少ない場合の簡易配当や、届出破産債権者全員の同意が得られた場合の同意配当のように、状況に応じた簡易迅速な配当方法を取ることも出来ます。
最後配当が終了した後、債権者の異議申し立て期間が終了したときには破産手続終結が決定されます。この決定により、会社は消滅することになります。
破産する上での注意点
債権者からの急な取り立てがあるかもしれません
破産を申請する前に、債権者が気配を察知して急な取り立てをすることがあります。
債権者として迅速に債権を回収するための行動といえますが、全てに向き合ってしまうと精神的に疲弊してしまうおそれがあります。また、支払不能に陥る危機的状況における抜け駆け的な債権回収は違法とされます。
事前に債権者に対しての適切なコミュニケーションと状況の説明が重要となりますが、弁護士に依頼することで、状況に応じて受任通知を債権者へ送付することにより、追加の取り立てを防ぐことも可能です。
事前に申し立て費用を確保してください
破産申立てには、裁判所に納める予納金や弁護士費用などの費用が必要です。
財務状況が厳しくとも、これらの費用がなくては法的な手続きを行うことができません。そのため、資金が完全に底を突く前に弁護士に依頼するべきでしょう。
特定の債権者への弁済が否認されることがあります
破産申立て前に、特定の債権者だけに多額の返済を行った場合、それが偏頗弁済とみなされ、そこ効力が否認されることがあります。
すべての債権者に対する公平な対応を心がけましょう。
手続期間の日常業務が制限されます
破産申手続中は、多くの業務が制限されます。新たな借金をすることはできず、財産の自由な処分が制限されます。
ストレスの強まる期間ではありますが、生活再建に必要なステップです。例としては以下のような制限が挙げられます。
新たな借り入れの禁止
破産手続きが開始されると、新たな借り入れや負債の発生は原則として禁止されます。これは、債権者間の公平を維持し、追加的な債務の発生を防ぐためのものです。
財産の差し押さえ
破産手続きが開始されると、財産は破産管財人の管理下に置かれます。その後、財産の保全・換価処分が行われ、債権者への配当が行われます。この間、財産の管理、使用・収益・処分が制限されます。
取引の制限
裁判所または破産管財人の許可が必要となる取引があります。これには、不動産の売却や重要な資産の売却などが含まれます。
会社破産したら経営者も破産しないといけないの?

経営する会社が破産する場合、その会社の社長個人も同時に破産をするという事例は、確かに多いです。
しかし、会社が破産する場合、その会社経営者も必ず自己破産しなくてはならないということではありません。
会社には、法律によって、経営者個人とは別の人格である「法人格」が認められています。つまり、法人・会社の代表取締役などの代表者は、その法人の機関として対外的な代表権を有していますが、あくまでも、その法人自体と代表者個人とは別人格ということになります。
そのため、会社が破産した場合でも、原則的に、別人格である会社経営者はその債務を引き受ける必要はありません。そして、会社の負っていた債務は、会社の破産手続の終結ともに消滅するのが原則です。
借入の連帯保証人になっているとどうなる?
しかし、会社が借入を行う際、代表取締役がその連帯保証人となっている場合には、会社の破産と同時に会社経営者個人も、破産手続開始の申立てを余儀なくされることが多い、あるいは、会社とあわせて破産をするほうが望ましい場合が少なくありません。
会社が銀行等の金融機関から運転資金を借りようとする場合、金融機関から経営者に対して、連帯保証人をつけることが求められることは日常的なことでしょう。
この連帯保証人の責任はとても重いです。連帯保証契約が締結された場合、連帯保証人(会社経営者)は、債権者(金融機関等)との関係では、主たる債務者(会社・法人)とほとんど同じ立場に立たされ、非常に大きなリスクを負うことになります。
自己破産申立をするケースが多い
また、会社の運転資金貸付の契約を締結する際、金融機関により、会社が破産手続の開始を申し立てたときには弁済期を待たずに連帯保証人に対して主債務の全額を請求することができるという特約(期限の利益喪失約款)を付されることが少なくありません。
そのため、最悪の場合には、会社が破産手続開始の申立てをするのと同時に、代表取締役等は、会社の債務の全額を負担する義務を負うことになります。
言い換えると、会社だけが破産したとしても、その手続によって、連帯保証人である代表者や役員等まで支払義務を免れることにはならないということです。
さらに、代表取締役等の会社経営者が会社の連帯保証人となってお金を借り入れる場合、その額は個人が借りる場合に比べて非常に高額に上ることが一般的です。実際、その負債額を、代表取締役個人が返済できることは困難といえます。
このような事情から、会社が自己破産をする場合には、 会社と同時に代表取締役個人も自己破産申立をすることがほとんどといえます。
代表取締役等が会社と同時に破産申立てをするメリット
代表取締役等は、会社の破産手続とは別個の手続で自己破産することもできます。
しかし、実際には、代表取締役等が破産申立てをする場合には、会社の破産手続と一緒に申し立てられることが一般的ですし、そのほうが望ましいでしょう。
なぜなら、会社破産と同時に破産手続を申立てることには、代表取締役等にとって、次のようなメリットがあるからです。
まず、別の手続で代表取締役が破産申立をする場合と比べて、代表取締役等の破産を会社破産と同時に行う場合、通常、費用負担を割安に抑えることができます。
会社と代表取締役等は別人格ですから、本来であれば、各々の破産がそれぞれ別々に処理される場合、二件分の予納金を納めなければなりません。
しかし、東京地方裁判所などでは、「少額管財制度(一般管財制度)」という制度を運用しており、この少額管財制度を使って会社と代表取締役等の破産を同時に申し立てれば、会社と経営者個人の破産を別々に申し立てた場合よりも低い最低予納金(東京地方裁判所の場合、20万円~)で申し立てることができます。
他方で、少額管財制度の運用はしていない裁判所も存在します。しかし、少額管財制度の運用はしていなくとも、例えば、岡山地方裁判所の場合、会社と経営者個人の同時申立てが可能であり、別々に申し立てた場合よりも低い最低予納金額(45万円~)で申立てることができます。
少額管財制度(一般管財制度)を利用する場合には、弁護士を申立人として選任する必要があります。そして、破産手続が開始される場合には、裁判所が弁護士を破産管財人として選任します。破産管財人は、破産手続を主導する立場にあり、財産調査・管理・処分・債権者対応や配当などを行っていきます。
また、少額管財制度を利用するか否かにかかわらず、会社の財産と代表取締役等の財産が重なっているなど会社と代表取締役等の破産に関係する事情が共通していることも多いので、会社と役員の破産手続を同時に申し立てることにより、1つの手続と扱われるのが通常です。したがって、同一の弁護士や破産管財人に処理を任せることとなるので、より迅速かつ円滑に破産手続を進めていくことができます。
もっとも、破産に関する制度運用は、少額管財制度(一般管財制度)を運用しているかどうか、少額管財制度の運用形態などは、上記のように裁判所によって異なります。
また、少額管財制度(一般管財制度)は、予納金の額を低く設定することで簡易迅速に破産手続を実現する制度であることから、債権者が多すぎる場合、売却に時間がかかる不動産などの財産がある場合、訴訟しなければ回収できない債権がある場合等、破産手続に時間がかかるような場合には、利用できない場合があります。
このようにケースバイケースの判断とならざるを得ないため、まずは、専門家である弁護士に相談されることをお奨めします。
会社破産と同時に自己破産することになった場合に、少額管財制度(一般管財制度)を利用できるのか等も含め、具体的状況を踏まえた上で、全力でサポートさせていただきます
会社破産に関するご相談は西村綜合法律事務所まで
代表弁護士からのメッセージ
経営者としては、最後まで会社再建のために頑張りたいお気持ちは良く分かります。もちろん、私たちも、企業再生のご相談を頂いた場合、最後まで貴社の再建のために全力を尽くします。しかしながら、状況によっては、どうしても再建が困難な場合もあります。そのような場合は、責任を持って会社を清算することも、経営者の大切な仕事です。そして、私たち弁護士は、そのような場合も、経営者に寄り添って、経営者やご家族、従業員の方の権利を最大限保護し、人生の再スタートが切れるようにお手伝いします。
一度、破産してしまうと全てがお終いという訳ではありません。会社法上も、破産は取締役の欠格事由から除外されています。破産しても、再び起業される方もおられます。
破産手続を選択する場合、従業員も全員失職することになりますが、給料や退職金などの労働債権を先に確保するなどして、従業員等に最低限の配慮をすることができます。破産を決断することは経営者にとって、もちろん、苦渋の決断であるとは思いますが、そうした状況を放置しても、問題が解決されることはないどころか、「自殺」や「夜逃げ」や「家族の離散」といった最悪の事態を招いてしまうこともあるのです。
あなたの会社が破産の危機に瀕している場合、あなた自身が精神的にも相当にきつい思いをされている筈です。1人で悩んでも答えが出ないばかりか、状況はますます悪化することが多々あります。第三者に相談するだけでも精神的に楽になることもあります。弁護士は当然、守秘義務を負っていますので、相談していることを他の誰かに知られることはありません。
あなたとあなたのご家族、従業員のためにも、一刻も早く、専門家である弁護士に相談し、客観的に状況を分析してもらった上で、然るべき措置を採ることをお奨めします。
西村綜合法律事務所ではオンライン形式も可能な初回無料相談を実施中です。お気軽にご相談ください。
初回無料相談はこちら

 メール・Web
メール・Web








