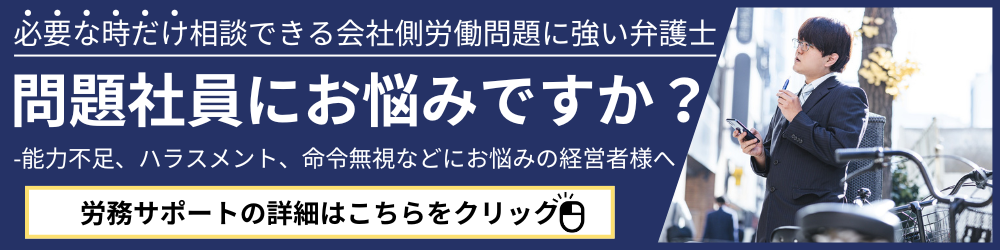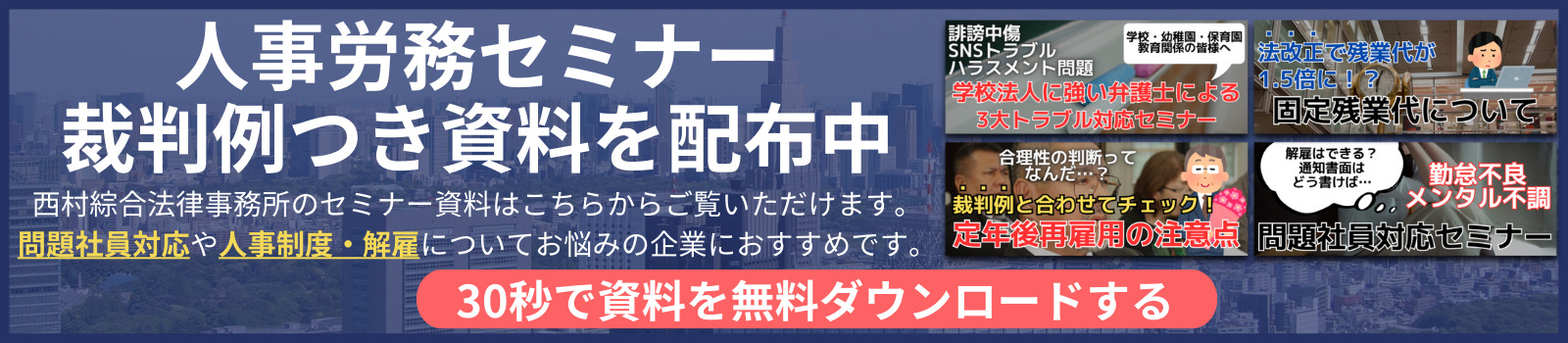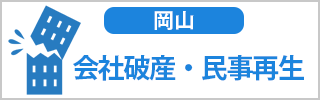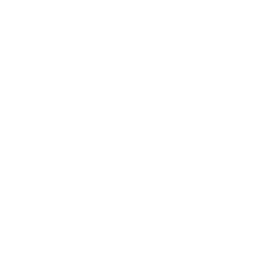問題社員を辞めさせることって可能?モンスター人材への対処方法を企業側弁護士が解説
企業が活動するには社員が必要です。しかし、企業の規模が大きくなり社員の数も増えてくると、能力不足、メンタル不調、横領等の問題行為を行うといった問題のある社員が生じることは避けがたいところです。
そのような問題社員を辞めさせることは可能なのでしょうか。企業における対応方法の注意点を解説します。
問題社員とは
企業においては様々な社員を雇用することになります。そのため、社員の様々な問題について法律相談をお受けしますが、特に、能力不足、メンタル不調、横領等の問題行為についてご相談を受けることが多いところです。
例①:能力不足
問題社員の例としては、企業が要求する成績を上げることができず能力が不足する社員が挙げられます。企業から相談を受ける頻度が最も多い問題社員の類型です。
例②:メンタル不調
精神的な不調を理由に企業を欠勤したり、繰り返し休業する社員も問題社員の類型と考えられています。近年はこの類型の社員に関する相談が増えています。
また、この類型の問題社員の特徴としては、解雇や退職勧奨を行う際に、パワハラの被害があったという主張がなされることが多いという点が挙げられます。
例③:横領等の問題行為
特に悪質なものとしては、横領等の問題行為を行い、企業の利益を犠牲に私利を図る社員が挙げられます。
企業としては、このような社員に対しては、厳格な対応をとる必要があります。
改善の余地がない場合辞めさせることは可能?
上記のとおり、企業から相談を受ける頻度が最も多い問題社員の類型は、能力不足の社員であり、このような社員を辞めさせることはできるのかというご相談を受けることが多いです。
一般的に能力不足の社員を解雇するには、客観的に能力が不足しているという事実と十分な教育訓練を実施しても改善の余地がないことを立証する必要があるとされています。
もっとも、特定の社員の成績の悪さいうものは、当該社員と接し、当該社員の業務への取り組み方や人となりを把握している上司や同僚からすれば当たり前なのですが、そのような成績の悪さを企業外の裁判所に客観的な事実として伝えることは容易ではないと考えられています。
また、多くの企業では能力不足の社員に対して、労力を費やして教育訓練を実施するよりも、当該社員に見切りをつけて別の方策を講じる方が、割に合うと判断する傾向にあり、十分な教育訓練を実施するというインセンティブが働かないという実情があるところです。
そのため、改善の余地がない場合に社員を辞めさせるというハードルは低いものではなく、特に気を付けて手続を進める必要がある場面と考えられています。
対応方法に関する検討事項
企業が、上記のような問題がある社員を辞めさせるには、主に退職勧奨を行うという対応方法と、解雇を行うという対応方法が存在します。
退職勧奨
退職勧奨とは、企業が社員に対し、退職するよう促し、双方の合意により雇用契約を解消させることをいいます。
解雇と異なり、企業と社員の合意に基づく退職となります。そのため、解雇事由が存在しないと考える場合にも退職勧奨を行うことは可能であり、双方で合意が得られれば、社員に企業を辞めてもらうことが可能となります。
もっとも、社員が退職の意思がないことを表明しているにもかかわらず、退職勧奨を継続するなど、労働者の自由な意思決定を妨げ、人格的利益を侵害するような態様で退職勧奨を行った場合は、民法上違法な行為と判断され、損害賠償責任を負う可能性がありますので、注意が必要です。
解雇
解雇とは、企業が社員に対し、一方的に雇用契約を解消することをいいます。先に述べた退職勧奨とは、企業が一方的に社員との雇用契約を終了させるという点で相違しています。
もっとも、簡単に企業が社員の雇用契約を一方的に解消できてしまうと、社員としては日々の生活が極めて不安定に陥る可能性が生じてしまいます。
そのため、労働契約法第16条では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定し、客観的な合理的な理由が存在し、社会通念上相当と認められる場合に限って、企業が社員を解雇することを認めています。
問題社員の対応方法を検討する際の注意点
問題社員に対し、どのような対応をとるかを実際に検討するにあたっては、以下のような点に注意して手続を進めることが必要になります。
就業規則上での解雇事由の確認
問題社員を解雇するにあたっては、社員の行動が具体的に就業規則上のどの解雇事由に該当するかを確認することが必要です。
就業規則における解雇事由については、就業規則に記載された解雇事由に基づいてのみ社員を解雇できるという限定列挙説と、就業規則に記載されていない解雇事由に基づいても社員を解雇できるという例示列挙説が存在します。
裁判所がいずれを採用するかは必ずしも明らかとなってはいませんが、ほとんどの企業においては、就業規則の解雇事由について、「その他前各号に準ずる事由がある場合」といった包括的な条項が設けられているはずです。この包括的な条項に基づく解雇も有効ですので、上記の限定列挙説と例示列挙説に関する議論はあまり意味がないところです。
もっとも、自社の就業規則にこのような包括的な条項が見当たらない場合は、就業規則に不備が存在する可能性が高いと思われますので、就業規則の点検が必要になります。また、解雇を行う場合は、社員のどのような行為が就業規則の解雇事由に該当するのかを社員に明らかにする必要があります。そのため、社員の問題行為が就業規則上のいかなる解雇事由に該当するのかをきちんと確認することは非常に重要な手続となります。
解雇制限期間への該当の有無
問題社員を解雇するにあたっては、法律上、一定の期間は解雇することができないとされる解雇制限期間が存在します。そのような期間中は、例え、社員に重大な問題が存在したとしても企業は社員を解雇することができません。解雇制限期間中に解雇を行った場合は、そのような解雇は無効になり、罰則も定められていますので企業は注意する必要があります。
解雇制限期間は労働基準法第19条で規定されていますが、同条は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のための休業期間及びその後30日間、と産前産後休業期間及びその30日間については、企業は社員を解雇できないものと規定しています。
解雇制限となるのは、あくまでも業務上の傷病による休業期間に限られています。また、業務上の傷病が治癒(症状固定)に至った後に30日が経過した場合、解雇制限は適用されなくなります。
いきなり解雇を検討しない
上記のとおり、労働契約法第16条により、客観的な合理的な理由が存在し、社会通念上相当と認められない限り解雇は認められないとされています。そして、裁判では、そのような解雇事由が存在することは企業が立証する必要があると考えられています。
そのため、一般的には、問題がある社員であっても、企業が社員を解雇するハードルは低くないとされています。
そこで、企業としては、社員をいきなり解雇するのではなく、十分な指導あるいは配置転換を行い、また、非違行為については解雇よりも軽微な処分を行い、それでも改善が見られないような場合に解雇を検討するという方針を採る必要があります。
問題社員への対応方法は弁護士にご相談ください
問題社員に対し、どのように対応すべきかという問題は、企業として非常に悩ましい問題ではないかと思われます。解雇が有効かという問題や退職勧奨がどこまで許されるかという問題は、時に微妙な判断を迫れられることが多く、専門家でないと判断を誤る可能性が高いと思われます。
万が一、解雇が無効と判断される場合、企業に極めて重大なダメージが生じるところですので、問題社員に対する解雇を検討している企業は特に弁護士に相談することをお勧めいたします。
問題社員への対応方法は弁護士にご相談ください
「問題社員を辞めさせることって可能?モンスター人材への対処方法を企業側弁護士が解説」の関連記事はこちら
- 諭旨解雇をするには?懲戒解雇との違いや法的な注意点を弁護士が解説
- 解雇や退職勧奨に踏み切る際の注意点!!問題社員(モンスター社員)への対応に強い弁護士が解説
- 異動や配置転換を拒否する社員への会社としての対応を解説
- 協調性のない社員やお局さん型の従業員を解雇するには?問題社員対応に強い弁護士が解説
- 解雇を見据えた問題社員との付き合い方・指導方法を徹底解説
- 能力の低い社員を配置転換したい!有効なケース、無効になるケースを徹底解説
- ローパフォーマー社員って?能力不足の部下・職員に会社として対処するには
- これって問題社員?辞めさせることはできる?パターン別の対処法を徹底解説
- 懲戒処分の要件・種類を弁護士が解説!法的に有効な処分を科すポイントって?
- 問題社員を辞めさせることって可能?モンスター人材への対処方法を企業側弁護士が解説
- モンスター社員を辞めさせる方法って?退職勧奨の流れと注意点を労働弁護士が徹底解説
- 自主退職させるための退職勧奨のポイント!解雇との違い、違法になるやり方を弁護士が解説

 メール・Web
メール・Web