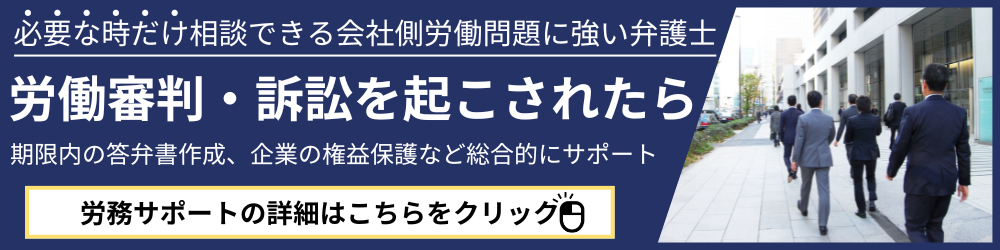労働訴訟を起こされたら?労働問題の裁判・審判に強い弁護士なら西村綜合法律事務所
「解雇した従業員から解雇無効を求める労働訴訟を起こされてしまった」
「残業代の支払いを求める内容の訴状が届いたが、どう対応していいか分からない」
などと、従業員や元従業員が会社を相手として、裁判所に労働トラブルの解決を求め訴えを提起してくることがあります。このように、会社が従業員や元従業員から労働問題の解決を目的として裁判所に訴えられてしまった場合、会社としては訴訟手続上今後どのような対応が必要となるのでしょうか。以下では労働訴訟の特徴と流れについて、会社側の視点からご説明します。
労働訴訟とは
訴訟とはいわゆる裁判のことです。
労働訴訟とは、労使間に生じた労働トラブルを裁判所の訴訟手続きによって裁判官が判断を下すことにより、問題の終局的な解決を図ろうとするものです。
昨今、労使間の労働問題に関する紛争件数は増加傾向にあり、特に近年の急激な従業員の権利意識の高まりとともに、未払い残業代や不当解雇、ハラスメントの損害賠償といった内容の紛争が後を絶ちません。
そのため、労働訴訟は会社が従業員に対して訴訟提起することも実際は可能であるものの、実態としては従業員が会社の労働法令違反に対して訴訟を提起する場合がほとんどです。
では、実際に労使間に労働紛争が生じてしまった場合どのくらいの事案が訴訟により解決されているのでしょうか?
まず、会社と従業員との間で労働紛争が生じた場合その多くにおいて労働審判による解決が試みられていますが、労働審判手続きにおいて解決に至らず労働訴訟に発展するケースもあります。
もちろん、はじめから訴訟での紛争解決を求めることも可能です。
もっとも、労働訴訟といっても通常の民事訴訟手続きと何ら手続面で異なるところはありません。
これらは単に通常の民事裁判のうち労働問題に関する訴訟を労働訴訟と呼称しているだけです。
ただ、労働事件を特別に取り扱う労働事件専門の裁判所は設けられていないものの、東京・大阪・横浜・名古屋・福岡などの規模の大きい裁判所では労働訴訟を専門的に取り扱う労働専門部や集中部が設けられている場合がありますので、この点については労働訴訟特有のものとなります。
会社側の対応のポイント
無視すると敗訴となってしまうため必ず対応しましょう
労働訴訟、つまり裁判が起こされた場合、何も対応することなく第1回目期日を無視してしまうと、相手方の主張を認めたとみなされ敗訴してしまいます。
そのため、訴状が届いたら、速やかに適切な対応を取ることが重要です。
従業員との労働契約を精査しましょう
労働訴訟においては、従業員との間に結ばれた労働契約が重要な役割を果たします。
契約内容を精査し、契約違反や不当な扱いがなかったことを証明できるよう、契約書、就業規則、採用時の労働条件通知書や関連する書類を整理することから始めましょう。
客観的な資料を確保したり、他の従業員への聴取を進めましょう
例えばパワハラ行為や発言が問題になっている場合、「いつ、どこで、誰が、どういう流れで、どんな言葉や行動をしたのか、普段の関係はどうだったのか」などを、具体的にチェックしておくことが大切です。
関わった社員から話を聞くときは、例えば業務日誌やLINE、メールなど、事実が文字としてのこっている証拠ないかも見ておくといいでしょう。こうした書類を集めていく過程で社員の記憶がはっきりすることもありますし、社員と会社の主張が異なるときの判断の手がかりにもなります。
労務に強い弁護士に依頼しましょう
労働訴訟は複雑であり、専門的な知識が必要です。
労務問題に強い弁護士に依頼することで、法的な観点から最適な対応策を立てることができます。また、弁護士は書面の作成や裁判での代理も行ってくれるため、訴訟手続きの負担を軽減することができます。
労働訴訟の特色
労働訴訟とは、通常の民事裁判のうち労働問題に関する訴訟を単に労働訴訟と呼称しているだけであって訴訟手続面では通常の民事裁判と何ら変わりのないものであることについては、先ほどご説明させていただきました。
以下では、そんな民事訴訟に共通する訴訟制度についてご説明させていただきます。
労働訴訟を提起する場合、その求める権利の額(訴額)によって訴訟を提起できる裁判所が異なります。
訴額が140万円以内であれば簡易裁判所へ、訴額が140万円を超える場合は地方裁判所となります。
労働紛争を解決するための手段には様々なものがあります。
一般的によく利用されている手段としては、労働審判制度などの方法が挙げられます。
そしてこの労働審判制度と労働訴訟とを比較した場合には、問題解決までの平均所要時間が大きく異なってきます。
基本的に労働審判制度においては3か月以内という比較的短時間での解決が可能であるのに対し、労働訴訟の場合には労働審判よりもかなり長い時間が必要となります。
令和元年7月19日に公表された「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第8回)」によれば、労働関係訴訟の平均審理期間は14.5か月となっており労働訴訟では審理が長期化する傾向にあります。
そのため、労働訴訟で労働紛争の解決を図ろうとする場合には少なくとも1年以上の時間が掛かるものであると覚えておいてください。
労働裁判は公開されるのが原則です(裁判公開の原則)。
この原則により、労働裁判においては口頭弁論や判決の手続きは公開の法廷で実施されます。
そのためいったん労働裁判が提起されると、会社名や訴えの内容等が世間に公開されることになります。
仮に会社が法令違反等を行っていた場合には会社の実態が世間に知られてしまうことになりますので、会社の社会的信用の失墜は避けられないでしょう。
訴訟制度に労働トラブルの解決を求めた場合、当事者間での和解による解決が困難な紛争であっても判決によって終局的な解決を図ることが可能となります。
そしてこの「紛争の終局的な解決」という訴訟制度の特徴は、訴訟制度の最大のメリットであるとも言えます。
それでは、「紛争の終局的な解決」とは何を差すのでしょうか?
現在、日本の訴訟制度では三審制がとられています。
三審制とは、訴訟制度上第一審の判決に不服がある場合は当事者に控訴を認め、第二審の判決に不服がある場合は上告を申し立てることで第三審の裁判を求めることができるというものです。
そして控訴や上告が可能である期間内にこれらの申立てがなされなかった場合には、判決が確定します。
また上告審で判決が下されれば、その判決は確定した判決となります。
このようにして確定した判決に対しては、終局的に紛争を解決させる効果があるので、判決が下されると当事者は他の機関に異議を申し立てることができなくなります。
つまり、いったん裁判所により判決が下されるとそれ以上紛争については争えなくなり、両当事者は裁判所の判断に拘束されることになるのです。
訴訟手続きの流れ
それでは会社が従業員から労働訴訟を提起された場合、訴訟手続きはどのように進行していくのでしょうか?
以下では、従業員から訴えが提起されてから裁判が終了するまでの訴訟手続きの一般的な流れについてご説明します。
労働訴訟は、民事訴訟法の規定に基づき訴えようとする者(原告)が地方裁判所または簡易裁判所に訴状を提出して訴えを提起することにより開始されます(ただし、簡易裁判所では、少額軽微な事件を簡易な手続で処理するため口頭で訴えの提起をすることができます)。
訴訟を提起された場合、裁判所から訴状と第一回口頭弁論期日への呼出状、答弁書催告書が特別送達郵便で届きます。
訴状とは原告が訴えを提起する際に裁判所に提出する書面のことで、その訴えに関わる当事者の氏名や請求の趣旨、請求の原因などが記載されています。
呼出状には、第一回口頭弁論期日の日時と答弁書の提出期限が記載されています。
答弁書とは第一回口頭弁論期日のために被告が提出する準備書面を指し、原告が訴状で主張した事実に対して、被告は準備書面を事前に提出した上で何らかの主張をしていくことになります。
答弁書には、訴状に記載されている請求を認めるかどうか、反論がある場合にはどのような反論があるのかを記載する必要があり、基本的には呼出状に記載されている裁判の日の1週間前までに裁判所に提出することになります。
もちろん民事訴訟は、弁護士に頼らず会社様ご自身で対応することも可能ですが、どのような請求を認め、どのようなことを反論すればよいのかについてはどうしても法律の専門知識や裁判の仕組みについての理解が必要になってきます。
特に答弁書は訴訟制度において非常に重要なものであり、答弁書の記載を誤ってしまった場合は、裁判において取り返しのつかない状態になってしまう可能性があります。
例えば、答弁書の「請求の趣旨に対する答弁」の欄については、請求の趣旨を争うか争わないかを記載する欄がありますが、絶対に請求を争わない旨の記載をしてはいけません。
誤って請求を争わない旨の記載をしてしまうと、即座に原告の主張通り(訴状通り)の判決が出てしまいかねません。
また同じく答弁書の「請求の原因に記載の事実」についても、不用意に自らに不利な事実を認めてしまうことに注意しなければなりません。
安易に原告の主張に従って自らに不利な事実を認めてしまった場合、訴訟法上「裁判上の自白」という取扱いがなされます。
これにより、裁判所は当該事実に拘束され、これに反する事実認定をすることができなくなりますので注意が必要です。
そのため、仮に訴えを提起された場合、どのような場合であっても弁護士に依頼されることをお勧め致します。
なお訴訟では、答弁書を提出することにより第一回口頭弁論期日に出頭しないことも可能です。
第二回期日以降は、基本的には原告と被告が交互に主張書面や証拠(書証)の提出を行います。
争点や証拠の整理が必要な事案においては、口頭弁論だけではなく非公開の別室で争点を整理する弁論準備手続が行われることもあります。
主張や書証による立証が尽くされた後、場合によっては人証(原告・被告の当事者に対する尋問や、証人の尋問)が行われることがあります。
当事者尋問とは、訴訟当事者本人を証拠方法として尋問する証拠調べのことをいい、その経験した事実につき尋問し当事者の供述から証拠資料を収集します。
一方で証人尋問とは、検察官や弁護士が証人に対して口頭で質問し証人に供述をさせ、その証言を証拠とする方法で行われる証拠調べのことをいいます。
裁判所は審理を行った結果、当事者間での話し合いの余地がある場合には和解を試みます。
当時者間で互いに譲り合って紛争を解決する旨の合意が成立した場合は、和解調書が作成され訴訟上の和解によって訴訟が終了することとなります。
一方で、和解による解決を試みたものの和解が決裂した場合や、和解での解決が見込めない場合には裁判所が判決を下すことになります。
当事者が判決に不満がある場合には原則として上級裁判所であと2回審理を受けることが可能ですが、当事者が上訴せず一定期間が過ぎた場合、又は上訴して2回の裁判を受けたときは判決が確定します。
弁護士に相談するメリット
書面作成や裁判への参加を代理してもらえる
もし従業員から労働審判や裁判を起こされたら、これらは裁判所で行われる正式な手続きなので、会社はルールに沿って、自分たちの言い分をまとめた文書や証拠を裁判所に出さなければなりません。
弁護士に相談する最大のメリットの一つは、書面の作成や裁判への参加を代理してもらえることです。これにより、会社側は日常の業務に専念しつつ、訴訟対応を進めることができます。
司法書士や社会保険労務士、行政書士などは、労働問題を扱う労働審判や裁判で会社を代理することは原則できませんので、労働審判や裁判に対応できるのは弁護士だけとなっています。
調査および聴取のサポートが受けられる
労働訴訟では、事実関係の調査や関係者の聴取が必要となることがあります。弁護士に依頼することで、これらの調査や聴取を効率的に進めることができ、専門家による適切な対応が期待できます。
会社側が有利になるように裁判を進めます
労働訴訟においては、労働者側の申し立てに対して適切に反証を行うと同時に、企業側の視点からも妥当な主張を展開し、説得力のある証拠を提出することで、裁判官に企業側に有利な判断を促します。
また、企業が不利な立場に立たされる可能性がある場合には、適切な時期に和解を提案し、敗訴のリスクや経済的損失を最小化する戦略を検討します。
労働訴訟にお困りの方は当事務所へご相談ください
労働トラブルが訴訟へと発展した場合、労使間における労働問題がある程度成熟した段階であると言えますので会社は早急にこれらに対処する必要があるといえます。
もっとも、労働訴訟手続きは非常に複雑なうえ、労働訴訟において裁判を有利に進めるためには適切な時期に適切な証拠を確実に主張していく必要があります。
仮に和解を試みる場合であっても、その内容やタイミング次第では会社に不利益が生じることも十分あり得ます。
したがって、もし会社が従業員から労働訴訟を起こされてしまった場合には、今後の労働訴訟を有利に進めるためにも、また誤った対応をしてしまい不利な状況に陥ることを防ぐためにも、ぜひ労務問題に精通した弁護士へご相談されることをご検討ください。
労働訴訟に強い弁護士にご依頼いただくことで、当事者間の和解案の調整から万一訴訟へ発展してしまった場合における訴訟代理に至るまで、会社様の紛争解決までを全面的にサポートをさせていただきます。
労働訴訟でお困りの際は、ぜひお気軽に西村綜合法律事務所までご相談ください。

 メール・Web
メール・Web