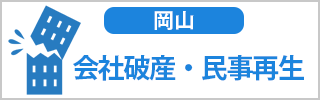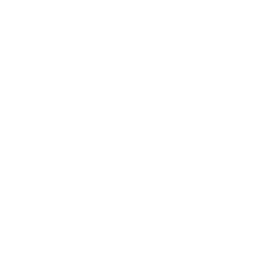建物賃貸借を行う際の契約書作成時の注意点を弁護士が解説
建物賃貸借は身近にありふれた契約ですが、事業や生活の本拠となる建物に関する契約であるため、安易に契約書にサインしてしまうことは禁物です。本記事では、建物賃貸借契約書を作成するときの注意点を解説してまいります。
建物賃貸借契約の基礎知識
まず、建物賃貸借契約について確認しましょう。
建物賃貸借契約とは
賃貸借契約の本質的要素は、目的物を使用収益することと使用収益の対価として賃料を支払うことの合意とされています。すると、建物賃貸借契約は、賃貸借の目的物を建物とし、建物の使用収益をすること、対価として賃料を支払うことを合意する契約をいうものとなります。
建物賃貸借契約に関係する主な法令は、民法、借地借家法、消費者契約法などがあります。これらの法令の下、建物賃貸借関係は規律されています。
契約書の記載事項(概要)
それでは、建物賃貸借契約のための契約書と機能するためには、どのような事項が記載されている必要があるのでしょうか。
まず、賃貸借契約といえるために、最低限、目的物を使用収益することと使用収益の対価として賃料を支払うことの合意が必要であり、また、目的物が建物であることが記載されている必要があります。一般的には、その他にも、契約期間や使用目的、敷金等の合意などを記載することも想定されます。
契約書の項目別|契約書作成時の注意点
次に、実際に記載項目ごとに契約書作成時の注意点を説明します。
当事者・物件の特定
契約の主体、契約の目的物となる物件を契約書上、特定する必要があります。この特定を適切に行わないと、当該契約から発生する法的義務を誰が負うのか、どの物件に関する契約なのかが不明となり、紛争の火種となることがあります。
当事者の特定は、一般的には住所や氏名(法人の場合は名称)で行います。
物件の特定は、通常、不動産登記簿に記載されている事項によって行います。具体的には、所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積といった項目があります。建物の現況と登記簿上の記載に食い違いがないかを確認しておきましょう。
使用目的
次に、使用目的です。
「住宅」、「事務所」、「店舗」、「倉庫」というような記載が一般的です。
この使用目的以外の目的のために目的物を使用収益した場合、目的外使用として、契約に違反することとなります。賃貸人としては、契約の解除や損害賠償を求めることができます。
契約期間と契約の更新
続いて、契約期間と契約の更新に関する事項です。
期間を定めずに契約をすることもできますが、建物賃貸借契約においては、期間の定めを設けるケースが一般的です。
契約期間を定めたとしても、期間満了時には当事者双方が契約更新の合意をすることによって、従前の賃貸借契約が更新されます。
もっとも、仮に更新の合意をしなかったとしても、直ちに賃貸借契約が終了するものではありません。
契約期間満了によって賃貸借契約を終了させるためには、期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知をする必要があります(借地借家法26条1項)。そして、賃貸人の側からの更新拒絶が認められるためには、「正当の事由」(借地借家法28条)が必要となります。裁判実務において、この「正当の事由」が認められるハードルは高く、一定の金銭的補償(立退料)を補完的に支払う必要があるケースがほとんどです。立退料を払えば必ず「正当の事由」が認められるわけではないことには注意が必要です。
なお、賃借人が期間満了後も目的物である建物を継続使用する場合に、賃貸人が遅滞なく異議を述べなかった場合には、契約更新がされたものとみなされます(借地借家法26条2項)。
賃料・賃料の増額に関する規定
最後に、賃料についての規定です。
賃料の定めは、賃貸借契約の必須の要素ですので、必ず設けなければなりません。
また、賃貸人の立場からすれば、経済事情や公租公課の変動により、賃料収益が低下する可能性もあります。そうした場合に、一定の収益を確保するためにも、交渉等により、賃料を増額することができる旨を設けておく必要があるでしょう。
ひな形利用による企業経営のリスク
以上、建物賃貸借契約によく含まれる項目を紹介しました。
一般的なひな形(例:国交省の賃貸住宅標準契約書)には上記のような項目も含まれており、実際にひな形を用いることも一つの選択肢です。ただ、ひな形をそのまま用いることには一定のリスクが伴うこととなります。
下記で紹介するようなトラブルに事前に手当てできるように、ひな形を調整する必要があります。
賃料に関するトラブル
まずは、賃料に関するトラブルです。
初期の賃料に関してトラブルになることは比較的少ないでしょう。賃借人となる者が、契約交渉時に提示された賃料に納得がいかないのであれば、賃貸借契約を締結しないことになります。
一方、賃貸借契約締結後、当事者の一方が賃料の増減を求めた場合にはトラブルになることがあります。これは、賃貸借契約の契約年数が長期間に渡ることで、契約当初は相場に照らして適切な金額であった賃料が、時代の変化に伴い相場との乖離が生じてきてしまうことから発生します。
先述したように、一定の事情が生じた場合には、賃料の増額を申し入れることができる旨を契約書に明記し、交渉の余地を残しておくことが必要です。もちろん増額申し入れをしたとしても、直ちに賃料が増額されるわけではありません。賃借人が納得しないのであれば、調停や裁判を通じて解決せざるを得ないこととなります。
さらに、賃借人から、賃料の減額の申し入れを受けることもあります。これを防ごうと、一定期間賃料を減額しない旨の特約を締結することは借主の地位を弱いものにすることとなり、無効になる(借地借家法30条)ので注意が必要です。
立ち退きに関するトラブル
次に、立ち退きに関するトラブルです。
賃貸人が、賃貸人の都合で、賃貸借契約の解約を求める場合には、「正当の事由」が必要であり、「正当の事由」の補完のため、立退料を支払う必要があります。
解約の際に賃借人は立退料の支払いを免除する等の条項は、賃借人に不利な条項となるため、無効となります(借地借家法30条)。
そのため、賃貸人の立場から賃貸借契約を解約し、賃借人に対して確実に立ち退きを求めることは至難となります。
一定期間後に必ず立ち退いてもらいたい場合には、定期建物賃貸借契約(借地借家法38条)を締結するしかありません。
退去時のトラブル
最後に、退去時によくあるトラブルとして、原状回復に関するトラブルがあります。
賃借人は、賃貸借契約の終了時に、賃貸目的物に生じた損傷を、借りたときの状態(原状)に回復した状態で返還する義務を負っています(民法621条本文)。賃借人は、通常の使用収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化については、原状回復の義務を負いません(同条)。
このように賃借人の義務の範囲が抽象的であり、賃借人がどの範囲で原状回復義務を負うのかをめぐってトラブルとなるのです。
こうしたトラブルを防ぐために、契約書に一般的に想定できる事項については、家具ごとにどちらがどの範囲で修繕義務を負うのかを明記しておくことが必要となります。また、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(国土交通省)も参考になるでしょう。
なお、このガイドラインを超える範囲で賃借人に原状回復義務を定める規定は、賃借人が個人で、事業目的以外の目的で賃貸借契約を締結する場合、消費者契約法10条が適用されて無効になる可能性があることには注意が必要です。
契約書の作成・チェックに関する相談は弁護士へ
以上、建物賃貸借契約書に関する注意点を概括的に説明してまいりました。
建物賃貸借契約書を作成するに当たっては、民法、借地借家法、消費者契約法の理解はさることながら、建物は生活や業務の本拠であることから紛争も多く、蓄積した判例への理解も必要となります。
建物賃貸借契約書の作成・チェックに関してお困りごとがありましたら、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

 メール・Web
メール・Web