解雇や退職勧奨に踏み切る際の注意点!!問題社員(モンスター社員)への対応に強い弁護士が解説
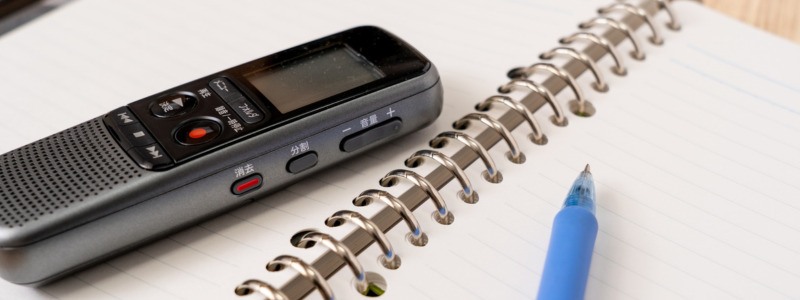
問題社員に対応する際の注意点や適切な対応方法を解説します。
放置した場合のリスクや解決のための手順、また異動や解雇を検討する際の重要な判断基準について具体的にお伝えします。最後には、弁護士に相談するメリットや支援内容についても解説します。
問題社員の例・特徴
規則や常識を守ることができない
就業規則を無視した行動や、基本的な職場の常識が通じない社員は、職場環境を乱す要因となります。
たとえば、無断欠勤や頻繁な遅刻が続き、業務スケジュールに支障をきたすケース。また、会社の明確な指示を無視して独自の判断で行動し、プロジェクト全体に悪影響を与えるケースなどです。これらの行動が頻繁に見られると、他の社員のモチベーションを低下させるだけでなく、職場全体の生産性に深刻な悪影響を及ぼします。
ハラスメントや職場いじめをしてしまう
セクハラやパワハラ、さらには職場内でのいじめ行為は、企業として見過ごすことのできない重大な問題です。
たとえば、上司の立場を利用して特定の部下に過度な業務負担を押し付けたり、部下の能力を公然と非難する行動。また、同僚間で特定の社員を仲間外れにしたり、悪口を言いふらすなどの行為が該当します。これらの行為は被害者のメンタルヘルスに大きなダメージを与えるだけでなく、職場全体の雰囲気を悪化させ、優秀な社員の離職を招くリスクがあります。迅速かつ厳正な対応が求められます。
メンタル不調や精神疾患がある
精神的な問題を抱えている社員については、業務への影響を考慮しつつ、適切なケアが必要です。
たとえば、頻繁な欠勤や業務中の注意力散漫、感情の起伏が激しいなどの兆候が見られる場合です。これらは個人の問題として片付けるのではなく、専門的な医療機関への相談を促したり、業務内容を軽減する措置を講じるなど、組織としてサポートを検討する必要があります。
ただし、業務に著しい支障をきたす場合には、配置転換や労務管理体制の見直しも視野に入れるべきです。
その他、会社経営に支障を及ぼす問題行動は多岐に渡ります
他の社員に対してストーカー行為を働いてしまう
職場内外で特定の社員を執拗に追い回す行為は、被害者の安全や精神的安定を脅かす重大な問題です。
たとえば、被害者の退勤時間を執拗に追跡したり、SNSを通じて過剰な接触を試みるなどの行為です。このようなケースでは、即座に調査を開始し、場合によっては警察や弁護士に相談することが必要です。
副業禁止であるにもかかわらず、副業をしている
就業規則で副業が禁止されているにもかかわらず、社員が規定を無視して副業を行う行為は、業務に支障をきたすだけでなく、情報漏洩や利益相反といったリスクを伴います。
たとえば、競合企業でのアルバイトや、自社の顧客名簿を利用した個人的なビジネスを行っている場合です。これらは重大な規律違反として速やかに対処する必要があります。
勧誘行為を行っている
職場内で特定の宗教や保険商品、投資案件などの勧誘行為を行う社員も問題です。
たとえば、休憩時間を利用して同僚に無理に勧誘したり、業務中に特定の勧誘資料を配布する行為が該当します。このような行為は、職場内の人間関係に悪影響を及ぼし、トラブルの原因となります。速やかに事実確認を行い、必要に応じて適切な指導や処分を講じることが重要です。
問題社員を放置・エスカレートさせてしまった時のリスク・問題
他の社員への負担が増える
問題社員を放置することで、周囲の社員がそのカバーに追われる事態が発生します。
たとえば、頻繁に遅刻や欠勤を繰り返す社員がいれば、その分の業務を他の社員が分担せざるを得なくなります。これにより、通常の業務に加えて追加の仕事が増えるため、時間外労働が増加し、疲労やストレスが蓄積します。
結果として、周囲の社員のモチベーションが低下し、職場全体の生産性が下がる事態が避けられません。また、不満を抱えた社員同士で摩擦が生じるなど、職場内の人間関係にも悪影響を及ぼします。
業務と無関係なトラブルの頻発
問題社員の行動によって、職場内外で不要なトラブルが頻発することも大きなリスクです。
たとえば、職場内で同僚とのトラブルを起こす社員がいる場合、人間関係の調整に管理職や人事担当者が時間を割かれることになります。また、問題社員が取引先との対応を誤ることで、取引関係に支障をきたしたり、企業の信用が損なわれたりする事態も想定されます。
さらに、業務に関係のない私的な行動が原因で、職場外でのトラブルが報道されるようなケースでは、会社全体のイメージダウンにもつながりかねません。これらは、本来業務に集中すべきリソースを無駄に消費してしまう結果を招きます。
いわゆる”まともな人から辞めていく”現象の発生
問題社員を放置した場合、最も深刻な影響は、有能な社員が職場を去ってしまうことです。
たとえば、問題社員の言動や行動が改善されない状況に対し、「自分の努力や真面目な姿勢が評価されない職場だ」と感じる社員が増えます。このような不満が蓄積されると、より良い環境を求めて転職を決意する社員が現れます。
その結果、企業にとって貴重な人材が流出し、優秀な社員を失った職場ではさらなる士気低下とパフォーマンス低下が起こります。また、離職が増えることで、採用コストや新人教育の負担が増加し、経営全体に悪影響を与える可能性があります。
異動や解雇などに踏み切る際の判断基準や流れについて
まずは事実確認や面談を行いましょう
問題行動が報告された場合、まずは事実確認を徹底することが必要です。
例えば、複数の社員から同じ問題行動が指摘されている場合には、記録や証拠を収集し、具体的な状況を把握します。そのうえで、当該社員に面談を行い、行動の理由や背景について丁寧にヒアリングを実施します。
この段階では、感情的な対立を避けるため、冷静かつ中立的な姿勢を心がけることが重要です。問題行動の背後に、職場環境や個人的な事情がある場合も考慮し、適切な対応を模索します。
書面による注意・指導により改善を求めましょう
問題行動が確認された場合、口頭での注意だけでなく、書面を活用して正式に指導を行いましょう。
例えば、「無断欠勤」や「業務命令違反」が発生した場合、これらを詳細に記載した書面を本人に手渡し、改善を求めます。この際、本人が内容を認識した証拠として署名を求めることも重要です。
書面による指導を行うことで、問題行動が繰り返された場合の証拠となり、後の法的手続きや解雇の正当性を裏付ける資料として活用できます。また、指導内容や改善目標を明確に伝えることで、社員が自身の問題を具体的に把握しやすくなります。
再三の指導を行っても改善しない場合は、さらなる措置を検討します
異動・配置転換
問題行動の影響が特定の部署や業務に限定されている場合は、別部署や異なる勤務地への異動を検討します。
例えば、特定の上司や同僚との相性が原因でトラブルが発生している場合、関係のない部署への配置転換を行うことで状況が改善することがあります。ただし、異動を命じる際には、雇用契約の内容(職種を限定する合意などがないか)の確認、業務内容や勤務地が著しく不利なものとならない配慮が必要です。
また、本人に異動の趣旨を十分に説明し、理解を得ることが円滑な異動につながります。
減給・降格処分
問題行動が改善されない場合には、給与や職位の変更を通じて対応することも選択肢の一つです。
例えば、部下へのハラスメントが繰り返される管理職に対しては、降格処分を行い、職場環境への悪影響を防ぐことが考えられます。この際、給与の減額については給与規程等に則り、適切な範囲で実施する必要があります。
処分を行う際には、本人に処分の理由を詳細に説明し、納得感を持たせる努力も重要です。
※懲戒処分としての減給や降格処分を行う場合には、就業規則の根拠規定、就業規則の周知状況、先例等を踏まえた相当性なども検討する必要があります。
出勤停止(謹慎)
問題行動が重大で即時の対応が必要な場合には、一定期間の出勤停止を命じることで、状況の再評価を行います。
例えば、業務中の重大なミスや、他の社員への深刻な迷惑行為が発生した場合、出勤停止を通じて本人に問題の重大性を認識させる機会を提供します。
出勤停止期間中には給与が支払われないことが一般的ですが、法的に無効とならないよう、期間を適切に設定する必要があります。一般的には、1~2週間程度の短期間で実施することが望ましいです。
※前提として就業規則の規定の存在や就業規則が周知されていることが必要となります。
異動や解雇等の処分は慎重に!実施する際の注意点
不適切な流れで処分を加えてしまうと訴訟のリスクがあります
処分を行う際に適切な手順を踏まない場合、不当解雇や違法な懲戒処分を理由に従業員から訴訟を起こされるリスクが高まります。
たとえば、問題行動に対する記録を十分に残さずに処分を実行した場合や、従業員の意見を聞かずに一方的な判断を下した場合、裁判で不利になる可能性があります。実際に、手続きが不適切であったために高額な賠償金を命じられた企業の事例もあります。これを避けるためには、すべての対応を記録に残し、段階的なアプローチを徹底することが重要です。
また、就業規則、先例等をチェックした上で、法的根拠があるか確認することも欠かせません。
異動や減給・降格を検討する際の注意点
複数回の指導を経たうえでの処分であるかどうか
問題行動が改善されない場合でも、いきなり厳しい処分を科すのではなく、段階を踏んだ対応が求められます。
例えば、最初に口頭での注意を行い、それでも改善が見られない場合には書面で指導を行うなど、段階的に記録を残すことが重要です。このプロセスを明確にしておくことで、処分が適正であることを後から証明しやすくなります。また、こうした段階的な対応を通じて、従業員に自己改善の機会を与えることが、企業としての誠実な姿勢を示すことにもつながります。
自主退職を強いる目的の処分であったかどうか
降格や減給が、事実上の退職強要とみなされる場合、違法性が問われる可能性があります。
たとえば、「業務が続けられない環境を意図的に作る」ような異動や降格は、退職強要として法的に無効と判断されることがあります。このようなリスクを避けるためには、処分が業務上の必要性に基づいていることを明確に説明し、本人の同意を得ることが不可欠です。
本人に丁寧な説明を行い、合意のうえ進めること
処分内容を伝える際には、納得感を持たせることが重要です。
例えば、処分の理由や背景を詳細に説明し、本人が状況を理解できるようにすることで、トラブルを未然に防ぐことができます。また、説明の際に第三者(人事部や専門家)を同席させることで、説明が公平かつ透明であることを確保することが望ましいです。
解雇を検討する際の注意点
再三の指導および処分を加えても改善がみられなかったどうか
解雇は従業員の雇用を奪う最も重い処分であるため、慎重な対応が求められます。
たとえば、問題行動について繰り返し指導を行ったが、改善が見られなかった場合や、職場環境に深刻な影響を与える行為が続いた場合にのみ、解雇が検討されます。この際、すべての指導記録を詳細に残し、指導が段階的かつ適切であったことを示すことが重要です。
解雇は客観的合理性と社会的相当性が必要になります。これは、解雇回避のための手段を尽くしたが、解雇せざるを得ないほど企業への害悪が大きいと言えるような状況でなければ、認められません。経営者がそのように考えたというだけでは足りず、過去の裁判例等に照らして考える必要があります。
適切な退職勧奨を行ったかどうか
解雇に至る前に、まずは退職勧奨という形で従業員に辞職を促すことが一般的です。
たとえば、「業務上の理由からこれ以上の雇用継続が難しい」と説明したうえで、退職に伴う補償や支援について提示することで、トラブルを避けることができます。ただし、強引な手法での退職勧奨は違法となるため、言葉遣いや対応には細心の注意を払う必要があります。
弁護士等の専門家に相談しているかどうか
解雇や処分を行う際には、弁護士などの専門家に相談することで法的リスクを最小限に抑えることができます。
専門家は、解雇が適正であるかを判断するだけでなく、文書の作成や交渉のサポートも行います。特に、従業員からの訴訟リスクがある場合には、事前に弁護士の意見を取り入れることで、企業側が不利にならないよう準備を進めることができます。
弁護士に問題社員対応を相談するべき理由
社員の問題性について客観的な判断が可能です
問題社員に関する対応で一番難しいのは、主観的な感情や職場内の偏見が入り込みやすい点です。
例えば、同僚や上司から「仕事に真剣ではない」とか「遅刻が多い」といった声が上がっても、それが具体的にどのような規則違反に該当するのか、法律的にどの程度問題があるのかを判断するのは容易ではありません。弁護士は、法律や就業規則に基づいて問題社員の行動を分析し、その問題性を客観的に評価することが可能です。
また、「職場でのトラブルがエスカレートしても、実際には懲戒処分や解雇には至らないケース」もあります。弁護士に相談することで、どの行動が法律上の懲戒事由に該当するかを具体的に把握し、法的に有効な対処を進めることができます。
指導や退職勧奨の進め方を相談できる
問題社員への指導や退職勧奨は、適切な進め方をしないとトラブルに発展するリスクがあります。
例えば、「業務に支障をきたしているので退職してほしい」と口頭で伝えるだけでは、従業員から「退職強要を受けた」と主張されることがあります。また、懲戒処分を行う際に手続きが不適切だと、処分の正当性が裁判で否定される可能性もあります。
弁護士は、書面での指導や懲戒手続きの進め方、退職勧奨時の注意点などを具体的にアドバイスしてくれます。たとえば、「問題行動を記録し、本人に書面で改善指導を通知する方法」や、「退職勧奨の際に提示する条件をどう設定すればトラブルを避けられるか」といった実務的な支援を受けることが可能です。
あとから解雇無効などを主張されても対処可能です
解雇は最も重い処分であるため、従業員が後から「解雇無効」を主張して争うケースも珍しくありません。
例えば、解雇後に従業員から「事実無根の理由で解雇された」や「適切な改善機会が与えられなかった」といった訴えがあった場合、企業が不利な立場に立たされる可能性があります。
弁護士は、解雇に至るまでのプロセスで必要な証拠収集や記録の作成を支援します。たとえば、口頭注意、書面での警告、改善機会の提供といった段階的な対応を文書化し、法的に正当性を主張できる形で準備を整えます。また、解雇理由やその手続きが労働基準法などの法律に沿っているかを確認し、不備があれば事前に改善案を提示してくれます。
さらに、万が一裁判や労働審判に発展した場合でも、弁護士が対応を一任されるため、企業の負担を軽減しながら適切な結果を目指すことができます。
問題社員トラブルは西村綜合法律事務所へご相談下さい
岡山密着型の西村綜合法律事務所では、初回相談無料、オンライン面談も可能です。経験豊富な弁護士が迅速かつ的確に対応し、問題社員に関するトラブル解決をサポートします。まずはお気軽にご相談ください。
「解雇や退職勧奨に踏み切る際の注意点!!問題社員(モンスター社員)への対応に強い弁護士が解説」の関連記事はこちら
- 諭旨解雇をするには?懲戒解雇との違いや法的な注意点を弁護士が解説
- 解雇や退職勧奨に踏み切る際の注意点!!問題社員(モンスター社員)への対応に強い弁護士が解説
- 異動や配置転換を拒否する社員への会社としての対応を解説
- 協調性のない社員やお局さん型の従業員を解雇するには?問題社員対応に強い弁護士が解説
- 解雇を見据えた問題社員との付き合い方・指導方法を徹底解説
- 能力の低い社員を配置転換したい!有効なケース、無効になるケースを徹底解説
- ローパフォーマー社員って?能力不足の部下・職員に会社として対処するには
- これって問題社員?辞めさせることはできる?パターン別の対処法を徹底解説
- 懲戒処分の要件・種類を弁護士が解説!法的に有効な処分を科すポイントって?
- 問題社員を辞めさせることって可能?モンスター人材への対処方法を企業側弁護士が解説
- モンスター社員を辞めさせる方法って?退職勧奨の流れと注意点を労働弁護士が徹底解説
- 自主退職させるための退職勧奨のポイント!解雇との違い、違法になるやり方を弁護士が解説

 メール・Web
メール・Web








