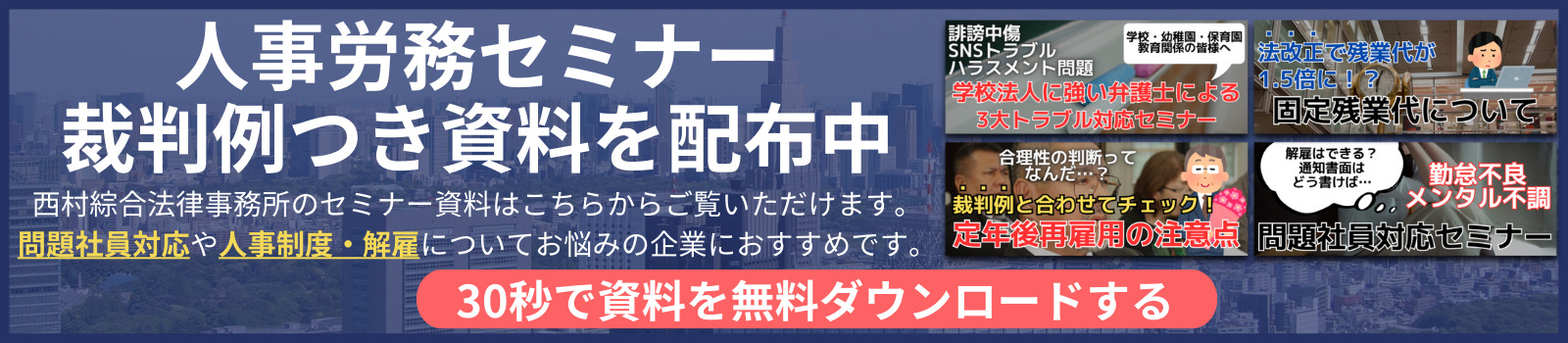モンスターペアレントに法的措置は可能?保護者への対応や学校運営のポイントを解説
学校法人と保護者の間で問題になっている「モンスターペアレント」とは何でしょうか?
今回は学校法人の経営者や人事担当者向けのコラムといたしまして、モンスターペアレントによる実際のトラブル事例をもとに解説し、裁判例をご紹介いたします。
モンスターペアレントとは?
モンスターペアレントの定義・意味
モンスターペアレントとは、教育現場に対し、無理な要求をしたり、理不尽な対応を求める保護者のことを指す和製英語です。略してモンペ、モンペアと呼ばれることもあります。
元々はこのような言葉はなかったのですが、元小学校教諭の方が上記のような保護者のことをモンスターペアレントと命名したことで、現在広く使用されるようになりました。今から10年以上も前ですが、「モンスターペアレント」というテレビドラマも放映されています。
モンスターペアレントと呼ばれる保護者の例としては、以下のようなものがあります。
- 学校に長時間かつ一方的に電話で話を続ける
- 担任の教師やクラス替えを求める
- 学校に原因がない子どもの怪我について、学校に責任を取るよう求める
- 子どもの髪形や服装について非常識な格好をさせる
- 子どものタレント活動やモデル活動のために理不尽な対応を求める
- 子どもを部活動のレギュラーにしたり、演劇の主役にするように求める
- 子どもが朝起きられないので起こしに来るよう学校に求める
- 金銭的に余裕があるのに給食費を払わない
また、最近では、文部科学省、教育委員会、都道府県・市町村など、教育現場を管理・統括する関係機関に対してクレームを入れる保護者の方が散見されるようになっており、このようなモンスターペアレントに対して適切に対応することが教育現場の重要な課題になっています。
理不尽な主張を行う保護者の心理
保護者からの無理な要求や理不尽な要求に対する対応を検討するには、保護者がなぜそのような行動をとってしまうのかを考える必要があります。
保護者も十人十色であり、様々な状況が存在するところですが、保護者が上記のような行動をとってしまう心理については、多くの場合、以下のようなものが存在するといわれています。
子離れができずに介入してしまう
保護者が上記のような問題のある行動をとってしまう原因の一つに、子離れができていないということを指摘することができます。
子育ての過程であまり他人に頼ることができなかったり、悩みを相談できる友人がいない場合など、親が子どもに依存してしまうといったことが起こり得ますが、このような場合、保護者は、ついつい子どものことが過剰に心配になり、教育現場にも過度な介入をしてしまうということがあります。
子どもの言うことが全て正解だと感じてしまう
例えば、子ども同士でトラブルが生じた際に、双方の言い分が異なることはよくあることです。しかし、そのような場合に何ら根拠がなくても「うちの子どもの言うことが正しい」「相手の子どもが嘘をついている」と主張する保護者がいるところです。
保護者がこのような問題のある行動をとってしまうのは、保護者が自分の子どもの言うことが全て正解だと感じてしまうということが挙げられます。
学校との協力への意識がない
モンスターペアレントと呼ばれる保護者には、家庭教育を重視するあまりに学校への協力への意識が希薄であるという特徴も指摘できるところです。
学校が個々の家庭の家庭教育を尊重する必要はありますが、そうであるからといって、保護者が学校教育を軽視していいということにはなりません。しかし、あまりこのことを十分に理解できていない保護者が存在することも事実です。
モンスターペアレントについて弁護士に相談するメリット
保護者の性質や状況に応じたアドバイスを得られる
弁護士に相談すると、モンスターペアレントとの対話の際の具体的な表現や、適切な対応の仕方などを知ることができます。
「こういった対応はエスカレートさせる可能性がある」「このような表現を使えば相手を落ち着かせやすい」などといった具体的なアドバイスをすることが可能です。
法的なルールに従った対応ができる
モンスターペアレントとの対応で不適切な方法を取ると、学校が逆に法律違反をしてしまう危険性も考えられます。弁護士は、それを防ぐために「個人情報の管理方法」や「生徒の権利保護」など、学校側が遵守すべき法的な規則について具体的なアドバイスを提供します。
学校そのものだけではなくブランド・信頼を守る
予期せぬ法的問題・モンスターペアレントとのトラブルに直面した際、弁護士は学校の利益を最優先に解決策を提案します。例えば、法的な手続きが必要な場合や、メディアからの疑問に対する適切な回答方法など、学校のブランド・信頼性 を守るための助言を提供します。
実際に起きた学校法人と保護者とのトラブル・裁判例
保護者との間に問題が生じた場合でも、基本的には対話や協議を通じて意思疎通を図り解決策を探っていくことになります。しかし、保護者の問題行動があまりにもエスカレートしてしまった場合、学校は法的手段をとることも検討しなくてはなりません。学校が保護者を提訴するということはその保護者との対立関係が決定的になるため、裁判例の数は多くありませんが、以下の2つの裁判例をご紹介します。
さいたま地熊谷支判平成25年2月28日
この事案は、ある保護者が、公立学校の教師に関し、子どものトラブルへの対応や、テストにおける採点について不信感を抱くようになったことから、
①教育委員会に対して相談を持ちかけたり、
②学校との連絡帳に、教師を非難する長文の文章を書いて提出し、
③さらには教師が子どもに暴行をしたとして警察署に被害相談に赴いたりしました。
そこで教師の方が保護者に対して、名誉毀損を理由として損害賠償請求を行ったという事件です。
この事件の判決では、結論として原告である教師の方の請求は認められませんでしたが、新聞や週刊誌が相次いでこの裁判を報道し話題となりました。
横浜地判平成26年10月17日
この事案は、ある保護者が、公立学校の教師の指導方針に不満を抱いたことから、
①教育委員会に対して、担任の交代またはクラス替えを要求し、その際に教師について「二重人格である」といった発言を行い、
②また、担任の交代またはクラス替えの要求が断られたことから、自ら学校で自分の子どもの机を隣のクラスに移動させようとした際に、これを制止しようとした教師に対して暴行を行いました。そこで教師の方が保護者に対して、教育委員会での発言及び教室での暴行が違法であるとして、損害賠償請求を行ったという事件です。
この事件では、①教育委員会での発言に関して名誉感情の侵害を認め、②また、教室での暴行についても責任を認め、教師の方の請求を一部認容する判決が出されています。
学校法人が保護者とのトラブルをなくすためにできる対策
学校法人が保護者とのトラブルをなくすためにできる対策としては様々なものが考えられますが、
以下のものが有効です。
不信感のない環境づくり
学校において、いじめや暴力行為といった問題行動が発生したにもかかわらず、学校側が適切な対応をとっていない場合、保護者の学校に対する信頼が失墜し、学校を信用してくれないという状況が生じてしまう可能性があります。
そうなれば、学校に対する要求、要望の程度も必然的に強くなってしまいますし、保護者も権利の主張を行うことが当然であると考えてしまうことになります。
そのため、いじめや暴力行為といった問題が生じないように学校を管理・運営し、「この学校であれば子どもを預けても大丈夫だ」と保護者からの信頼を勝ち取ることが、モンスターペレント対策としての第一歩になります。
家庭教育の尊重
保護者とのトラブルをなくすためには家庭教育を学校側もしっかりと尊重するということもポイントになります。
家庭教育の内容や目的、方針は家庭ごとに異なりますが、これを尊重して保護者に接することで、保護者が学校を尊重することに繋げることが可能となります。
モンスターペアレント等の保護者対応でお困りの際は弁護士に相談を
モンスターペアレントは、対応が難しく、適切な法的対処が必要な場合があります。是非一度法律の専門家である弁護士にご相談下さい。
「モンスターペアレントに法的措置は可能?保護者への対応や学校運営のポイントを解説」の関連記事はこちら
- いじめが発覚した際の学校側の対応を弁護士が解説
- 学校法人のM&Aのメリットやスキーム、流れを弁護士が解説
- 学校の広告や宣伝に関する不当表示や不正競争行為について
- 学校側で教員の内定取り消しができるケースって?弁護士が解説
- 教員からの残業代請求ってあり!?学校の残業代について弁護士が解説
- 私生活上の非違行為で教員の懲戒処分ってできる?弁護士が解説
- 学校・教育機関への誹謗中傷に強い弁護士をお探しの方へ
- 問題教員・モンスターティーチャーへの対応に強い弁護士をお探しの方へ
- 学校経営における教員の鬱・適応障害などへの対応|学校側の弁護士が解説
- 学校の広告にはどんな規制がある?誇大広告や罰則について学校法人に強い弁護士が解説
- 【学校側の弁護士】学校事故の保護者・生徒の対応に強い弁護士をお探しの方へ
- 授業で許される著作権って?学校法人に強い弁護士が徹底解説
- 共通テスト流出・・・学校法人における問題漏洩について弁護士が解説
- 学校側の弁護士が解説 – 学生側から留年・退学・除籍等に不服申し立てを受けてしまったら
- 保護者からのハラスメントに限界!クレーマーやモンスターペアレントに対して学校としてできること
- 学校法人の理事の選任・変更について学校側弁護士が解説
- 学校側弁護士がアカハラの防止・措置について解説 – 大学などにおけるアカデミックハラスメント
- 学校と個人情報保護法の関わりを弁護士が解説 – どこまでの提供ならOK?
- 授業や資料における著作権の注意点!学校側弁護士が解説
- 教員の定年と再雇用制度について学校法人に強い弁護士が解説
- 教員同士のパワハラや学校の長時間労働を労務問題に強い弁護士が解説
- 学校法人における就業規則の重要性について弁護士が解説
- モンスターペアレントからの誹謗中傷・悪口にどう対応すればいい?学校・幼稚園・保育園側の弁護士が解説
- 学校の労務トラブルや教職員のパワハラについて弁護士が解説
- 休職を繰り返す教員への対応 – 学校運営におけるメンタルヘルスを弁護士が解説
- 塾・予備校の弁護士が送迎トラブルや騒音問題への対処を解説
- 保護者トラブルって録音してOK?学校や保育園・幼稚園側の弁護士がモンスターペアレント対応について解説
- 生徒への暴言や行きすぎた指導をする教師に対して学校側ができること
- モンスターペアレントに法的措置は可能?保護者への対応や学校運営のポイントを解説
- 学校事故の事例・対応法って?保護者対応などについても弁護士が解説
- 学校側からモンスターペアレントに法的措置は可能?モンペの対応を学校・幼稚園・保育園に強い弁護士が解説
- 給食費を払わない家庭からの徴収について学校法人に強い弁護士が解説
- 給食費を払わない親への請求方法!顧問弁護士なら支払督促が可能です
- 学校運営で知っておくべき基準!体罰はどこから?教師への措置について弁護士が解説
- 学習塾・予備校のための弁護士 – 教育支援業の法律相談は西村綜合法律事務所まで

 メール・Web
メール・Web