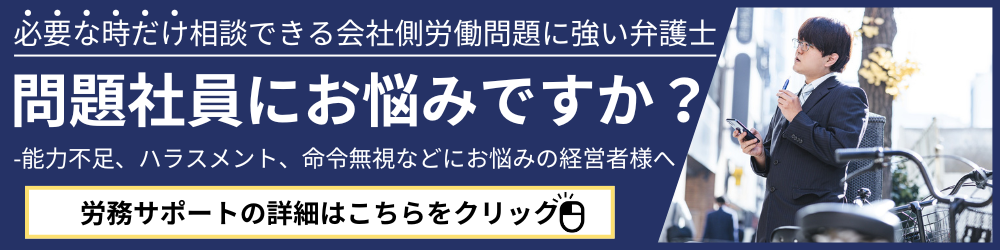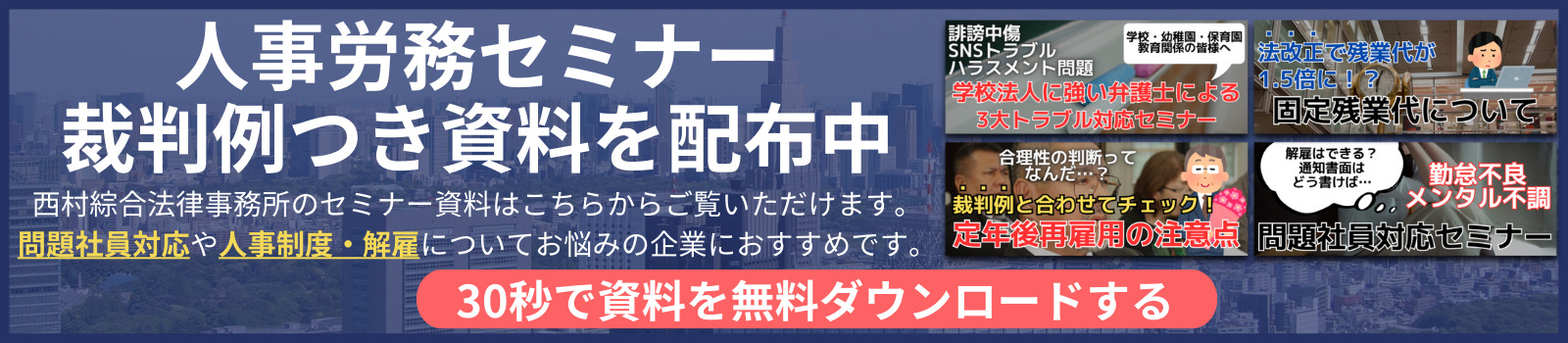休職を繰り返す教員への対応 – 学校運営におけるメンタルヘルスを弁護士が解説

学校法人においてメンタルヘルスを抱える教職員は決して少なくありません。
そのため、学校法人はメンタルヘルスを抱えた教職員をどのように扱うべきかについて検討しなければならない場面にしばしば遭遇します。
そこで、以下では
- 学校法人におけるメンタルヘルスの現状
- 学校法人におけるメンタルヘルスを抱える教職員への対応方法
などについてご説明させて頂きます。
学校・幼稚園などの従業員のメンタル不調に強い弁護士をお探しの方はこちらのページもご覧ください。
教員の休職規定は充分に整備しておきましょう
まずはじめに、学校法人における教職員のメンタルヘルスの現状についてご説明させて頂きます。
厚生労働省の調査によると、令和2年度の教育職員の精神疾患による病気休職者数は5180人となっています。教育職員の精神疾患による病気休職者数は、年々5000人前後で推移しており、高止まりといえます。
そのため、メンタルヘルスを抱えてしまった教職員について、学校法人はどのように対応すべきかが重要となります。そこで、以下では、対応方法についてご説明させて頂きます。
就業規則内での休職・復職に関する規程の整備
まずは、就業規則でメンタルヘルスに備えて休職・復職に関する規程を整備することが重要です。
- 不完全労務提供を休職事由とする
- 「治癒」の定義を明確にする
- 休職期間に法人の裁量を入れる
- 休職期間の通算規定を設ける
- 休職期間中の取り扱いの明確化
- 休職期間中の教職員の治療経過の把握
- 復職手続きで医師の意見を聴取できる規定をおく
- 復職取消の規定を設ける
- 休職期間満了時の手続きは自然退職とする
等の確認事項が主なポイントとなります。
治癒の定義づけを行いましょう
メンタルヘルスの場合は、連続的な欠勤と出勤と欠勤を繰り返すことや出勤しても実際には仕事ができないケースが存在します。
そのため、「私傷病による欠勤が1ヶ月を経過したとき」と休職事由を定めても休職命令できない場合があります。したがって、「業務外の傷病により完全な労務提供が困難で、その回復に相当の時間を要すると認められるとき」を休職事由として定めることが考えられます。
メンタルヘルスを抱えていた教職員が復帰しようとする場合、主治医の診断書に「短時間労働であれば就労可能」などと記載されるケースがあります。
しかし、このような労務提供は学校の業務をこなすのに不十分であると思います。しかし、「治癒」すなわち復職について明確な基準がないと、裁判で争いになったときに、このような診断書を裁判所が鵜呑みにしてしまうリスクがあります。復職の基準における「治癒」は学校法人側が決めるべきものです。そこで、就業規則上、法人が求める復職基準の「治癒」の定義を定めることが重要です。
メンタルヘルスは様々な状況が考えられるため、法人が与えるべき休職期間が異なるのが当然です。
そこで、休職期間について一定の範囲で法人の裁量を確保するために、「休職事由を考慮の上」「次の期間を限度として法人が定める」とすることが重要です。
休職期間の規定を見直しましょう
メンタルヘルスの場合、休職と復職を繰り返すことがあります。
しかし、学校法人として人員計画を立てることができなくなります。また、メンタルヘルスは類似症状でありながら、医師により病名が異なることがあります。そのため、類似の理由を含めて休職期間を通算する規定を定めるべきです。
休職期間中は教職員による労務提供がないため、法人としては給与を支払う必要はありません。そのため、休職期間中は給与を支給しないことを就業規則に明示しておくことが重要です。
休職期間中の教職員の治療経過を把握することで、復職の見込みを法人は把握することができます。そこで、休職期間中の職員に定期的に法人が認める又は指定する医師の診断を受けさせて、少なくとも月1回法人に報告させるように義務付けることを就業規則に明記することが重要です。
メンタルヘルスに陥った教職員の主治医は、医学的に回復したことが判断できても、教職員としての職務が行えるかの判断はできません。また、主治医は患者である教職員の立場を尊重して教職員の希望に偏った判断を下すことがあります。そのため、主治医と面談して教職員の業務内容を説明し、本当に教職員としての職務を行えるほどに回復しているか意見を聞くことが大切です。さらに、産業医や法人指定の意見も聴けるようにする必要があります。そこで、復職手続きにおいては、教職員に対して、医師の治癒証明の提出の要求と診断書を発行した主治医に対する面談の要求ができる規定をおくべきです。
メンタルヘルスは、休職と復職を繰り返すケースがあるので、復職取消の規定も入れるべきです。休職期間満了時に「解雇」とすると教職員との無用のトラブルが発生します。そのため、法人の意思表示が必要なく、解雇予告手当手続きを必要としない自然退職と規定すべきです。
このようにメンタルヘルスに備えて就業規則を整備するためには、様々な事柄を想定しなければなりません。
メンタル不調を理由とした解雇の可否について
メンタル不調・精神疾患で休職中の教員を解雇することは困難です
そもそも、メンタルヘルスが業務に起因する場合は、労働基準法19条1項本文によって解雇が禁止されています。メンタルヘルスが、業務に起因するかどうかについては、厚生労働省が公表している心理的負荷による精神障害の認定基準が参考になります。同基準は、令和2年5月に改正され、同年6月から改正後の基準に基づいて判断することを要求しています。改正の際に、パワーハラスメントについて同基準に追加されていることに注意が必要です。
法人が教職員のメンタルヘルスについて業務に起因するかどうか判断できない場合は、労働基準監督署の判断に委ねるしかないです。
ただし、労働基準監督署に対して法人の認識する事実関係や考え方は積極的に伝えておくべきです。そこで、法人としては、労災申請の際に、文書を作成し、申請書と一緒に提出すべきです。
メンタル不調を抱える従業員の解雇については簡単なものではありません。精神的に問題を抱えている従業員の休職・解雇についてはこちらのページも併せてご覧ください。
休職期間の満了時に自然退職(解雇)とする規定が必要です
休職期間満了時に治癒しなかった教員を自然退職とするためには、前述の通り就業規則にその旨を明確に記載しておく必要があります。こういった規定を事前に設けておくことで、企業は労務管理の明確な基準・裏付けを持って対応できるようになります。
しかしこの規定を運用する際には、「規定ですから」と押し付けるだけではなく、従業員に十分な説明を行い、納得を得る努力を怠らないようにしましょう。
教員がメンタル不調・精神疾患に陥ってしまう要因と対策
教員のメンタル不調・精神疾患の代表的な要因
なぜ、教職員がメンタルヘルスを抱えてしまうのかについて以下ではご説明させて頂きます。
長時間労働
まず、教職員の長時間労働がメンタルヘルスの要因となっていると考えられます。日本教職員組合による令和3年の調査によれば教職員の1週間の労働時間の平均は62時間56分であり、単純計算すると月の平均残業時間は90時間を上回ることになります。厚生労働省の令和4年4月分の調査によれば全体的な職種の残業時間の平均は、約10.7時間となっています。そのため、現在の教職員は一般的な社会人と比較しても長時間労働になってしまっていることが分かります。また、過労死ラインとされている月の残業時間は80時間とされています。そのため、教職員の残業時間は、精神的にも肉体的にもかなり負荷がかかっていることが分かります。
上司等からのハラスメント
教職員同士は、コミュニケーションを密に取りながら生徒指導にあたります。そのため、上司等の職位が高い教職員が自分より職位の低い教職員にパワーハラスメントを行なっている事案は少なくありません。実際、全日本教職員組合青年部が実施した調査によれば教職員全体のおよそ32パーセントの教職員がパワーハラスメントの被害に遭っています。具体例としては、来年度の希望(担当学年)を書いたら、「他の若い職員は一任と書いたのに、いい加減にしろ」と叱責された、自分が参加しない飲み会の送迎をさせられるなどが同調査で判明しました。また、同調査によれば教職員全体のおよそ8パーセントがセクシャルハラスメントの被害に遭っています。具体例としては、「うちは部活の学校だから、女はいらない」と管理職から言われる、ハグしてほしいと不必要な身体接触を求められるなどが同調査で判明しました。日常的に教職員同士は関わることが多いため、ハラスメントについて言い出しづらい実態も存在していると思われます。その結果、継続的なハラスメントを受け続けることによって精神的に疲弊してしまうことがあります。
保護者・PTA等の対応
教職員は、保護者・PTA等に対する対応もしなければなりません。保護者等の要求の中には、学校とのトラブルについて書面での回答を求めたり、面談での録音を求められたり、電話をかけてきてなかなか電話を切らなかったり、面談を終わらせないようにしたりする人がいます。学校として、学校の立場や見解を伝える際に、このような保護者等の要望通りに対応したり、対応し続ければならなかったりする義務は存在しません。しかし、教職員は、保護者等との関係悪化を避けるために、過度な対応をしてしまうことがしばしばあります。その結果、教職員が保護者に対する対応に疲れて精神的に疲弊してしまうことがあります。
メンタル不調・精神疾患を発生させないために実施すべきこと
先に述べたことを踏まえると、メンタルヘルスを出さないことが重要となります。そこで、メンタル不調者を出さないために実施すべきことについて説明させて頂きます。
労働環境の整備・改善に向けた取り組み
教職員の労働条件や職場環境をチェックし、管理指導者が、改善対策を取ることが大事です。特に、長時間労働については、増員などを含めた人員計画の策定も視野に入れた方が良いでしょう。
精神的課題に関する相談体制の構築
メンタルヘルスは長期間の負荷によって症状が現れることがあるので、定期的なチェックを行う方法が効果的です。また、メンタルヘルス対策は、教職員の心という最もプライベートな部分に踏み込む行為です。そのため、その情報が確実に保護されるという保証が必要です。このような観点を踏まえたメンタルヘルスに関する相談体制の構築が必要です。
他職員等とのコミュニケーション状況の確認
感情のコントロールができなくなるのはメンタルヘルスの特徴の一つです。そのため、他職員等とのコミュニケーションの中で、些細なことで急に怒り出すようになったり、突然泣き出したり、何もせずにぼうっとしている時間が多くなったり、昼食や飲み会などの誘いを断るようになるなどの現象が目につくようになっていないかを把握することも大事です。このように精神的に不調となり始めた教職員の変化に気づけるような体制を整えることも重要です。
復職後の管理も重要です
休職後の社員が復職した際、適切な管理体制を整えることは、企業にとっても社員にとっても重要な課題と言えます。復職後のフォローが不十分だと、メンタル不調の再発やさらなる休職といったリスクが高まり、結果的に職場全体に悪影響を及ぼす可能性があります。
再び戦力となる可能性も高いので適切なサポートが必要です
休職を経た社員でも、適切な支援と配慮があれば、再び重要な戦力として職場で活躍できる可能性も高いです。
例えば、休職の原因が職場の人間関係だった場合、配置転換や業務内容の調整を行うことで、社員の意欲や能力を最大限に引き出せる可能性があります。
また、復職をサポートすることは、他の社員に対しても「この会社は従業員を大切にする企業だ」というメッセージを送ることになり、職場全体の士気向上につながります。
リハビリ勤務・時短勤務などを検討しましょう
復職直後から従来どおりの業務量を課すと、社員に過度な負担がかかり、再度の休職や離職につながるリスクがあります。
そのため、復職後の数週間から数か月間はリハビリ勤務や時短勤務といった段階的な復職プログラムを導入するのが効果的です。例えば、最初の1か月間は午前中のみ勤務し、次の1か月でフルタイムに戻すといった方法が考えられます。これにより、社員の健康状態に応じたスムーズな復職が可能になります。
定期的にミーティングや状況確認を行いましょう
復職後も、社員の状態や業務適応状況を定期的に確認することが重要です。
例えば、直属の上司が毎週10分程度のミーティングを行い、業務量や健康状態についてヒアリングを行う等のサポートが挙げられます。
また、復職後のやり取りや調整内容は、必ず記録に残しておくことが重要です。メールや書面、さらには社内ツールでの議事録として記録することで、後々のトラブルを防ぐ証拠となります。特に、労働紛争が発生した際には、これらの記録が企業を守るための重要な資料となります。
学校法人におけるメンタル不調者対応は弁護士にご相談ください
学校法人においてメンタルヘルスを抱えた教職員の発生防止や発生時の対応においては、法的知識を前提とした規則づくりが重要となります。そのため、学校法人におけるメンタルヘルスの対応については、是非一度、法律の専門家である弁護士にご相談下さい。
「休職を繰り返す教員への対応 – 学校運営におけるメンタルヘルスを弁護士が解説」の関連記事はこちら
- いじめが発覚した際の学校側の対応を弁護士が解説
- 学校法人のM&Aのメリットやスキーム、流れを弁護士が解説
- 学校の広告や宣伝に関する不当表示や不正競争行為について
- 学校側で教員の内定取り消しができるケースって?弁護士が解説
- 教員からの残業代請求ってあり!?学校の残業代について弁護士が解説
- 私生活上の非違行為で教員の懲戒処分ってできる?弁護士が解説
- 学校・教育機関への誹謗中傷に強い弁護士をお探しの方へ
- 問題教員・モンスターティーチャーへの対応に強い弁護士をお探しの方へ
- 学校経営における教員の鬱・適応障害などへの対応|学校側の弁護士が解説
- 学校の広告にはどんな規制がある?誇大広告や罰則について学校法人に強い弁護士が解説
- 【学校側の弁護士】学校事故の保護者・生徒の対応に強い弁護士をお探しの方へ
- 授業で許される著作権って?学校法人に強い弁護士が徹底解説
- 共通テスト流出・・・学校法人における問題漏洩について弁護士が解説
- 学校側の弁護士が解説 – 学生側から留年・退学・除籍等に不服申し立てを受けてしまったら
- 保護者からのハラスメントに限界!クレーマーやモンスターペアレントに対して学校としてできること
- 学校法人の理事の選任・変更について学校側弁護士が解説
- 学校側弁護士がアカハラの防止・措置について解説 – 大学などにおけるアカデミックハラスメント
- 学校と個人情報保護法の関わりを弁護士が解説 – どこまでの提供ならOK?
- 授業や資料における著作権の注意点!学校側弁護士が解説
- 教員の定年と再雇用制度について学校法人に強い弁護士が解説
- 教員同士のパワハラや学校の長時間労働を労務問題に強い弁護士が解説
- 学校法人における就業規則の重要性について弁護士が解説
- モンスターペアレントからの誹謗中傷・悪口にどう対応すればいい?学校・幼稚園・保育園側の弁護士が解説
- 学校の労務トラブルや教職員のパワハラについて弁護士が解説
- 休職を繰り返す教員への対応 – 学校運営におけるメンタルヘルスを弁護士が解説
- 塾・予備校の弁護士が送迎トラブルや騒音問題への対処を解説
- 保護者トラブルって録音してOK?学校や保育園・幼稚園側の弁護士がモンスターペアレント対応について解説
- 生徒への暴言や行きすぎた指導をする教師に対して学校側ができること
- モンスターペアレントに法的措置は可能?保護者への対応や学校運営のポイントを解説
- 学校事故の事例・対応法って?保護者対応などについても弁護士が解説
- 学校側からモンスターペアレントに法的措置は可能?モンペの対応を学校・幼稚園・保育園に強い弁護士が解説
- 給食費を払わない家庭からの徴収について学校法人に強い弁護士が解説
- 給食費を払わない親への請求方法!顧問弁護士なら支払督促が可能です
- 学校運営で知っておくべき基準!体罰はどこから?教師への措置について弁護士が解説
- 学習塾・予備校のための弁護士 – 教育支援業の法律相談は西村綜合法律事務所まで

 メール・Web
メール・Web