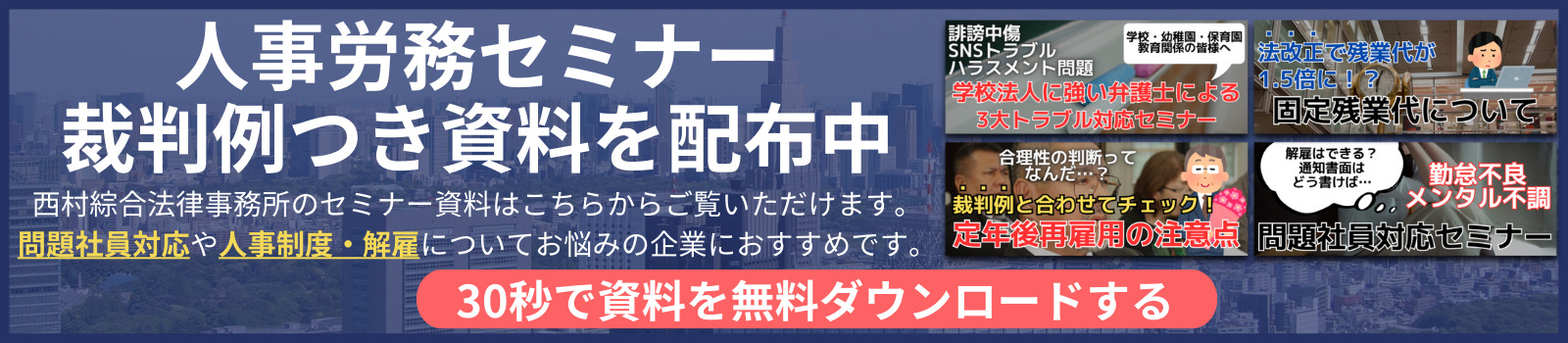授業や資料における著作権の注意点!学校側弁護士が解説
学校では、様々な文献や資料を利用することが多いと思われますが、このような文献や資料の使用にあたっては、他者の著作権に配慮する必要があり、著作権を侵害しないように対応する必要があります。
インターネット上のイラストを無断で学校だよりに使用し、他者の著作権を侵害したとして賠償金を支払ったというような事例が時々報道さるところです。
このページでは学校法人で注意すべき著作権について弁護士が解説します。
著作権とは?
著作権とは、美術、音楽、写真などの作品を創作した者が取得する権利のことです。著作権の内容を端的に説明すると、著作物の創作者が、自己の作品をどのように使用するかを決定する権利ということができます。
著作権が認められるのは美術、音楽、写真などの作品と説明しましたが、これらには、小説、論文、講演、音楽、絵画、イラスト、アニメ、漫画、映画、写真といった作品も含まれ、全て著作物に該当することになります。
著作権侵害になるケース
学校法人の運営では、著作権を侵害しないように気を付けなければならないところですが、次のような場合に著作権侵害となると考えられています。
著作物を無断使用する
まず、小説、論文、講演、音楽、絵画、イラスト、アニメ、漫画、映画、写真といった著作物をそのままの形で、無断使用する場合、著作権侵害となります。
上記のとおり、インターネット上のイラストを無断使用したことが著作権違反であるとして、学校が賠償金を支払ったという事例が時々報道されますが、このような事例がまさに無断使用に当たるものです。
ここでいう著作権の「使用」には、著作物を複製する行為、著作物をインターネット上に公開する行為などが含まれていますが、場合によっては、著作権法の規定により、そのような行為を行うことも許容される場合があります。
著作権が保護期間内である
著作権には保護期間が設定されており、この保護期間がまだ切れていない著作物を無断使用すると著作権侵害となります。
著作権の保護期間は、映画を除き、著作者が死亡してから70年が原則とされています(著作権法51条2項)。
そして、この70年という期間は、著作者が死亡してからスタートしますので、著作者が存命の場合は、その期間も当然保護期間に含まれることになります。
仮に、著作者が、著作物を創作し30年存命したとすれば、そこから死後70年は著作権の効力が生じますので、結局、著作権の効力が消滅するのは、著作物の創作から100年が経過したときということになります。
このように、著作権の保護期間は極めて長期に及びます。そのため、基本的には、他者の著作物の保護期間が切れているというとはないと認識しておくべきでしょう。
類似性が認められる
上記のとおり、著作物をそっくりそのまま使用する場合は著作権侵害になるところですが、著作物をそのままを使用した場合だけではなく、著作物に類似した表現活動を行った場合も、著作権侵害となると考えられています。
そのため、他人の著作物である小説、論文、講演、音楽、絵画、イラスト、アニメ、漫画、映画、写真に類似した作品を用いた場合も、著作権侵害が成立する可能性があります。
著作物との類似性については、著作物における表現形式上の本質的な特徴を直接感得できるかによるとされていますが(最判昭和55年3月28日、最判平成13年6月28)、微妙な場合が多く、判断に苦慮することも少ないところです。
著作物を利用する権利を有していない
著作権を無断使用すると著作権侵害となる一方、当然ですが、著作権者の許諾を得ている場合は、著作権侵害とはなりません。
著作権者からの許諾に基づいて著作物を利用する場合は、契約書や合意書を作成し、許諾の存在を証拠化しておきましょう。
著作権法違反にならないケース
保護期間内の著作物を無断使用する場合、著作権侵害となるのが原則ですが、著作権法で認められている一定の場合は、例外的に著作物の使用が認められ、著作権違反にならないとされています。学校法人では、特に著作権法35条及び36条により、著作物の利用が認められることがあります。
学校の授業で利用する
著作権法35条1項において、非営利の学校等において授業で使用する場合、必要な限度において、教師や生徒児童は公表された著作物を使用することができるとされています。
そのため、教員が授業で使用するために小説などをコピーして配布することや、児童生徒が調べ学習のために新聞記事などをコピーして他の児童生徒に配布するといった行為も問題なく認められます。
試験問題に利用する
著作権法36条1項において、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的のため、必要な限度において、公表された著作物を使用することができるとされています。
そのため、社説や小説を用いて試験を行うことも、問題なく認められます。
また、期末試験などの定期テストを行う場合も、同条の適用があるため、やはり、著作物の使用が認められますし、定期テストの場合は、35条1項も適用され、いずれにしても著作権法違反とならないと考えられています。
学校で注意すべきケース
上記のとおり、学校では、著作権者の許諾がなくても著作物を使用することができる場合が比較的多いですが、以下の場合には、著作物の使用が認められませんので注意が必要です。
個人または学校のホームページに使用する
著作権法35条1項は、「授業の過程における利用に供することを目的とする場合」に「必要と認められる限度において」、著作物を使用できると規定しているに過ぎません(著作権法35条1項)。
そして、学校がホームページに他者の著作物を掲載する場合、多くの場合、広報などが目的となるに過ぎず、授業での利用が目的とは認められないことがほとんどと考えられます。
そのため、学校が個人または学校のホームページに他者の著作物を使用することは認められません。
著作権法違反になってしまう典型的なケースですので注意を要します。
市販の学習ドリルなど購入を前提としたテキストをコピーする
市販の学習ドリルなど購入を前提としたテキストや図書をコピーする場合は、学校教育を目的とする場合でも、著作権法違反となります。
著作権法35条1項は、授業での利用を目的とする場合に、必要と認められる限度において、著作物を使用できると規定していますが、同時に、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」は著作権違反になるとしています(著作権法35条1項但書)。
そして、そもそも市販の学習ドリルなどは、個々人が購入することを前提としていますので、そのような前提のテキストや図書をコピーして利用することは、「著作権者の利益を不当に害する」と考えざるを得えないところです。
これも著作権法違反になってしまう典型的なケースですので注意を要します。
学校法人の著作権でお困りの方は弁護士にご相談ください
著作権は、小説、論文、講演、音楽、絵画、イラスト、アニメ、漫画、映画、写真といった作品について容易に認められる権利ですが、どのような場合に利用が許されるかは法令を確認しても分かり難いところがあります。
一方、学校の著作権侵害事例については時々ニュースでも見かけるところですので、しっかりとした対応が必要です。
学校法人の著作権でお困りの方は当事務所にご相談ください。
「授業や資料における著作権の注意点!学校側弁護士が解説」の関連記事はこちら
- いじめが発覚した際の学校側の対応を弁護士が解説
- 学校法人のM&Aのメリットやスキーム、流れを弁護士が解説
- 学校の広告や宣伝に関する不当表示や不正競争行為について
- 学校側で教員の内定取り消しができるケースって?弁護士が解説
- 教員からの残業代請求ってあり!?学校の残業代について弁護士が解説
- 私生活上の非違行為で教員の懲戒処分ってできる?弁護士が解説
- 学校・教育機関への誹謗中傷に強い弁護士をお探しの方へ
- 問題教員・モンスターティーチャーへの対応に強い弁護士をお探しの方へ
- 学校経営における教員の鬱・適応障害などへの対応|学校側の弁護士が解説
- 学校の広告にはどんな規制がある?誇大広告や罰則について学校法人に強い弁護士が解説
- 【学校側の弁護士】学校事故の保護者・生徒の対応に強い弁護士をお探しの方へ
- 授業で許される著作権って?学校法人に強い弁護士が徹底解説
- 共通テスト流出・・・学校法人における問題漏洩について弁護士が解説
- 学校側の弁護士が解説 – 学生側から留年・退学・除籍等に不服申し立てを受けてしまったら
- 保護者からのハラスメントに限界!クレーマーやモンスターペアレントに対して学校としてできること
- 学校法人の理事の選任・変更について学校側弁護士が解説
- 学校側弁護士がアカハラの防止・措置について解説 – 大学などにおけるアカデミックハラスメント
- 学校と個人情報保護法の関わりを弁護士が解説 – どこまでの提供ならOK?
- 授業や資料における著作権の注意点!学校側弁護士が解説
- 教員の定年と再雇用制度について学校法人に強い弁護士が解説
- 教員同士のパワハラや学校の長時間労働を労務問題に強い弁護士が解説
- 学校法人における就業規則の重要性について弁護士が解説
- モンスターペアレントからの誹謗中傷・悪口にどう対応すればいい?学校・幼稚園・保育園側の弁護士が解説
- 学校の労務トラブルや教職員のパワハラについて弁護士が解説
- 休職を繰り返す教員への対応 – 学校運営におけるメンタルヘルスを弁護士が解説
- 塾・予備校の弁護士が送迎トラブルや騒音問題への対処を解説
- 保護者トラブルって録音してOK?学校や保育園・幼稚園側の弁護士がモンスターペアレント対応について解説
- 生徒への暴言や行きすぎた指導をする教師に対して学校側ができること
- モンスターペアレントに法的措置は可能?保護者への対応や学校運営のポイントを解説
- 学校事故の事例・対応法って?保護者対応などについても弁護士が解説
- 学校側からモンスターペアレントに法的措置は可能?モンペの対応を学校・幼稚園・保育園に強い弁護士が解説
- 給食費を払わない家庭からの徴収について学校法人に強い弁護士が解説
- 給食費を払わない親への請求方法!顧問弁護士なら支払督促が可能です
- 学校運営で知っておくべき基準!体罰はどこから?教師への措置について弁護士が解説
- 学習塾・予備校のための弁護士 – 教育支援業の法律相談は西村綜合法律事務所まで

 メール・Web
メール・Web