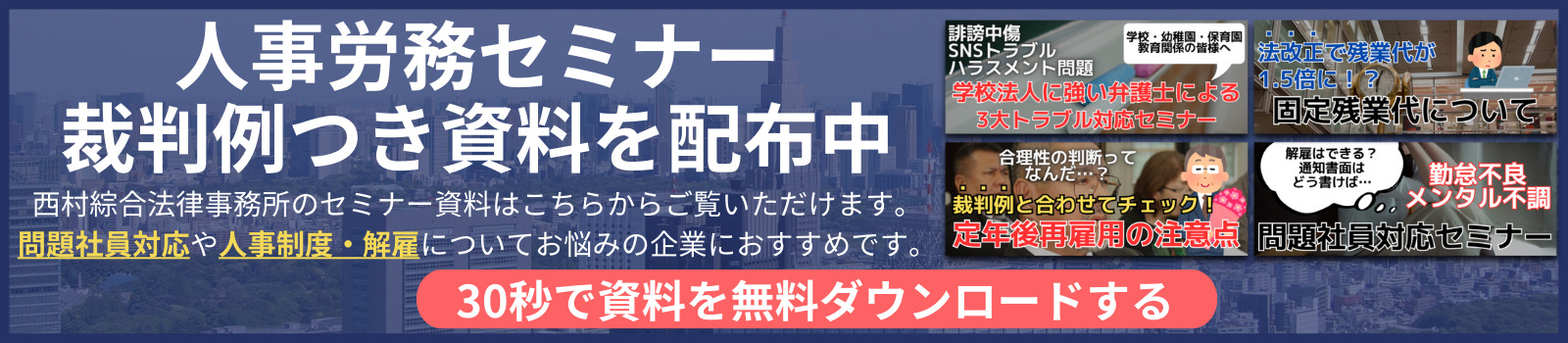学校側弁護士がアカハラの防止・措置について解説 – 大学などにおけるアカデミックハラスメント
学校関連のお問合せにつきましては、当事務所は学校側に注力しておりますので
保護者側・生徒側(学校側が相手になるケース)のご相談は原則としてお受けできません
1.アカデミックハラスメントの概要
近年、報道などでアカデミックハラスメントに関する問題が取り上げられることが多くなってきています。アカデミックハラスメントはセクシャルハラスメントやパワーハラスメントなどのハラスメントの一種です。もっとも、アカデミックハラスメントは教育機関や学校で問題になるため、他のハラスメントとは一線を画すところがあり、その特性に留意しながら対応することが必要になります。
この記事ではアカデミックハラスメントに対処する方法を説明していきます。
学校・幼稚園・保育園などの教育機関における問題教員・モンスター職員への対応に強い弁護士をお探しの方はこちらのページもご覧ください。
1.1定義
アカデミックハラスメントは法律で定義が決められているわけではありません。
様々な意味合いで使用される表現ではありますが、NPOアカデミック・ハラスメントをなくすネットワーク(NAAH)では、アカデミックハラスメントを「研究教育に関わる優位な力関係のもとで行われる理不尽な行為」と定義しています。
東京大学の「東京大学アカデミックハラスメント防止宣言」では、アカデミックハラスメントを「大学の構成員が、教育・研究上の権力を濫用し、他の構成員に対して不適切で不当な言動を行うことにより、その者に、修学・教育・研究ないし職務遂行上の不利益を与え、あるいはその修学・教育・研究ないし職務遂行に差し支えるような精神的・身体的損害を与えることを内容とする人格権侵害」と定義し、京都大学の「京都大学におけるハラスメントの防止等に関する規程」ではアカデミックハラスメントを「教員がその職務上の地位又は権限その他人間関係等の優位性を不当に利用して他の教員又は学生等に対して行う業務の適正な範囲を超えた研究若しくは教育上又は修学上の不適切な言動」と定義しています。
そのため、学校を始めとした教育機関で問題になるハラスメント一般をアカデミックハラスメントと呼ぶと考えれば大きな問題ないといえるでしょう。
アカデミックハラスメントが問題になる学校や教育機関は、閉鎖的な人間関係が形成される部分があるところです。そのため、アカデミックハラスメントについては、周囲からその存在を認識し難いといった特徴があります。また、その存在を認識し難いことから、ハラスメントがエスカレートし、被害者に重大な損害を被ることが少なくないという点もアカデミックハラスメントの特徴の一つです。
1.2具体的なアカデミックハラスメントの例
上記のNPOアカデミック・ハラスメントをなくすネットワークではアカデミックハラスメントの具体例を例示しており、次のような行為がアカデミックハラスメントに該当するとしています。
■研究教育機関における正当な活動を直接的・間接的に妨害すること。
■学生の進級・卒業・修了を正当な理由無く認めないこと。また正当な理由無く単位を与えないこと。
■就職・進学の妨害、望まない異動の強要など。
■教員の職務上の義務である研究指導や教育を怠ること。また指導下にある学生・部下を差別的に扱うこと。
■本来研究費から支出すべきものを、学生・部下に負担させる。
■研究論文の著者を決める国際的なルールを破ること、アイデアの盗用など。
■本人がその場に居るか否かにかかわらず、学生や部下を傷つけるネガティブな言動を行うこと。発奮させる手段としても不適切。
■暴力。
■誹謗、中傷。
■不適切な環境下での指導の強制。
■権力の濫用。
■プライベートを必要以上に知ろうとしたり、プライベートなことに介入しようとしたりすること。
■他大学の学生、留学生、聴講生、ゲストなどへの排斥行為。
学校関連のお問合せにつきましては、当事務所は学校側に注力しておりますので
保護者側・生徒側(学校側が相手になるケース)のご相談は原則としてお受けできません
2.アカデミックハラスメントの防止方法
2.1学校内の組織を整備し教員を教育する
アカデミックハラスメントを防止するには、ハラスメントは許されない行為であるということを教員に認識させることが重要になります。
そこで、アカデミックハラスメントに関する規程を作成する、あるいは、就業規則においてアカデミックハラスメントが懲戒事由に該当することを明記するといった対応をとることで、アカデミックハラスメントに対してはペナルティが課されるということを教員に認識させることがスタートとなります。
また、教員に対する研修を行うなどして、ハラスメントを行うべきではないという意識を組織単位で醸成することも重要です。
2.2相談窓口を活用する
上記のとおり、閉鎖的な環境がアカデミックハラスメントを生じさせる遠因の一つとなっています。そこで、相談窓口を設置し、いつでも被害申告を相談できる環境を整備することが大切となります。
大学を始めとしたほとんどの教育機関には既に相談窓口が設置されているもの思われます。しかし、アカデミックハラスメントの対策を一歩前に進めるのであれば、様々な種類の相談窓口を複数設置するというのが効果的です。
すなわち、総務部などの内部通報窓口しか相談窓口を設けていない学校が散見されますが、内部の通報窓口の場合、申告者が特定される可能性に懸念があることや、人間関係から抵抗があることを理由として、被害者が相談窓口の利用を躊躇う可能性が否定できません。
そこで、例えば法律事務所などに相談窓口を設置し、外部の相談窓口も併用することで、被害者の抵抗感を軽減させることが可能になります。
また、相談窓口を設置するだけでは意味がないため、その存在を適時アピールすることも重要になります。
3.法的な側面
3.1教員の責任
アカデミックハラスメントが行われた場合、そのような行為を行った教員は、被害者の人格権を侵害したとして、不法行為に基づく損害賠償責任を負う可能性があるところです(民法709条)。
また、アカデミックハラスメントが暴力、強要など犯罪行為に及んでいるような場合には、傷害罪(刑法第204条)、暴行罪、(同208条)、強要罪(同223条)といった刑事責任も生じる可能性があります。
さらに、アカデミックハラスメントの存在が確認された場合、そのような行為の存在は懲戒処分の対象になるところです。内容や被害の程度にもよりますが、戒告、譴責、減給、出勤停止、降格、懲戒解雇といった懲戒処分が下されるという責任も負うことになります。
3.2学校の責任
学校法人が雇用する教員が、他の者にアカデミックハラスメントを行い、その教員が損害賠償責任を負う場合は、学校法人も使用者責任に基づく損害賠償責任を負う可能性があります(民法715条)。
また、学校法人は雇用する労働者の心身の安全を確保するように努めなければいけないという安全配慮義務を負っています。そのため、学校法人がこのような義務を履行しなかった結果、雇用する被害者にアカデミックハラスメントの被害が生じてしまった場合は、債務不履行に基づく損害賠償責任を負う可能性もあるところです(同415条)。
3.3第三者の支援や弁護士の助言
被害者がアカデミックハラスメントの被害を申告した場合、学校法人としてはその存在を調査しなくてはなりません。
しかし、加害者とされた者がハラスメント行為の存在を否定した場合、ハラスメントが行われたのか、行われなかったのかを証拠に照らして事実認定することは容易なことではありません。また、特定の行為の存在が確認された場合でも、その行為がアカデミックハラスメントに該当するのか、しないのかの判断が容易でないことも少なくありません。
そのため、学校法人がアカデミックハラスメントに適切に対応していくには、第三者の支援や弁護士の助言を受けることが不可欠といえます。
そして、証拠に基づいて事実を認定する能力を持つこと、裁判例や法令に関する知識が豊富であることに照らせば、基本的には弁護士のアドバイスに従ってアカデミックハラスメントに対応していくのが適当と考えられます。
学校関連のお問合せにつきましては、当事務所は学校側に注力しておりますので
保護者側・生徒側(学校側が相手になるケース)のご相談は原則としてお受けできません
「学校側弁護士がアカハラの防止・措置について解説 – 大学などにおけるアカデミックハラスメント」の関連記事はこちら
- いじめが発覚した際の学校側の対応を弁護士が解説
- 学校法人のM&Aのメリットやスキーム、流れを弁護士が解説
- 学校の広告や宣伝に関する不当表示や不正競争行為について
- 学校側で教員の内定取り消しができるケースって?弁護士が解説
- 教員からの残業代請求ってあり!?学校の残業代について弁護士が解説
- 私生活上の非違行為で教員の懲戒処分ってできる?弁護士が解説
- 学校・教育機関への誹謗中傷に強い弁護士をお探しの方へ
- 問題教員・モンスターティーチャーへの対応に強い弁護士をお探しの方へ
- 学校経営における教員の鬱・適応障害などへの対応|学校側の弁護士が解説
- 学校の広告にはどんな規制がある?誇大広告や罰則について学校法人に強い弁護士が解説
- 【学校側の弁護士】学校事故の保護者・生徒の対応に強い弁護士をお探しの方へ
- 授業で許される著作権って?学校法人に強い弁護士が徹底解説
- 共通テスト流出・・・学校法人における問題漏洩について弁護士が解説
- 学校側の弁護士が解説 – 学生側から留年・退学・除籍等に不服申し立てを受けてしまったら
- 保護者からのハラスメントに限界!クレーマーやモンスターペアレントに対して学校としてできること
- 学校法人の理事の選任・変更について学校側弁護士が解説
- 学校側弁護士がアカハラの防止・措置について解説 – 大学などにおけるアカデミックハラスメント
- 学校と個人情報保護法の関わりを弁護士が解説 – どこまでの提供ならOK?
- 授業や資料における著作権の注意点!学校側弁護士が解説
- 教員の定年と再雇用制度について学校法人に強い弁護士が解説
- 教員同士のパワハラや学校の長時間労働を労務問題に強い弁護士が解説
- 学校法人における就業規則の重要性について弁護士が解説
- モンスターペアレントからの誹謗中傷・悪口にどう対応すればいい?学校・幼稚園・保育園側の弁護士が解説
- 学校の労務トラブルや教職員のパワハラについて弁護士が解説
- 休職を繰り返す教員への対応 – 学校運営におけるメンタルヘルスを弁護士が解説
- 塾・予備校の弁護士が送迎トラブルや騒音問題への対処を解説
- 保護者トラブルって録音してOK?学校や保育園・幼稚園側の弁護士がモンスターペアレント対応について解説
- 生徒への暴言や行きすぎた指導をする教師に対して学校側ができること
- モンスターペアレントに法的措置は可能?保護者への対応や学校運営のポイントを解説
- 学校事故の事例・対応法って?保護者対応などについても弁護士が解説
- 学校側からモンスターペアレントに法的措置は可能?モンペの対応を学校・幼稚園・保育園に強い弁護士が解説
- 給食費を払わない家庭からの徴収について学校法人に強い弁護士が解説
- 給食費を払わない親への請求方法!顧問弁護士なら支払督促が可能です
- 学校運営で知っておくべき基準!体罰はどこから?教師への措置について弁護士が解説
- 学習塾・予備校のための弁護士 – 教育支援業の法律相談は西村綜合法律事務所まで

 メール・Web
メール・Web