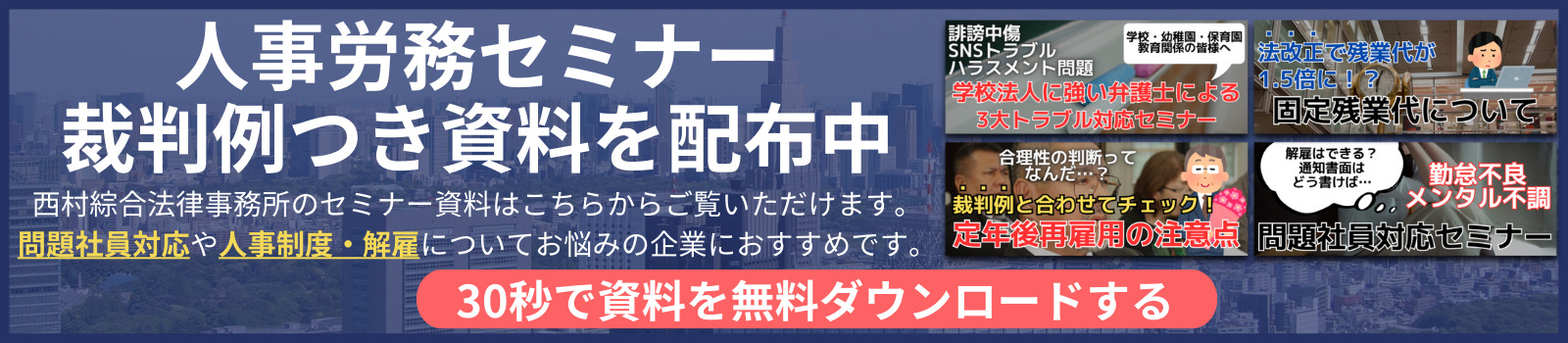生徒への暴言や行きすぎた指導をする教師に対して学校側ができること
学校内での生徒指導には適切な行動が求められますが、中には行き過ぎた指導や暴言・暴力などの問題が発生することがあります。
そうした問題が生じた場合、学校法人としてどのような対応が求められるのでしょうか?
本記事では、学校法人の経営者や人事担当者向けのコラムといたしまして、問題教職員に対する対処方法や、その問題が生徒・保護者に与える影響などについて解説します。
学校・幼稚園・保育園などの教育機関における問題教員・モンスター職員への対応に強い弁護士をお探しの方はこちらのページもご覧ください。
学校法人における”問題社員”の例
学校法人における”問題社員”の例としては次のようなものがあります。
生徒への暴言
まず、生徒に対して暴言を言ってしまう教職員です。公立、私立の学校を問わず教職員が生徒に対して暴言を吐いたというニュースを目にしたことがある方も多いかと思います。
学校教育法第11条は「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、監督庁の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。但し、体罰を加えることはできない。」と規定し、教職員の体罰を禁止しているのですが、暴言が体罰といえるかについては条文上不明確といえます。
しかし、東京都においては、「暴言や行き過ぎた指導は、体罰概念に含まれないが、体罰と同様に、教育上不適切な行為であり許されないものである。」と公表しており、体罰と同様に教職員の暴言も問題視していく必要があるとしています。
過剰な叱咤と暴力
次に、部活動などの指導の際に、過剰な叱咤と暴力に手を出してしまう教職員も散見されるところです。このような例は、部活動や課外活動に注力しているような学校法人において問題となることが多いところです。
この点については、厚労省が平成25年5月27日付で「運動部活動の在り方に関する調査研究報告書」を公表していますが、①殴る、蹴る等、②社会通念、医・科学に基づいた健康管理、安全確保の点から認め難い又は限度を超えたような肉体的、精神的負荷を課す、③パワーハラスメントと判断される言葉や態度による脅し、威圧・威嚇的発言や行為、嫌がらせ等を行う、④セクシャルハラスメントと判断される発言や行為を行う、⑤身体や容姿に係ること、人格否定的(人格等を侮辱したり否定したりするような)な発言を行う、⑥特定の生徒に対して独善的に執拗かつ過度に肉体的、精神的負荷を与える、といった行動は体罰等として許されないとしています。
このように、どのような理由があるとしても、教職員の生徒に対する暴力は許されないとされています。
理不尽な評価
教職員が、生徒に対し、理不尽な評価を行うというのも問題行動の一つとされています。教職員である以上、生徒を客観的かつ公平に評価することが必要ですが、自身の好き嫌いで生徒を評価してしまう教職員がいるため、生徒や保護者から時折問題視されることがあります。
問題のある教職員を放置するリスク
学校法人が上記のような問題のある教職員を放置してしまうとどのようなリスクが生じてしまうのでしょうか。
生徒への精神的な負荷・不登校への発展
当然ですが、問題のある教職員を放置することで、最も大きな被害を受けてしまうのは、直接教職員と接する生徒自身です。
教師による不適切な指導が原因で生徒に精神的な負荷が生じることはあってはならないことです。また、教師による不適切な指導が継続すれば、生徒が不登校に陥ってしまう可能性もあり、問題が重大化する可能性が存在します。
ハラスメント問題として学校法人の評価の低下
教職員の問題行動がパワーハラスメント、セクシャルハラスメントと評価され、学内でそのような問題が生じていることが対外的に明るみに出ると、ハラスメント問題として学校法人の評価の低下を免れることができなくなります。
教育委員会等も関与した問題への発展
学校法人の教職員が問題を起こしてしまう場合、教育委員会による事実関係の確認、公表といった事態に発展する可能性もあるところです。
また、事案がより重大な場合は、第三者員会が設置され、外部の構成員による調査を受けるという事態に発展する可能性も存在します。
問題のある教職員にすべき対処方法
上記のような問題のある教職員に対し、学校法人はどのように対応すべきでしょうか。
現在の対応状況に関する事実確認(教職員・生徒)
まず、教職員の問題行動に関しては、どのような事実関係が存在するのかを確認することが必要になります。
学校法人が教職員の問題行動を把握する経緯は様々かと思いますが、問題行動の被害者あるいはその目撃者から、他の教職員や相談窓口に相談が寄せられるというパターンが比較的多いのではないかと思われます。
そのような場合は、被害者、目撃者から事実関係をヒアリングするとともに、被害内容を基礎づける客観的証拠の提出を求めます。また、その他にも被害状況を知っている第三者がいるかを確認し、そのような第三者がいる場合は、第三者から事実関係と客観的な証拠の存在を確認します。
このように被害者、目撃者、第三者から事実関係を確認した場合は、確認した事実を整理します。
その後に、問題を起こした教職員からも話を聞きます。そして、
①どのような事実関係を認めるのか
②どのような事実関係を認めないのか
を明らかにし、①の教職員が認めた事実については、特別の事情がない限り、そのような事実関係があったと認定することができますが、②の教職員が認めなかった事実については、被害者、目撃者、第三者からのヒアリング内容及び収集した客観的証拠によって、事実認定ができるのかを検討することが必要になります。
このように教職員・生徒問わず、現在の対応状況に関する事実確認を行い、正確な事実認定を行うことが必要となります。
事実内容に基づいた指導・改善に向けた対応策の提示
上記のとおり、事実認定の結果、教職員の問題行動が存在すると確認できた場合は、懲戒処分を含めて指導を行うことが必要になります。問題行動が認められた教職員自身に適切な指導を行うことが、学校法人の信頼回復に向けた第一歩となります。
また、教職員に対する処分だけではなく、教職員が問題を起こしたという事実を、学校法人自身の問題でもあると捉え、同じ問題が繰り返されないように改善に向けた対応策を決定し実行していくことになります。
改善が見込めない場合、退職・解雇等の検討
上記のように教職員に対し指導を実施しても、指導が奏功せず改善が見込めない場合も考えられるところです。
そのような場合は、教職員を解雇することも検討する必要があります。
しかし、公立学校と異なり学校法人における教職員については、労働基準法が適用されます。そのため、教職員を解雇するには、客観的に合理的な理由が存在するとともに、社会通念上相当であると認められることが必要となるのですが(労働基準法16条)、条文が抽象的であり明確な基準を設けていないため、教職員の解雇に当たっては、時には微妙な判断を迫られることも多く、多くの学校法人様が頭を悩ませているところでもあります。
問題のある教職員対応でお困りの学校法人様は西村綜合法律事務所にご相談ください
学校法人における教職員の問題行動に対しては、生徒の心身のケア、レピュテーションに対する配慮など、一般企業の問題社員対応とは異なった観点からの対応が必要になります。問題のある教職員対応でお困りの学校法人様は当事務所にご相談ください。
「生徒への暴言や行きすぎた指導をする教師に対して学校側ができること」の関連記事はこちら
- いじめが発覚した際の学校側の対応を弁護士が解説
- 学校法人のM&Aのメリットやスキーム、流れを弁護士が解説
- 学校の広告や宣伝に関する不当表示や不正競争行為について
- 学校側で教員の内定取り消しができるケースって?弁護士が解説
- 教員からの残業代請求ってあり!?学校の残業代について弁護士が解説
- 私生活上の非違行為で教員の懲戒処分ってできる?弁護士が解説
- 学校・教育機関への誹謗中傷に強い弁護士をお探しの方へ
- 問題教員・モンスターティーチャーへの対応に強い弁護士をお探しの方へ
- 学校経営における教員の鬱・適応障害などへの対応|学校側の弁護士が解説
- 学校の広告にはどんな規制がある?誇大広告や罰則について学校法人に強い弁護士が解説
- 【学校側の弁護士】学校事故の保護者・生徒の対応に強い弁護士をお探しの方へ
- 授業で許される著作権って?学校法人に強い弁護士が徹底解説
- 共通テスト流出・・・学校法人における問題漏洩について弁護士が解説
- 学校側の弁護士が解説 – 学生側から留年・退学・除籍等に不服申し立てを受けてしまったら
- 保護者からのハラスメントに限界!クレーマーやモンスターペアレントに対して学校としてできること
- 学校法人の理事の選任・変更について学校側弁護士が解説
- 学校側弁護士がアカハラの防止・措置について解説 – 大学などにおけるアカデミックハラスメント
- 学校と個人情報保護法の関わりを弁護士が解説 – どこまでの提供ならOK?
- 授業や資料における著作権の注意点!学校側弁護士が解説
- 教員の定年と再雇用制度について学校法人に強い弁護士が解説
- 教員同士のパワハラや学校の長時間労働を労務問題に強い弁護士が解説
- 学校法人における就業規則の重要性について弁護士が解説
- モンスターペアレントからの誹謗中傷・悪口にどう対応すればいい?学校・幼稚園・保育園側の弁護士が解説
- 学校の労務トラブルや教職員のパワハラについて弁護士が解説
- 休職を繰り返す教員への対応 – 学校運営におけるメンタルヘルスを弁護士が解説
- 塾・予備校の弁護士が送迎トラブルや騒音問題への対処を解説
- 保護者トラブルって録音してOK?学校や保育園・幼稚園側の弁護士がモンスターペアレント対応について解説
- 生徒への暴言や行きすぎた指導をする教師に対して学校側ができること
- モンスターペアレントに法的措置は可能?保護者への対応や学校運営のポイントを解説
- 学校事故の事例・対応法って?保護者対応などについても弁護士が解説
- 学校側からモンスターペアレントに法的措置は可能?モンペの対応を学校・幼稚園・保育園に強い弁護士が解説
- 給食費を払わない家庭からの徴収について学校法人に強い弁護士が解説
- 給食費を払わない親への請求方法!顧問弁護士なら支払督促が可能です
- 学校運営で知っておくべき基準!体罰はどこから?教師への措置について弁護士が解説
- 学習塾・予備校のための弁護士 – 教育支援業の法律相談は西村綜合法律事務所まで

 メール・Web
メール・Web