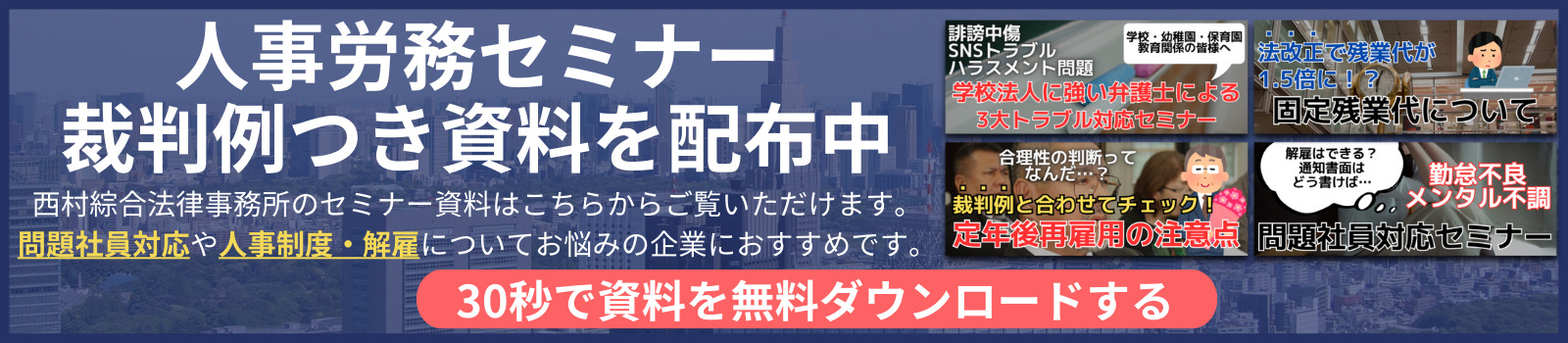教員の定年と再雇用制度について学校法人に強い弁護士が解説

一般企業と同様に、学校法人においても65歳までは再雇用制度などで教職員の雇用を継続しなければなりません。
高齢化の進行や教員のなり手の減少にともなって、定年を迎えた教職員の扱いの重要性が高まっています。経営面に配慮しつつ高齢人材を適切に活用するためには、再雇用制度に関する法律上のルールを押さえておくべきです。
本記事では、
- 再雇用制度の基礎知識
- 学校法人が再雇用制度で気をつけるべきポイント
- 再雇用の拒否が可能か
などについて弁護士が解説しています。
再雇用制度について知りたい学校法人関係者の方は、ぜひ最後までお読みください。
再雇用制度の基礎知識
まずは、定年後の再雇用制度とはいかなるものかを解説します。
再雇用制度とは?
再雇用制度とは、定年を迎えた労働者をいったん退職させたうえで、もう一度雇用する制度をいいます。
再雇用制度が必要とされるのは、高年齢者雇用安定法において、就労を希望する労働者について65歳までの雇用継続が義務づけられたためです。
具体的には、事業者は65歳までの雇用を確保するために以下のいずれかの方法をとらなければなりません(高年齢者雇用安定法9条1項)。
- 定年の引き上げ
- 雇用継続制度の導入
- 定年の廃止
法律上は上記のいずれかの方法をとればよいのですが、定年の引き上げや廃止は経営へのインパクトが大きいと考えられます。現実には、雇用継続制度の導入を選択している事業者が多いです。
定年後再雇用制度と「再就職」との違いとは?
定年を迎えた人が「再就職」をするケースもあります。再就職とは、定年退職後に別の会社に就職することです。教育業界においても、教員が定年後に別の学校に勤務するケースは見受けられます。
再雇用制度は、いったん定年退職するものの、同じ会社で働き続ける制度です。再就職と再雇用制度を比べると、定年退職する点は同様ですが、定年後の勤務先が変わるか否かという違いがあります。
学校法人が再雇用制度で気をつけるべきポイント
再雇用制度において気をつけるべきポイントは以下の通りです。
雇用形態・契約期間
再雇用制度において、雇用形態に制限はありません。常勤とするか非常勤とするかについても定めはありません。したがって、合意さえできれば、正社員であった教職員を契約社員、嘱託社員、パートタイマーなどで雇用できます。
契約期間についても決まりはありません。実際には契約期間を1年とし、65歳まで毎年更新するのが一般的です。学校側の意向による65歳に達する前の雇い止めは、労働契約法19条により制限されています。
有期の労働契約については、通算5年を超えると労働者からの申し入れにより無期の労働契約に転換されるとのルールが存在します(労働契約法18条)。無期転換ルールには有期雇用特別措置法による特例があり、定年後に再雇用された高齢者を対象から外すことが可能です。特例を適用するためには、労働局による認定を受けなければなりません。
賃金(給与)
再雇用後の賃金は、教職員との合意により決定できます。定年前と同一の賃金を支払う必要はありません。実際に、再雇用後に給与が下がるケースは多いです。
もっとも、同じ仕事をする定年前の教職員と比べて著しく低額だと、パートタイム有期雇用労働法8条に違反してしまいます。何割まで減額できるかは個々の事情にもよるため明確な線引きはできませんが、定年前と同じ仕事をしているのに極端に減少しないよう注意してください。
基本給だけでなく、各種手当についても不合理な差別をしてはなりません。たとえば、交通費は職種や雇用形態に関係なく発生するため、再雇用した教職員に通勤手当を支給しないのは不合理と考えられます。
また、賃金に大きな影響を与えるのが仕事内容です。
再雇用後も常勤で仕事内容は変わらないケースもありますが、担任や部活の顧問には就かないなど、変更点があっても構いません。業務負荷や責任を軽くすれば、賃金の低下を正当化しやすいです。
もっとも、教員を再雇用後に清掃員にするなど、元の仕事とあまりにかけ離れた業務内容としてはなりません。従来の経験を全く生かせない業務を命じれば、違法と判断されるリスクがあります。
いずれにせよ、トラブル防止のためには、再雇用後の仕事内容や待遇に関する十分な説明を心がけてください。
有給休暇
再雇用後の年次有給休暇の付与日数は、定年前の勤務期間を通算して決定されます。形式的には再雇用される前に定年退職していますが、実質的には続けて雇用しているためです。
定年前に付与されていた有給休暇は、再雇用によりリセットされずに繰り越されます。
再雇用制度の拒否について
教職員が再雇用を望んでいるにもかかわらず学校側が拒否するのは、原則として違法です。希望者は全員再雇用するのが基本になります。
例外的に、心身の状態が勤務に耐えられない、勤務態度が著しく不良であるなど、解雇できる理由があれば再雇用を拒否できます。「重度の認知症である」「児童・生徒にわいせつ行為に及んだ」といったケースが想定されます。
とはいえ、再雇用を拒否できるケースは限定的です。「指導能力が低い」「担当クラスでいじめが発生した」といった理由だけでいきなり解雇するのは困難であり、再雇用の拒否もできません。
再雇用の拒否が違法である場合には損害賠償請求がなされ、多額の支払いを強いられるリスクがあります。安易に拒否しないようにしてください。
なお、そもそも教職員が再雇用を望んでいないケースや、合理的な条件を提示したのに教職員が同意してくれなかったケースでは、再雇用しなくても違法とはなりません。
学校法人の再雇用制度は弁護士にご相談ください
ここまで、再雇用制度について、制度の意義や学校法人が注意すべき点などについて解説してきました。
高齢化の進行により、65歳までの雇用継続が法律上義務づけられています。方法はいくつかありますが、学校側にとって負担が少ない再雇用制度は現実的な手段といえるでしょう。もっとも、待遇を下げすぎて教職員との間でトラブルが発生しないよう、注意しなければなりません。
再雇用制度についてお悩みの方は、弁護士までご相談ください。雇用形態や賃金体系などについて、法令に反しないで適切な制度設計ができるようアドバイスが可能です。就業規則の変更など、必要な各種手続きもサポートいたします。すでにトラブルが発生している場合には、交渉・訴訟を代行し、解決に向けて活動します。
当事務所は、学校法人に関する法律問題に積極的に取り組んでおり、教育現場特有の事情も踏まえた対応が可能です。お困りの方はぜひお問い合わせください。
「教員の定年と再雇用制度について学校法人に強い弁護士が解説」の関連記事はこちら
- いじめが発覚した際の学校側の対応を弁護士が解説
- 学校法人のM&Aのメリットやスキーム、流れを弁護士が解説
- 学校の広告や宣伝に関する不当表示や不正競争行為について
- 学校側で教員の内定取り消しができるケースって?弁護士が解説
- 教員からの残業代請求ってあり!?学校の残業代について弁護士が解説
- 私生活上の非違行為で教員の懲戒処分ってできる?弁護士が解説
- 学校・教育機関への誹謗中傷に強い弁護士をお探しの方へ
- 問題教員・モンスターティーチャーへの対応に強い弁護士をお探しの方へ
- 学校経営における教員の鬱・適応障害などへの対応|学校側の弁護士が解説
- 学校の広告にはどんな規制がある?誇大広告や罰則について学校法人に強い弁護士が解説
- 【学校側の弁護士】学校事故の保護者・生徒の対応に強い弁護士をお探しの方へ
- 授業で許される著作権って?学校法人に強い弁護士が徹底解説
- 共通テスト流出・・・学校法人における問題漏洩について弁護士が解説
- 学校側の弁護士が解説 – 学生側から留年・退学・除籍等に不服申し立てを受けてしまったら
- 保護者からのハラスメントに限界!クレーマーやモンスターペアレントに対して学校としてできること
- 学校法人の理事の選任・変更について学校側弁護士が解説
- 学校側弁護士がアカハラの防止・措置について解説 – 大学などにおけるアカデミックハラスメント
- 学校と個人情報保護法の関わりを弁護士が解説 – どこまでの提供ならOK?
- 授業や資料における著作権の注意点!学校側弁護士が解説
- 教員の定年と再雇用制度について学校法人に強い弁護士が解説
- 教員同士のパワハラや学校の長時間労働を労務問題に強い弁護士が解説
- 学校法人における就業規則の重要性について弁護士が解説
- モンスターペアレントからの誹謗中傷・悪口にどう対応すればいい?学校・幼稚園・保育園側の弁護士が解説
- 学校の労務トラブルや教職員のパワハラについて弁護士が解説
- 休職を繰り返す教員への対応 – 学校運営におけるメンタルヘルスを弁護士が解説
- 塾・予備校の弁護士が送迎トラブルや騒音問題への対処を解説
- 保護者トラブルって録音してOK?学校や保育園・幼稚園側の弁護士がモンスターペアレント対応について解説
- 生徒への暴言や行きすぎた指導をする教師に対して学校側ができること
- モンスターペアレントに法的措置は可能?保護者への対応や学校運営のポイントを解説
- 学校事故の事例・対応法って?保護者対応などについても弁護士が解説
- 学校側からモンスターペアレントに法的措置は可能?モンペの対応を学校・幼稚園・保育園に強い弁護士が解説
- 給食費を払わない家庭からの徴収について学校法人に強い弁護士が解説
- 給食費を払わない親への請求方法!顧問弁護士なら支払督促が可能です
- 学校運営で知っておくべき基準!体罰はどこから?教師への措置について弁護士が解説
- 学習塾・予備校のための弁護士 – 教育支援業の法律相談は西村綜合法律事務所まで

 メール・Web
メール・Web