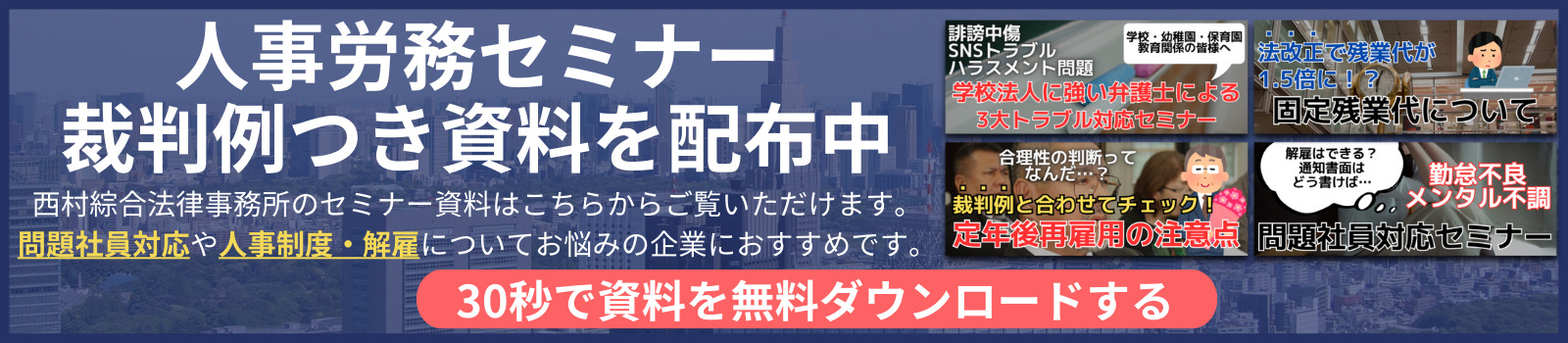保護者からのハラスメントに限界!クレーマーやモンスターペアレントに対して学校としてできること
「保護者から理不尽なクレームを受けた」「近隣住民から騒音に苦情が出ている」などとお悩みでしょうか?
クレームが正当な場合もありますが、不当な要求が続くと学校だけで対応できないケースも少なくありません。必要に応じて弁護士に対応を任せれば、教職員の負担を減らして本来の業務に集中できます。
本記事では、
- 学校法人のクレーム対応を弁護士に任せるメリット
- 学校への悪質クレーマーに対応する方法
- 学校法人における主なクレームの種類と対応方法
などについて解説しています。
クレーム対応にお悩みの学校関係者の方は、ぜひ最後までお読みください。
また、現在モンスターペアレントや保護者からのハラスメントにお悩みの従業員(教員や事務の方等)がいらっしゃいましたら、まずは校内の主任や上長にあたる方へご相談ください。弁護士が介入する場合、「学校全体」と保護者(クレーマー)の間に入ることになりますので、どちらにせよ学校として対処する形になります。その場合、事前に学校側とお話しができていないと対応できないケースがほとんどです。
加えて教員個人への攻撃だけでなく、学校や幼稚園への誹謗中傷にまで発展してしまった場合は弁護士へのご相談をお勧めいたします。詳しくはこちらのページをご覧ください。
学校への悪質クレーマーに対応する方法
学校への悪質なクレーマーに対応する際には、以下の点に注意してください。
窓口を統一する
ポイントのひとつは、窓口を統一することです。個々の教職員に対応を任せ、それぞれで言っていることが異なると、クレーマーにつけ入る隙を与えてしまいます。
窓口をひとつにすれば、学校として組織的な対応が可能です。とりわけ弁護士を窓口にすれば、相手に隙を見せずに対応できます。
教員に理不尽な謝罪をさせない
クレームを受けたときに、場を収めるために教職員に謝罪させるケースがあります。
しかし、理不尽な謝罪をすると、クレーマーが調子づいて要求を拡大させるリスクが高いです。加えて、謝罪を強いられた教職員に対する安全配慮義務違反として、学校から教職員への損害賠償責任が発生する可能性もあります。
クレーム対応として最後まで話を聞くにしても、不当な主張に対して謝罪する必要はありません。
学校法人のクレーム対応を弁護士に任せるメリット
学校に寄せられるクレームの種類は様々です。
中には以下のような理不尽なクレームもあります。
- 自分の子を特別扱いして欲しい
- 卒業後に人生がうまくいかないのは学校の指導のせいだ
- 近所に音が響くので校庭で遊ぶのは禁止にしろ
教職員がクレーム対応に追われると、他の業務に支障が出る、メンタルヘルス不調をきたすなどの弊害が生じます。また、適切に対応しないとネット上に誹謗中傷を書き込まれるリスクもあります。
学校だけで対応が困難であれば、弁護士に任せるのが有効な方法です。弁護士にクレーム対応を任せると、以下のメリットがあります。
法的に説得力ある説明ができる
悪質なクレーマーは、自分勝手な論理を振りかざして、要求を受け入れさせようとします。
- ケンカはすべて学校の責任だから損害を賠償しろ
- 指導が足りない分だけ学費を返せ
- 登下校時の声がうるさいので慰謝料を払え
こうした主張に応じるのは不可能です。しかし、教職員に対応を任せると強く反論できない場合も多いでしょう。
弁護士に対応を任せれば、法律上できないことを明確にし、適切な説明ができます。
もちろん教育現場である以上、法律だけですべて解決できるわけではありません。とはいえ、法律上無理のある主張には毅然と反論しないと、要求がエスカレートしてしまいます。
自分勝手な要求をするクレーマーには、教職員からではなく、弁護士の立場から法律上の説明をする方が有効です。
クレームの繰り返しを防ぐ
学校側に非がある場合には、補償など一定の対応が必要になる可能性もあります。
もっとも、取り決めた内容が双方に明確になっていないと、クレームが繰り返されるリスクが高いです。弁護士がついていれば、合意内容を書面にし、争いを蒸し返されないように対応できます。
学校本来の業務に集中できる
理不尽なクレームへの対応は、学校の本来の業務ではありません。クレーム対応に慣れていない教職員が相手をすると、不十分な対応になるばかりか、本来の業務に支障が出るおそれがあります。
クレーム対応に精通した弁護士に対応を任せれば、本来の業務を圧迫せずにすみ、教職員の負担を軽減できます。
また、現在モンスターペアレントや保護者からのハラスメントにお悩みの従業員(教員や事務の方等)がいらっしゃいましたら、まずは校内の主任や上長にあたる方へご相談ください。弁護士が介入する場合、「学校全体」と保護者(クレーマー)の間に入ることになりますので、どちらにせよ学校として対処する形になります。その場合、事前に学校側とお話しができていないと対応できないケースがほとんどです。
学校におけるクレーム解決までの流れと弁護士の役割
学校におけるクレーム解決の流れは、以下の通りです。弁護士が担う役割にも触れつつ解説します。
事実関係を把握する
まずは、事実関係の把握が不可欠です。事実認識を誤ってしまうと、その後の対応も適切にできません。不自然な主張だと感じても、ひとまず相手の言い分を聞いたうえで、関係者への事情聴取などを通じて正確な事実を調査してください。
弁護士は、相手に連絡をとって主張を聞き、学校関係者への事情聴取や客観的な証拠の収集も行います。事実調査に慣れているため、より正確な状況把握が可能です。
解決策を検討し提示する
事実調査が完了したら、解決策の検討に移ります。学校側に法的な責任があるか、何らかの補償や謝罪が必要かなどを話しあって、方針を決定してください。方針を決定したら、相手方に回答として提示しましょう。
検討に弁護士が入っていれば、法的責任の有無やリスクについて確実な判断が可能です。法的責任があるときには、裁判になる事態も想定しつつ、交渉で妥当な落としどころを探ります。法的に問題がないときには、必要以上に譲歩せずに対応します。
合意ができたら、書面を作成して、紛争が蒸し返されないようにしてください。弁護士がついていれば、法的に問題が生じないように書面を作成できます。
クレーマーの納得が得られない場合には対応をやめる
残念ながら、適切と思える解決案を示したにもかかわらず、相手の納得が得られないケースもあります。学校側の対応に問題がなくても、「誠意がない」などと難癖をつけ、繰り返し電話や面談を求めるのです。
その場合、提示した回答が最終的な方針であることを伝えるのがひとつの方法です。いつまでも理不尽な主張に付き合っていると、収集がつかなくなってしまいます。
相手によっては、執拗な電話など嫌がらせをしてくる場合もあります。弁護士に依頼すれば、クレーマーに対する警告や法的措置が可能です。万が一相手から訴訟を提起されたとしても、安心して対応を任せられます。
弁護士の選び方
クレーマーへの対応を弁護士に任せるときは、選び方が重要になります。
学校法人への対応経験が豊富な弁護士を選ぶ
大きなポイントが、学校法人に関する案件への対応経験が豊富な弁護士を選ぶことです。
学校現場では法律面だけでなく、教育的な配慮も必要になります。学校法人から依頼を受けた経験がない弁護士だと、法律面だけを考えて非現実的な対応をとりかねません。
学校法人への対応経験が豊富で業界の事情に精通している弁護士に依頼すれば、話が伝わりやすくスムーズに対処してもらえます。
事務所の場所は気にしすぎない
近くにある法律事務所の弁護士への依頼を考えている方が多いかと思います。たしかに、対面のやりとりは近くにいる弁護士の方が都合がつきやすいです。
もっとも、クレーマーへの対応は電話や書面でもできます。学校法人に精通した弁護士が近くにいない場合には、場所にこだわらずに探した方が良いでしょう。
学校法人における主なクレームの種類と対応方法
学校法人に寄せられるクレームは様々であり、正当な言い分の場合には、適切な対応が必要です。クレームの種類ごとに対応方法を解説します。
体罰・ハラスメントへの対応と防止策
教職員による体罰やハラスメントに関してクレームを受けた場合、まずは事実調査が重要です。当事者だけでなく関係者にも事情をよく確認し、客観的な証拠も収集して、事実が何かを見極めてください。
体罰やハラスメントが存在したと明らかになれば、学校側にも責任が生じ得るため、相手方との交渉が必要です。加害者となった教職員の懲戒処分も検討しなければなりません。
加えて、再発防止のためにルールを整備し、研修などを通じて周知徹底してください。内部通報窓口の整備も有効な方法です。
学費返還請求の判断と対応
入試に合格したものの入学を辞退する受験生から、支払い済みの入学金や学費の返還を求められるケースもあります。
学費については、返還が必要です。学費は学校法人が提供する教育そのものへの対価であるため、入学しない場合には請求できません。
対して入学金については、返還が不要と考えられています。入学金は学校に入学し得る地位を取得するための対価とされ、実際にも入学を前提として事務手続きを進め、費用が発生しているためです。
就職支援とキャリアカウンセリングの改善
学校法人が提供する 就職支援やキャリアカウンセリングに対して、卒業生・在校生やその保護者などからクレームがつけられる場合もあります。
中には「希望した企業に就職できなかった分を賠償しろ」といった、理不尽なものもあります。学生を特定の企業に就職させる義務は認められないため、学校側が得られなかった給与等を補償する必要はありません。
また、学生の内定先の企業から、内定辞退について損害賠償を求められるケースもあり得ます。しかし、学校は労働契約の当事者ではなく、請求に応じる義務はありません。
とはいえ、就職支援やキャリアカウンセリングは、いまや学校法人が提供する重要なサービスのひとつです。トラブルが生じないよう、適宜改善を進めてください。
学校法人の理事の変更でお困りの方は弁護士にご相談ください
当事務所では、学校法人の皆様の支援に力を入れて参りました。業界特有の事情も踏まえつつ、必要な法的サポートをいたします。理事の変更などでお困りの点がある学校法人関係者の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
「保護者からのハラスメントに限界!クレーマーやモンスターペアレントに対して学校としてできること」の関連記事はこちら
- いじめが発覚した際の学校側の対応を弁護士が解説
- 学校法人のM&Aのメリットやスキーム、流れを弁護士が解説
- 学校の広告や宣伝に関する不当表示や不正競争行為について
- 学校側で教員の内定取り消しができるケースって?弁護士が解説
- 教員からの残業代請求ってあり!?学校の残業代について弁護士が解説
- 私生活上の非違行為で教員の懲戒処分ってできる?弁護士が解説
- 学校・教育機関への誹謗中傷に強い弁護士をお探しの方へ
- 問題教員・モンスターティーチャーへの対応に強い弁護士をお探しの方へ
- 学校経営における教員の鬱・適応障害などへの対応|学校側の弁護士が解説
- 学校の広告にはどんな規制がある?誇大広告や罰則について学校法人に強い弁護士が解説
- 【学校側の弁護士】学校事故の保護者・生徒の対応に強い弁護士をお探しの方へ
- 授業で許される著作権って?学校法人に強い弁護士が徹底解説
- 共通テスト流出・・・学校法人における問題漏洩について弁護士が解説
- 学校側の弁護士が解説 – 学生側から留年・退学・除籍等に不服申し立てを受けてしまったら
- 保護者からのハラスメントに限界!クレーマーやモンスターペアレントに対して学校としてできること
- 学校法人の理事の選任・変更について学校側弁護士が解説
- 学校側弁護士がアカハラの防止・措置について解説 – 大学などにおけるアカデミックハラスメント
- 学校と個人情報保護法の関わりを弁護士が解説 – どこまでの提供ならOK?
- 授業や資料における著作権の注意点!学校側弁護士が解説
- 教員の定年と再雇用制度について学校法人に強い弁護士が解説
- 教員同士のパワハラや学校の長時間労働を労務問題に強い弁護士が解説
- 学校法人における就業規則の重要性について弁護士が解説
- モンスターペアレントからの誹謗中傷・悪口にどう対応すればいい?学校・幼稚園・保育園側の弁護士が解説
- 学校の労務トラブルや教職員のパワハラについて弁護士が解説
- 休職を繰り返す教員への対応 – 学校運営におけるメンタルヘルスを弁護士が解説
- 塾・予備校の弁護士が送迎トラブルや騒音問題への対処を解説
- 保護者トラブルって録音してOK?学校や保育園・幼稚園側の弁護士がモンスターペアレント対応について解説
- 生徒への暴言や行きすぎた指導をする教師に対して学校側ができること
- モンスターペアレントに法的措置は可能?保護者への対応や学校運営のポイントを解説
- 学校事故の事例・対応法って?保護者対応などについても弁護士が解説
- 学校側からモンスターペアレントに法的措置は可能?モンペの対応を学校・幼稚園・保育園に強い弁護士が解説
- 給食費を払わない家庭からの徴収について学校法人に強い弁護士が解説
- 給食費を払わない親への請求方法!顧問弁護士なら支払督促が可能です
- 学校運営で知っておくべき基準!体罰はどこから?教師への措置について弁護士が解説
- 学習塾・予備校のための弁護士 – 教育支援業の法律相談は西村綜合法律事務所まで

 メール・Web
メール・Web